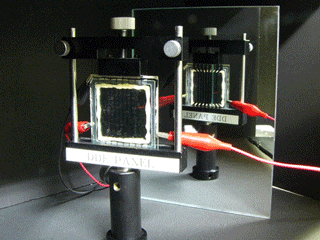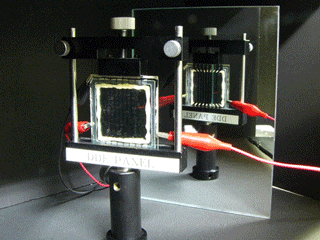携帯電話などのディスプレイとして薄型・軽量・低消費電力の液晶パネルが用いられています。
折りたたみ式の端末機では2枚の液晶パネルを搭載し、開いた状態と閉じた状態で別々の液晶によって表示しています。
1枚のパネルでいずれの状態においても表示が可能であれば、携帯電話はより薄型・軽量化が可能になります。
近年、透明有機ELパネルを用いた超薄型の両面発光ディスプレイの可能性が示されています。
この透明有機ELパネルを表裏から同時に表示を見る場合、一方は正常に表示可能ですが、もう一方の面では表示が左右反転することから、2人が対面した状態で表示を見ることが不可能となります。
また、この両面発光有機ELディスプレイは常に両面に発光しているため、携帯電話への応用を考えた場合、閉じた状態でも内側へも発光することになり、効率の点からも大きなロスとなります。
上記の問題点を解決することが可能なデバイスとして我々はデュアル・ドライブ・エミッション(DDE)パネルを開発しました。
その概略図を左図に示します。
このパネルはガラスなどの透明な基板上に第1の透明電極を形成し、第1の有機EL層、反射電極、第2の有機EL層、第2の透明電極を順次積層することによって、実現されます。
第1の有機EL、第2の有機ELから得られる発光は、それぞれ第1の透明電極、第2の透明電極を通って得られ、それぞれの有機ELは独立に動作します。
右図に試作したDDEパネルの発光写真を示します。
一枚の基板の両側で独立した発光が得られていることがわかります。
写真右側は鏡に反射した像となっていますので、左右反転しています。

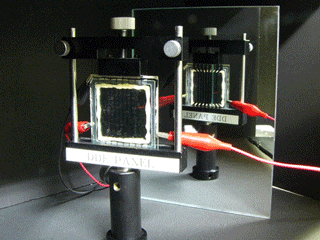
[参考文献]
- "Dual Drive & Emission Panel",
T. Miyashita, S. Naka, H. Okada, and H. Onnagawa,
Jpn. J. Appl. Phys. 44 (6A) 3682-3685 (2005).
- 北日本新聞 2005年(平成17年) 7月25日朝刊
- 建設工業新聞 2006年(平成18年) 2月 7日朝刊
携帯電話はもはや電話の機能だけではなく、PDAやデジタルカメラなどの機能を付加し、重要なモバイル情報端末としての地位を固めています。
携帯電話には多機能化とともに、薄型・軽量化が要求されています。
この薄型・軽量化を実現可能なデバイスとして我々はバイ・ファンクション・マトリクス(Bi-Matrix)パネルを開発しました。
その概略図の一例を左図に示します。
このパネルはガラスなどの透明な基板上に第1の透明電極を形成し、有機EL層、中間走査透明電極、有機フォトダイオード(PD)層、不透明電極を順次積層することによって、実現されます。
有機EL層からは発光を、有機PD層では透明電極を通して受光することが可能になります。
つまり1枚のパネルで発光ディスプレイとスキャナの複合機能を有することが可能になります。
また、2つの異なる機能を有するパネルを貼り合わせるなどの工程が必要のない、単純な構造を有しており、コストの面からも有効であると考えられます。
また、プラスチックフィルムなどの基板上に作製することで、より薄く、より軽量なフレキシブルなパネルの実現も可能です。


[参考文献]
- "Organic Bi-function Matrix Array",
Y. Matsushita , H. Shimada, T. Miyashita, M. Shibata, S. Naka, H. Okada and H. Onnagawa,
Jpn. J. Appl. Phys. 44 (4B) 2826-2829 (2005).
有機ELと有機PDを積層させた複合機能デバイスであるBi-Matrixの発展形として、単一の有機デバイス構造により発光と受光機能を実現できるマルチファンクションダイオード(MFD)を開発しました。
本デバイスでは、順バイアスで発光、逆バイアスで受光動作をさせます。
また、将来的には、光照射による太陽電池動作も期待できます。
このMFDの実現で、パソコンや携帯電話等のモバイル製品応用へ向けたスキャナ機能付きディスプレイの実現が期待されます。


[参考文献]
- "Organic Multifunction Diodes Operable for Emission and Photodetection Modes",
H. Shimada, J. Yanagi, Y. Matsushita, S. Naka, H. Okada and H. Onnagawa,
Jpn. J. Appl. Phys. 45 (4B) pp.3750-3753 (2006).
大型フラットパネルディスプレイなど、大面積基板上に微細なデバイスを集積するためには、個々のデバイス作製技術のみならず、デバイス間の配線技術が重要となります。
ここで、大面積・フレキシブル基板上への配線形成への従来フォトリソグラフィ技術の適用を考えると、高精度光学系の大型化、基板平坦性・変形に伴うアラインメント精度の確保、低温プロセス化などの課題が考えられます。
また、蒸着やスパッタ法による配線形成では、装置の大型化・高コスト化が課題となり、これらの課題を解決する新たなパターニング技術が望まれています。
我々は、銀ナノ粒子配線と干渉露光を組合せた微細配線形成法を開発しました。
まず、疎水性ポリイミドを干渉露光法によりパターニングすることで、ガラス親水部とポリイミド疎水部からなる凹凸を作製します。
この凹凸の親水部に銀ナノ粒子分散液を流し込み、乾燥させることで微細配線が形成されます。
本方法により、3μm幅の配線形成が確認されました。
これにより、大面積基板上への配線形成が期待されます。
図にこの方法で用いた干渉露光概略図と原子間力顕微鏡(AFM)像を紹介します。


[参考文献]
- "干渉露光法を用いたナノ粒子配線の作製",
岡田 茂, 中 茂樹, 岡田 裕之, 女川 博義,
電子情報通信学会論文誌 C J88-C (8) 670-671 (2005).
PDAや携帯電話等のモバイルを中心とした表示ディスプレイとして、有機EL素子が注目されています。
有機ELは、簡単な構造で作製が容易で、それに伴うコスト低減が期待できます。
しかし、高価な真空装置や微細パターン形成等の高度な技術が要求されます。
ここで、大気中成膜可能で微細パターン形成可能な方法としてインクジェット(IJP)法があります。
当研究室では、1987年夏よりIJPによる有機EL素子の開発に着手し、1988年秋季応用物理学会、Asia Display98 等より成果を紹介してきました。
ここで、これまで開発されてきたIJP法による有機EL素子作製では、パターニングによる隔壁(バンク)形成と高精度のインク吐出による位置合わせが必要でしたが、我々は、簡単・高歩留まりにデバイス作製可能な自己整合IJP有機EL素子を提案・実現してきました。
自己整合とは、自動的な位置合わせ形成方法であり、下図に概略図を示します。
透明電極付きガラス基板に絶縁膜を形成し、IJP法で有機発光材料を吐出します。
吐出されたインクの溶媒で絶縁膜を溶解し、乾燥過程で発光部が形成されます。
周辺部はデバイスのバンクとなります。実際に、これまで作製した有機ELパネルを以下に紹介します。


[参考文献]
- "Top-Emission Organic Light-Emitting Diodes with Ink-Jet Printed Self-Aligned Emission Zones",
R. Satoh, S. Naka, M. Shibata, H. Okada, H. Onnagawa and T.Miyabayashi,
Jpn. J. Appl. Phys. 45 (3A) pp.1829-1831 (2006).
- "Self-Aligned Bank Formation of Organic Electroluminescent Devices Using Ink-Jet Printing Method",
R. Satoh, S. Naka, M. Shibata, H. Okada, H. Onnagawa, T.Miyabayashi and T. Inoue,
Jpn. J. Appl. Phys. 43 (11A) pp.7725-7728 (2004).
- "Ink-Jet Printed Organic Electroluminescent Devices",
K. Yoshimori, S. Naka, M. Shibata, H. Okada and H. Onnagawa,
Proceedings of the 18th International Display Research Conference (Asia Display '98) pp.213-216 (1998).
RFIDタグやIDカードなど、軽量、フレキシブルかつ省エネルギーで動作するユビキタスな情報機器用トランジスタとして、有機電界効果トランジスタ(OFET)が注目されています。
その高性能化には、短チャネル化、移動度・相互コンダクタンスの向上、自己整合化、パターニング技術の確立、安定性向上等の課題があり、電荷分配による書込み電圧の変化、寄生素子効果の低減、フォトリソグラフィ工程の際にマスク合わせが不要となると言う観点より自己整合技術の導入が有効です。
我々はOFETの高性能化のため、背面露光法を用いた自己整合OFETを実現しました。
図(a)~(f)に、背面露光法を用いた自己整合プロセスにより素子作製を示します。
本方法により、ゲートとソース/ドレインのオーバーラップが0.5ミクロン程度と小さくなり、集積回路を構成した際の電荷分配による電圧低下や信号伝搬遅延を最小限にし、高速動作が実現できます。





[参考文献]
- "Self-Aligned Organic Field-Effect Transistors Using Back-Surface Exposure Method",
T. Hyodo, F. Morita, S. Naka, H. Okada and H. Onnagawa,
Jpn. J. Appl. Phys. 43 (4B) pp.2323-2325 (2004).
有機EL素子は、厚さ数10nmといった極薄発光層の中で発光します。
その光は透明電極やガラス基板を通って外部に放出されます。しかし、空気より屈折率の大きな発光層中で発生した光のうち真正面に出てくる光はスネルの法則により全体の約20%に過ぎません。
つまり、有機EL内部で発生した光のおよそ80%は、素子あるいはガラス基板中を導波し基板正面に取り出し出来ません。
その対策として、ガラス基板の光取り出し面上に光干渉の無いランダムドット形状を形成することで、従来内部に閉じ込められていたガラス-空気界面での光の一部を外部に出すことに成功しました。



[参考文献]
- "Improved Light Outcoupling in Organic Electroluminescent Devices with Random Dots",
A. Kitamura, S. Naka, H. Okada, and H. Onnagawa,
Jpn. J. Appl. Phys. 44 (1B) pp.626-629 (2005).
有機EL素子における代表的な作製プロセスとしては、蒸着系プロセスと溶液系プロセスがあります。
溶液系プロセスは、蒸着系プロセスよりも簡単作製・大面積化可能・高材料利用効率など多くの利点を持っており、課題とされる作製コストの低減可能な方法として期待されています。
ここで、従来、溶液系プロセスでは溶液化が容易な高分子材料が用いられてきました。
しかし、高分子材料は、残念ながら最高性能が低分子系材料に劣るのみならず、精製の難しさ、膜の不均一に伴う伝導・発光特性の不均一などの諸問題を持ち、かつ信頼性の点で低分子材料よりも劣っています。
一方、低分子材料は高純度、高輝度・高効率、良好な色再現性、長寿命などの優位性があります。
そこで、もし高分子材料を低分子材料に置き換えることができれば、低分子系蒸着デバイスと同等の素子性能、同等の信頼性を実現できる可能性があります。
諸検討の結果、最高性能を示すりん光系低分子系有機材料による溶液プロセスで、同一構造を有する蒸着系デバイスと同等の性能と信頼性を実現することに成功しました。
現在、本成果を利用し、自己整合IJP法を用いた有機EL素子の実現に取り組んでいます。



[参考文献]
- "Durability Test of Solution-Processed Organic Electrophosphorescent Devices with Small Organic Molecules",
M. Ooe, S. Naka, H. Okada and H. Onnagawa,
Jpn. J. Appl. Phys. 45 (1A) pp.250-254 (2006).
一般に、有機EL素子の有機膜の成膜には、真空蒸着法が用いられています。
しかし、真空蒸着法による素子作製は大面積化が難しく、装置も高価であり、より安価で大面積量産化が可能な成膜法が望まれています。
我々は、有機薄膜の高速成膜プロセスとしてスプレイ法を提案いたしました。
本方法により、簡単、高速かつ均一な成膜が可能になります。さらに、スプレイガンの工夫により、大面積基板にも対応可能です。
この様にスプレイ法は大面積化・量産化に優れた次世代有機EL素子作製法として有望と考えています。

[参考文献]
- "Sprayed Organic Electrophosphorescent Devices with Small Organic Molecules", T. Echigo, S. Naka, H. Okada, and H. Onnagawa,
Jpn. J. Appl. Phys. 44 (1B) pp.613-616 (2005).
- "Spray Method for Organic Electroluminescent Device Fabrication",
T. Echigo, S. Naka, H. Okada and H. Onnagawa,
Jpn. J. Appl. Phys. 41 (10) pp.6219-6222 (2002).
液晶ディスプレイ用の広視野角化の技術として、MVA方式、ASM方式、IPS方式、OCB方式、VA方式、光学的補償方式など様々な方法が提案されています。
その視野角特性改善の方法の1つとして配向分割技術があります。
この方法は、1画素を複数の領域(ドメイン)に分割し液晶配向方向を変え、視野角を改善する方法です。
我々は、印加電圧によるマルチドメイン化による視野角特性向上と電圧-透過率特性の改善を目指し、同心円電極と放射状電極を用いた液晶表示方式を提案しました。
電極構造は、偏り無く、色変化の少ない視野角特性を目指し、上下左右対称に設計しました。
この方式を用いることで、広視野角、電圧-透過率特性の制御性、画素形状による良好な表示を実現しました。



[参考文献]
- "Field-induced Microdomain Liquid-Crystal Display Modes",
H. Ohno, H. Okada and H. Onnagawa,
J. Appl. Phys. 93 (12) pp.9630-9633 (2003).
- 岡田 裕之,大野 洋,女川 博義 液晶表示素子 特許3656103号(2005.3.18)
最近の大型テレビ向けのパネル開発では、広視野角化や応答時間の改善が望まれています。
本改善の一方法として、垂直配向とマルチドメイン形成の組合せが有望です。
単なる垂直配向液晶素子では、電圧印加による液晶の傾き方向を規定出来ません。
また、対称構造を利用すると、光干渉や回折による違和感が問題となります。
そこで、電極上のランダム位置に、まるで虫食いの様に穴を形成することで、電圧印加時の液晶配向を半球状に制御可能な液晶表示方式を提案・実現しました。
本方式の適用で、広視野角、高速応答かつ違和感の無い表示方式が可能となります。


[参考文献]
- "Wormhole Liquid Crystal Display Modes- Position Controlled Domains with Half Cut Droplet",
M. Inaba, H. Okada and H.Onnagawa,
Euro-display '02 P-26 (2002).
- 岡田 裕之,鰍場 真樹,女川 博義 液晶表示素子 特許3723834号(2005.9.30)