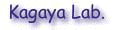 つぶやき2004
つぶやき2004
「考える能力」の覚醒
最近,機会があって講義以外にも教育に関わる仕事をすることが多く,これに関するつぶやき。これまで大学では,教育については個々の経験にもとづき自由にやっていたように思う。そのため個性的で伝説の(?)教授等がどこの大学でも1人や2人は存在した(する?)だろう。このように自由に教育していても多くの学生は育っていたように思うが,これは個々の学生が「いい・わるい」「こうなりたい・なりたくない」等という「「自分の考え」を,意識してか無意識にかは別として,ある程度持っていたためではないかと思っている。しかし今,「自分の考え」を持っている学生が少なくなってきているように思う。もともと考える力がないのか,それとも考えることをさぼっているだけか...その違いはとても大きい。もし考える能力があるのであれば,それを覚醒させる仕掛けを我々はしなければならない。この仕掛けこそ,大学に必要な「教育」なのかもしれない,と今頃ようやく気づいてきた。基本概念の徹底理解に加え,学生の考える能力を開花させる教育を実施すれば,卒業研究の出来もこれまで以上になるのではないだろうか。では考える能力をのばすためにどのような仕掛けがあるか...現在注目されている「Project Based Learning」という手法が興味深い。「特色GP」主導で実施中の「工学特論(創造工学特別実習)」がまさにこれで,担当者として試行錯誤しながら学生の進化を観察している。これだけでなく,より多くの「仕掛け」を考えていく必要があるだろう。後は「考える能力」を見抜く選抜(入試)方式が,富山大学の将来を左右する大きな課題か....。