�������Ԑ��������ڃT���v�����O�@��p�������k�����Ήߒ��̌���
Investigation of Compression Ignition Process by Direct Sampling of Intermediate Species in Cylinder
��������(Masaharu KASSAI)
1.�@����
�@���������N���[���Ȕr�C���������\�������k�����iHCCI�j�@�ւ́C�O�I�Ȓ��@�\�������Ȃ����ߒ��ΐ��䂨��сC�������̋}���R�Ă̗}�����ۑ�ƂȂ��Ă���DHCCI�͋ψ�C�������Ƃ��Ă̈��k���������������n�ł���C�Y�����f�̎����Ήߒ����ڍׂɌ������邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�D
�@���ΐ��̍����Y�����f�ɂ����鎩���͗≊�ƔM���̓�i�K���琬��C�≊�ł̔M��������сC�≊���ł̐����ω��C�ߎ_�����f�iH2O2�j�Ȃǂ̒��Ԑ������̒~�ς��M���̔��������ɉe�����y�ڂ��Ƃ����[1]�D���������������ŁC�≊�������x�z����ቷ�_�������̌����͕s���ł���D
�@���������ɂ�����ߋ��̌����ł́C�W���`���G�[�e���iDME�j��R���Ƃ��C�≊�̂ݔ�����������ɂ�����l�d�Ɍ^���ʕ��͊��p�����r�C���͂���C�A���f�q�h���̒��Ԑ��������≊�i�s�����Ȑ��䂷��������ʕ]������[2]�D�܂��CFT-IR��p�����r�C���͂ɂ��DME�R�Ăɂ�����HCOOH�CHCOOCH3���ʂ���[3]�D
�{�����ł́CDME�̒ቷ�_�������̃��J�j�Y�������̒Y�����f�R���ɂ����p�\�ł��邱�Ƃ��m���߂邽�߁CPRF�iPrimary Reference Fuel�j���\������m���}���w�v�^���in-heptane�j��R���Ƃ����ꍇ�ɂ��Č������s�����D�v����@�Ƃ��ẮC�{�������ŐV���ɊJ�����ꂽ�������ڃT���v�����O�@[4]��p���C�≊�ɂ�����R������ђ��Ԑ����������ԕ����v�������D
2.�@�������@����є����v�Z
2.1�@���茴��
Fig.1�ɃG���W�������ɂ�����K�X�������ނ���ю��ԕ���\�̊T�O�}�������D���̗l�ɁC�o���u�J�َ��Ԃɑ��̎悳���T���v�����O�K�X�����͕ω�����D�{�����ɂ����ẮC�p���X�o���u�̊J�َ��Ԃɑ��鐬���Z�x�ω����獷�����Ƃ邱�Ƃ�Core Volume�݂̂̃T���v�����O���s�Ȃ��C���蕨���ł��钂�f�iN2�j�ɂ���ċK�i�����]�������D���̊J�َ��ԍ����@�ɂ�荂���������ԕ���\����������D
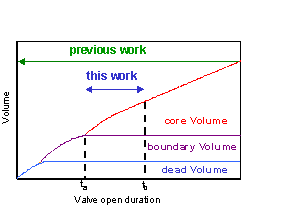
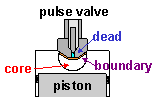
Fig.1 Concept of pulse gas sampling from engine cylinder
2.2�@�������@
�@���k���Ύ��G���W���i�r�C��383cc�C���k��8.0�j���O�����[�^�[�ɂ��쓮���C�펞600rpm�ɕۂD�R���ł���n-heptane�͗\�ߕ��˗ʌ�����s�����C���W�F�N�^�ɂ�蕬�˗ʂ����C���ʔ�����肵���D�����ɑ����������̓Z���T�ƃN�����N���Ɏ��t�������[�^���[�G���R�[�_�[�ɂ��N�����N�p�x���̎w�����v�������D
�@�{�v�����u�ɂ�����T���v�����O���C����Fig.2�Ɏ����D
�G���W���w�b�h�Ɏ��t�����p���X�o���u�iGeneral valve�C009-0659-900�j�̊J�قɂ�萁���o���K�X�������C���J�j�J���u�[�X�^�[�|���v�ɂ��A�������r�C���s���`�����o�[����Ďl�d�Ɍ^���ʕ��͊�iANELVA�CM-400GA-DTS�j
�ɓ��������o�����D�N�����N���Ɏ��t�������[�^���[�G���R�[�_�[�ƃp���X�o���u�h���C�o�[�̓�������邱�ƂŁC�C�ӂ̃N�����N�p�x�Ńp���X�o���u���J�قł���D
�@����v�����s�������w���n-heptane (m/e = 100)�CHCHO(m/e = 30)�CH2O2(m/e = 34)������Cn-heptane�ɂ��Ă͗≊�����O�ł���ATDC-80deg�ɂ�����v���l�������R���Z�x�ł���Ƃ��CHCHO�ɂ��Ă͔Z�x���m�̃T���v���K�X��p���čZ�����s�����D
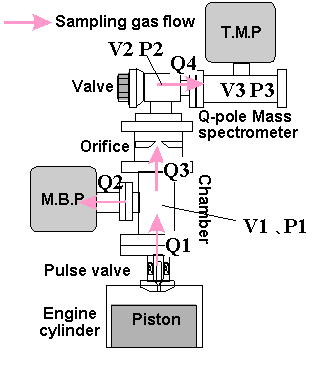
Fig.2 Pulse Sampling Line
2.3�@�����v�Z
�������ʂ̔�r�Ƃ��Ď����Ŏg�p�����G���W���Ɠ��l�̑̐ϕω���^���CCHEMKIN�W��ICEngine��p�����f�M���0�����̉��w���͊w�v�Z���s�����D�������f���ɂ́C Curran���n-heptane�ڍה����@�\[5]��p�����D
3.�@�������ʂƍl�@
3.1�@�J�َ��ԍ����@�̕]��
�@Fig.3�ɋz�C���x410K�C���ʔ�0.35�C�≊�̂ݔ�����������ɂ����āCATDC+60deg�ŊJ�َ��Ԃ�0.5�`1.5ms�ƕω�����������n-heptane�����HCHO��N2�K�i���M�����x�̕ω��������D�J�َ��Ԃ𑝂₵�Ă����ƁC�R���ł���n-heptane�͌������C���Ԑ������ł���HCHO�͑������Ă��邱�Ƃ�����D����̓T���v�����O�̈悪�ǖʋߖT�̖������̈悩��R�Ă̒��S���Ɉڍs�������Ƃ�\���Ă���D�e�N�����N�p�x�ɂ�����]���ɂ��C�{�����̌v�������ł͊J�َ���0.9ms�����1.5ms�ł̍�������邱�ƂƂ����D
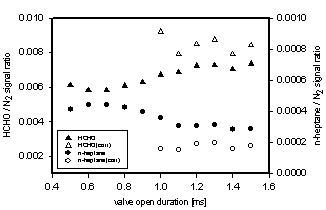
Fig.3�@n-heptane/N2 and HCHO/N2 Signal ratio as a function of valve open duration. Intake gas temperature=410K, Equivalence ratio = 0.35, ATDC+60deg.
3.2
���ԕ����v��
�@Fig.4�ɋz�C���x410K�C���ʔ�0.30�C�≊�̂ݔ�����������ł̈��́E�M�����v���t�@�C������сCn-heptane�CHCHO�̎��ԕ����v�����ʂ������D�����v�Z���O�����ł���̂ɑ������͋�ԕ��z�������Ă��邽�߂ɍ��ق͂���
���̂́Cn-heptane�̏����HCHO�̐����v���t�@�C�����擾���邱�Ƃ��o�����D
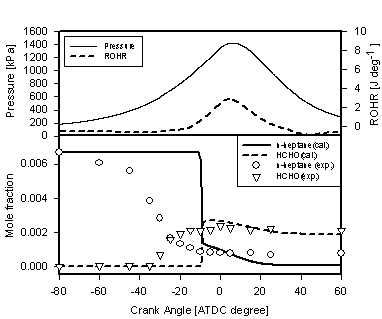
Fig.4 Profiles of Pressure and ROHR, Mole fraction of n-heptane and HCHO. Intake gas temperature=410K, Equivalence ratio = 0.35, ATDC+60deg.
�@Fig.5�ɓ��ʔ��ω��������ۂ�n-heptane�����HCHO�̍ŏI�ʂ����������R���Z�x�ŋK�i���������ʂ������D�z�C���x410K�ɂ�����M�����������͌v�Z�C�����Ƃ��ɂ��悻���ʔ�0.40�ł���C���ʔ䂪�オ��M�������ɋ߂Â��قǁC�R����������HCHO�������͍����Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����D
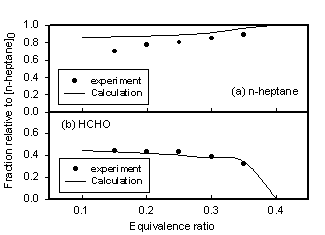
Fig.5�@Fraction relative to initial n-heptane concentration as a function of equivalence ratio. (a) n-heptane consumption, (b) HCHO. Intake gas temperature=410K.
3.3�@ H2O2�v��
H2O2�v���ɂ����ẮC��C���ɑ��݂���O2�̓��ʑ̂ł���18O(m/e = 34)�̉e�����l������K�v������D�≊�ɂ��H2O2�͐������邪�C18O�͈ꕔ�����邽�߁CO2�����18O�̃V�O�i�����x�䂨��є��������قړ������Ƃ̉���̉��C�����v������O2���狁�߂�ꂽ18O�̐M�������������������s�����D���̌���Fig.6�Ɏ����悤��H2O2�̑����v���t�@�C��������ꂽ�D
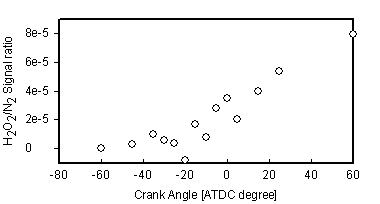
Fig.6�@Profile of H2O2/N2 Signal ratio. Intake gas temperature = 410K, Equivalenve ratio = 0.35.
4.�@���_
�@n-heptane��R���Ƃ���HCCI�@�ւł̗≊�ɂ��āC�����K�X�ڃT���v�����O�v�����C��ʂ��s�����D�����v�Z�Ƃ̔�r���玟�̌��_���D
1. n-heptane�̒ቷ�_�������ɂ��C�G���W�������ł�n-heptane�̏����HCHO�CH2O2�̐��������ԕ����v�����邱�Ƃ��ł����D
2. ���ʔ�ɑ���R����������HCHO�̐��������̕ω��͌v�Z�ƊT�ˈ�v���C��ʐ�������D
3. �_�f���ʑ̂��l�����邱�Ƃɂ��H2O2�̑����v���t�@�C�����擾�ł����D
�Q�l����
[1]Westbrook C. K., Proc. Combust. Inst., 28, 1563 (2000).
[2]Yamada, H. et al., Combust. Flame, 140,24 (2005).
[3]��F��C��43��R�ăV���|�W�E���u���W�C(2005)�C228
[4]�g���C��42��R�ăV���|�W�E���u���W�C(2004)�C289
[5]H.J.Curran et al., Combust. Flame, 114,149 (1998).