DME�̉ߔZ�\�����Ή��̍\���ɑ���ቷ�_�������̌���
Effect of Low-Temperature
Oxidation on the Structure of Rich Premix DME Flame
�{�V�@�[���Y(Keitaro MIYAZAWA)
1.
����
�\�������k���@�ւɂ����钅�Ύ�������C�ΉԒ��Ύ��G���W���ɂ�����m�b�L���O�̗}���Ɋ֘A���āC�ቷ�_���������ߔN���ڂ���Ă���D�Y�����f�R���ł͒ቷ�_���������܂ޏڍה����@�\���\�z����C���Ήߒ��̐��l�v�Z���\�ƂȂ��Ă���D����甽���@�\�́C�}�����k�@�C�Ռ��g�ǁCJet Stirred Reactor���̎����f�[�^���Č�����l�ɒ��߂��ꂽ���̂ł��邪�C��蕝�L�������C�قȂ鑪�荀�ڂ̎����ɂ�茟����C���ǂ���邱�Ƃ��]�܂����D
�@�w�����ʃo�[�i�Ή��͒ʏ��C�����ł�mm���x�̃X�P�[���Ńo�[�i���o�����ɖ�������Ή��ƂȂ邪�C�ߔZ�����ł�cm�̃I�[�_�[�̕����オ�荂���ƉΉ������������قȉΉ������I�ɐ����ł���D���ɒቷ�_���ߒ������R���Ő������e�Ղł���C�≊�Ɛ��ƌĂԓ�i�\���̉Ή��ƂȂ�D���̌��ۂ͌Â���Powling[1]�ɂ���Č�������C�ŋ߂ł͖쐨��[2]���W�G�`���G�[�e���̓�i�Ή�����I�ɐ������C���x���z����≻�w��T���v�����O���s���Ă���D�������Ȃ���C�ڍׂȔ����@�\��p�������l�v�Z�Ȃǂ͍s���Ă��炸�C���̓���ȔR�Ă̐����@�\�͊m�������Ƃ͌����Ȃ��D
�@�{�����ł�DME(�W���G�`���G�[�e��)��p���ĉߔZ�\�����Ή��������I�Ɍ`�����C���l�v�Z�������Ă��̐����@�\���𖾂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ����������s�����DDME��p���������͂���܂ōs���Ă��Ȃ����C�ቷ�_���@�\�������Ɏ����Ƃ��m���Ă���C�W�G�`���G�[�e���Ɠ��l�ɓ�i�̒ቷ�x�����`�������Ɨ\�z�����D�܂��C��]�̂���ڍה������f�������݂��邱�Ƃ���C�{�����̖ړI�ɂƂ��čœK�̑Ώۂł���ƍl�����D
2. �������@
�쐨��̎������Q�l�ɂ��Ė{�����ō쐬�����\�����w���Ή��o�[�i��Fig.1�Ɏ����DDME�Ɗ�����C�̓}�X�t���R���g���[����p���ė��ʂ߂��o�[�i�ɓ��������D���̍ہC�\�����K�X�̓r�[�Y���[�U�����V�����_�[���ŏ\�����������D�C�̂̓n�j�J���q�[�^�[�ŗ\�M����C�Č������ŗ��ʂ��ψꉻ���C����Ƀn�j�J����ʂ邱�ƂŐ�������R�Ď��ɓ��������(���o���a50mm)�D�Ή��͉~���K���X�Z��(���a100mm)���ŕێ������D�Ή��ʂ̕ϓ���}���邽�߃K���X�Z���V��ɋ��Ԃ�ݒu�����D�ߔZ�R�Ă̍ۂɂ͋��ԏ�Ɏ��Ӌ�C�Ƃ̊g�U�Ή����`�����Ďc���R��������������D��������̉��x���z����͑f���a100��m��K�^�M�d��p���C�K���X�~�����S����Ōv�������D�M�d�ɑ����t�˂ɂ�鉷�x�����̕�͍s���Ă��Ȃ��D


Fig. 1 Schematic of experimental apparatus and photograph of DME flame
3. ���l�v�Z
�@�ڍה����@�\��Curran�炪��Ă������f��[3]��p���C�Ή��̃V�~�����[�V�����ɂ́CCHEMKIN�U��Flame�C�y��CHEMKIN�W��Premix���g�p�����D�����͒f�M�ꎟ���w���Ή��v�Z�ɂ��āC�A���������ƃG�l���M�[�ۑ������ڍ��w�������J�j�Y���ƘA�����Ē�틫�E�l���������R�[�h�ł���D�v�Z���[�h�ɂ͎��R�`�d�Ή��ƃo�[�i�Ή������邪�C�ߔZ�\�����w���Ή��ɑ��Ă͎��R�`�d�Ή��̌v�Z���[�h���g�p�����D����͖{�Ή��ł͕����オ�肪�傫���C�Ή��f�ʐς����o�����ʐςł͂Ȃ��K���X�Z���̒f�ʐςƂ��Č`������C�o�[�i���ւ̔M�ړ��͂قƂ�ǂȂ��ƍl�����邽�߂ł���D�܂��C���͂�1�C�����Ƃ����D
4. ���ʂƍl�@
�\�����K�X�̗��ʂ͓��ʔ�4.0�ʼnΉ����ł���ʒu�ł��鐁�o��������64mm�̍����ň��肷��220 cc/s�Ƃ��C���o�����̉��x��460K�Ƃ����DFig.2�ɓ��ʔ�=4.0, 4.5, 5.0�̏����ɂ����đ��肳�ꂽ���x���z�ƁCFlame�̌v�Z���ʂœ���ꂽ���x���z�������D�ߔZ�\�����w���Ή��o�[�i�ŕێ����ꂽ�Ή���Flame�ɂ�鎩�R�`�d�Ή��ł�x�������̊�_���{���I�ɈقȂ邽�߁C���x�̗����オ��_��x�������ɍ��킹�Ă���D�v�Z�̓q�[�g���X�������̂ŁC�Ή��O��̉��x���z�͎����ƈقȂ�D�Ή��I�[�̉��x����v����l�Ɍv�Z��̏������x���z���߂��390K�ƂȂ����D�S�Ă̓��ʔ�ɑ��āC���x�v���t�@�C���y�щΉ����Ɋւ��đ���l��Flame�ɂ��v�Z�l���ǂ���v���Ă���D�R�đ��x�ɂ��ẮC���ʔ�4.0��Flame�̌v�Z���ʂł�3.63cm/s�ł������D�������ʂɑ��Ă̓K���X�Z�����a���ς̗�����390�j�Ɋ��Z�����4.0cm/s�ƂȂ莩�R�`�d�Ή��Ƌ߂��l�ƂȂ����D�쐨��̓W�G�`���G�[�e���ƃm���}���w�v�^����R���Ƃ��ē�i�K�̔��������Ή��������ł��邱�Ƃ��m�F���Ă���D�{�������u�ł��W�G�`���G�[�e���ł͓�i�K�������m�F�ł������CDME�Ή��ł͔����͈�i���������Ȃ��D���̔����т͉��x�㏸�̒��ԓ_�t�߁CFig.2�ł͖�0.7cm�̈ʒu�ɂ���D�v�Z�̉��x�v���t�@�C���͊ɂ�����ł��邪��i�\����L���Ă���C�����ɂ�����Ă���l�Ɍ����邪���m�ł͂Ȃ��D���w��Z�x�v���t�@�C���ɂ���Ċm�F���Ă������Ƃ�����̉ۑ�ł���D

Fig. 2 Measured and calculated temperature profiles of DME flat flames.
Fig.3�ɉΉ����ƔR�đ��x�ɂ���DME��Flame�v�Z���ʂƎ������ʂ̔�r�������D�ቷ�_�������̌��ʂ��������邽�߁C�ቷ�_���@�\�������Ȃ����^����Flame�v�Z���s���C���̌��ʂ����킹�Ď����D���^���̔����@�\�ɂ�GRI-Mech 3.0��p�����D�Ή����̎Z�o�ɂ͔R�đO��őQ�ߐ��������C���̉��x�͈̗͂�������10%��菜������Ԃ��Ή����Ƃ��ĎZ�o�����D�R�đ��x�̎Z�o�́C������̌v�Z�����o�����̉��x��390K�Ƃ��Čv�Z���C���̐��o�����ł̖��R�K�X������R�đ��x�Ƃ����D
DME�ɂ��Ă̌v�Z���ʂł́C���ʔ䑝���Ƌ��ɔR�đ��x�͒ቺ���C�Ή����͑��債�Ă������C���̕ω����͓��ʔ�3�ȏ�Ŋɂ₩�ƂȂ�C5�ȏ�ł��Ή��͌`�������D�����l�̂��铖�ʔ�3.5–5�͈̔͂ŔR�đ��x�͌v�Z�l�ƊT�ˈ�v���Ă���D������^���̌v�Z�l�͓����ʔ��DME�����R�đ��x�͒x���C�Ή����͍L���D���ʔ�2.3�܂ł�DME�̌��ʂ��0.5�ᓖ�ʔ䑤�փV�t�g�����l�ɐ��ڂ��C���ʔ�2.3�ȏ�ł͌v�Z�����������邱�Ƃ�����C����
�łقڔR�Č��E�ƍl������D
�����̂��Ƃ���ᓖ�ʔ䑤�ł�DME�ƃ��^���ɋ��ʂ��č����R�Ă̋@�\���x�z���CDME�݂̂��R�Ă��鍂���ʔ�ł͒ቷ�_�����x�z���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����\�������Ă���D
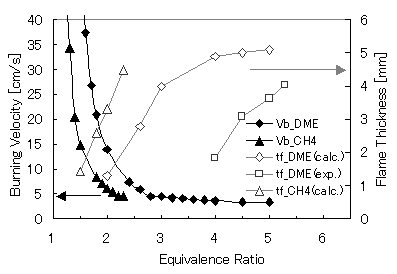
Fig. 3 Burning velocity(Vb) and flame
zone thickness(tf) of DME and methane flames (��=1.2-5.0).
Fig. 4�͑w���\�����Ή��̊Ȉ��_�ł���M���_�W�����ē���ꂽ���x�v���t�@�C�����C�������x�̕ω��Ŏ������O���t�ł���D�ꎟ���̉Ή��̗��_���́C
![]() (1)
(1)
�ł���D�M�`���ƔR�Ĕ��M�̃o�����X�̌��ʁC���Ή����`������C���M��q�Ɣ������x�萔k(T)��^����ƁC�����y�яo�����x�����E�����Ƃ����ŗL���Ƃ��Ẳ��x���z�ƌŗL���Ƃ��Ă̔R�đ��xSu��������D
�����Ŕ������x�萔k(T)�Ƃ��āC�ǂ��p�������i�A���j�E�X�����C�����āC700-900 K�Œቷ�قǑ��x�����������x�����������������f�������̗p�����D���̌��ʓ������x��I�ׂ�Fig. 4�Ɏ����悤�ɓ�i���x�㏸���Č����邱�Ƃ��ł����D
�����x��������߂�ƁC��i�\�����ア�������̂��̂ƂȂ����D��i�K�Ή��`�����m�F����Ă���m���}���w�v�^���ł͒��Βx�ꎞ�Ԃʼn��x�ɑ������ȕ����x���������̂ɑ��CDME�ł͎ア�����x�����������Ƃ��m���Ă���D���̂��ƂƏ�L�v�Z���ʂƂ͌X������v���Ă���D
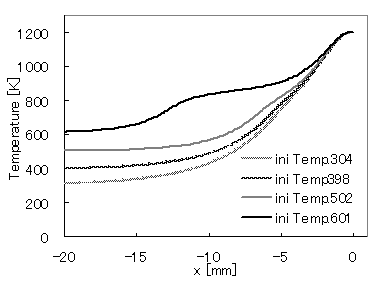
Fig. 4 Temperature profiles of 1-D premix flame
numerical integration at various initial temperatures
5.
�܂Ƃ�
DME��R���Ƃ��ĉߔZ�\�����̕��ʉΉ��`���̎������s���C�R�đ��x�ƉΉ����C�����̓��ʔ�ˑ��Ɋւ��āC�ڍה����@�\��A�������ꎟ���Ή��\���v�Z�őΉ����錋�ʂ�ꂽ�D�������ʔ�قǒቷ�R�ċ@�\�Ɋ܂܂��f�����̏d�v���������Ȃ邱�Ƃ��m�F�ł����D��i�Ή��\���̑��݂��������ꂽ���̂́C��荂���x�̉��x���z����≻�w�퐬�����͂��s�����Ƃł��ׂ������ׂĂ����K�v������D
�Q�l����
[1]J.Powling, Fuel, 28(1949)25-28.
[2]�쐨��, �@�_(�a��)�C64��627��(1998)341-347.
[3]H.J. Curran et al., Int. J. Chem. Kinet. 32(2000), 741-759.