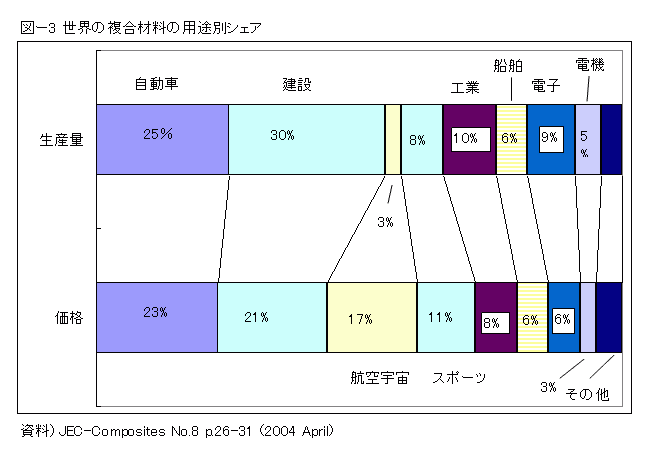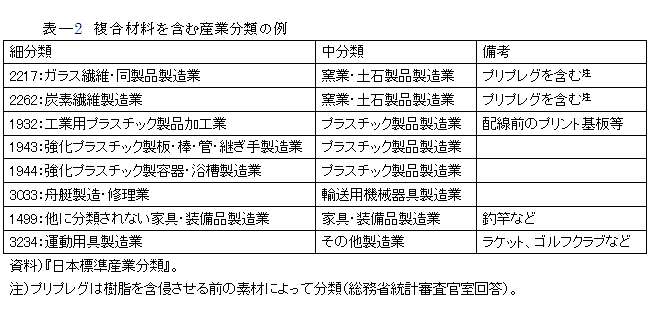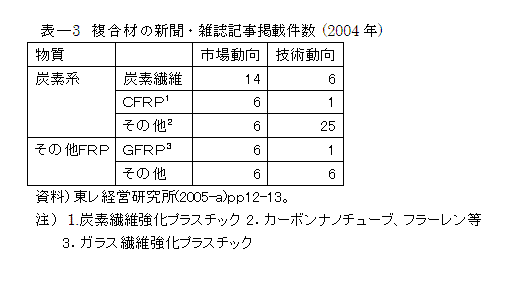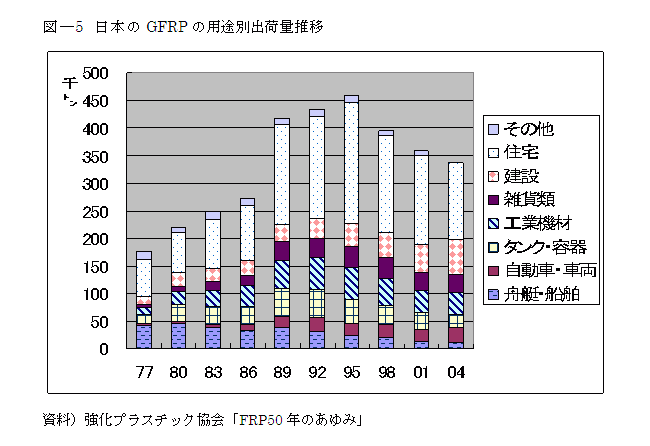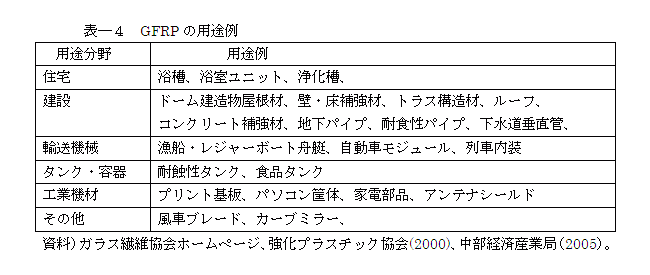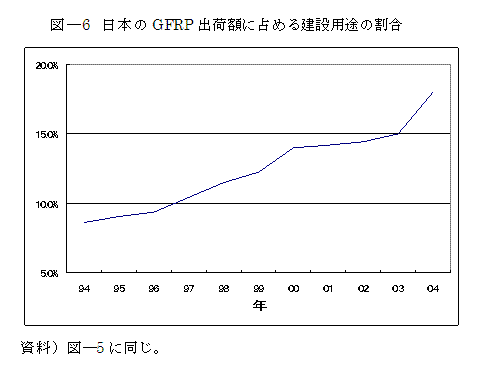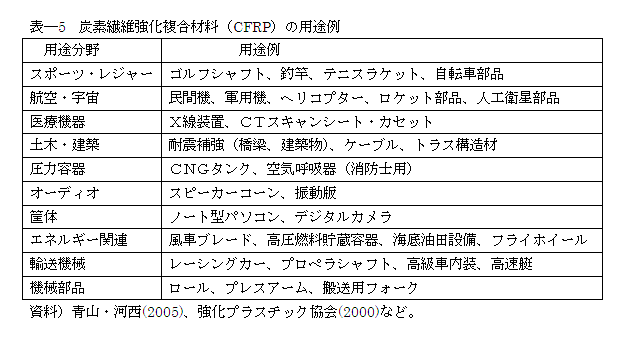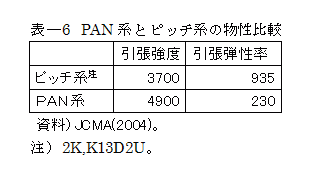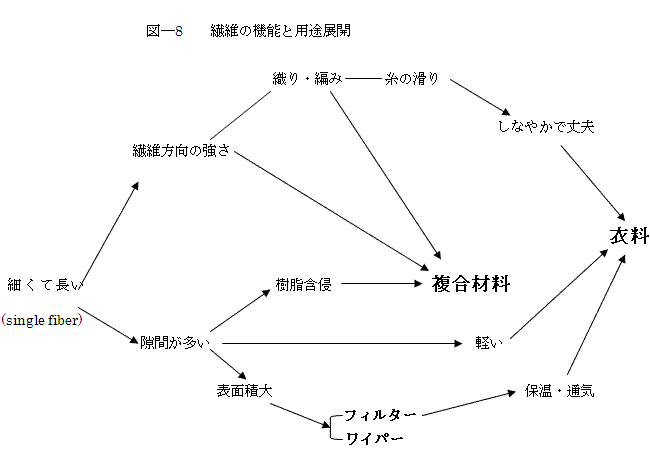| 戻る 松井隆幸 I.はじめに 本稿は、ガラス繊維、炭素繊維、複合材料を産業論の視点で分析する枠組みを提供し、これらの産業の位置づけを明らかにしようとするものである。 ここで「複合材料」とは、繊維によって強化された繊維強化複合材料、中でも樹脂を母材とする繊維強化プラスチックを指すものとする1。またここで「産業論の視点」とは、「産業単位で観察される技術、製品の物理的・化学的性質、具体的な生産活動に焦点を当て、それらと企業組織・事業展開・立地・国際競争力など社会科学的諸側面との関連を分析する視点」2としたい。 本稿では無機繊維であるガラス繊維や炭素繊維と区別して3、天然繊維・合成繊維など通常「繊維」と呼ばれるものを「有機繊維」と呼ぶことにする。ガラス繊維や炭素繊維はほぼ全量が衣料用ではなく産業用途だが、拙稿(2004)で指摘したとおり、社会科学の分野の繊維分析は衣料用繊維に集中しており、産業用繊維が取り上げられることはほとんどなかった。 無機繊維には他に金属繊維やセラミック繊維などがあり、本稿では取り上げないが、いずれ分析の対象にしたい。また、複合材料に加工される繊維として、有機繊維であるアラミド繊維がある。これは本稿でも必要に応じてとりあげたい。 ガラス繊維や炭素繊維は「窯業・土石」産業に分類されるが、「繊維」の名がつくのみで、有機繊維とは無縁の存在なのだろうか。それとも何らかの関連を持つのだろうか。ここでは、ガラス繊維・炭素繊維・複合材料を、以下のような問題意識で分析したい。
II.複合材料産業の構造 ガラス繊維や炭素繊維は、そのままの形で製品となることはほとんどない。強化繊維として樹脂と組み合されて、複合材料に加工される。繊維と組み合わせて成形することによって、樹脂に強度と剛性(変形しにくさ)が加わる訳である。その際、強化繊維はプリフォーム4やプリプレグ5といった中間加工品の形態をとることがある(図―1)。
ガラス繊維には断熱材や吸音材に使用される短繊維もあるが、本稿では複合材料に加工される長繊維を対象にする。ちなみに2003年の我が国のガラス繊維生産は、短繊維21.1万トン、長繊維48.1万トンである(『繊維ハンドブック』)。 図―2~4は、世界における複合材料料産業の概要を示したものである。図―2は使用される強化繊維の種類であるが、量・価格ともにガラス繊維が圧倒的なシェアを占めている。炭素繊維・アラミド繊維といった、いわゆる先端複合材料は生産量では合わせて1%を占めるに過ぎないが、高価であるため、価格ベースでは10%台になる。綿や紙といった天然素材を使うものもあり、家電製品のプリント配線板に用いられる紙・フェノール積層板などがここに含まれる。
表―1は、アラミド繊維を加えた強化繊維と、競合する金属との物性を比較したものである。強度とは「壊れ難さ」であり、弾性率とは「変形し難さ」である。強化繊維はいずれも引張強度、すなわち繊維方向の強さに優れることがわかる。炭素繊維は弾性率もきわめて高い。また、密度が示す通り、繊維はいずれも金属に比べて軽いため、比強度や比弾性率(軽くて強い・変形し難い)での優位が目立つ。
一方で複合材料はリサイクルの難しさ、成形後の加工の難しさ、樹脂部分の耐熱性の低さ、特性のばらつきによる信頼性の低さ6、(成形方法によって異なるが)生産性の低さ、などの難点を持つ。 炭素繊維・アラミド繊維はきわめて高価であり、ガラス繊維と比較して素材で十数倍、成形品でも数倍の価格差がある。そのため、高い水準で軽さと強さが求められる分野に用途が限られている。アラミド繊維は比較的変形しやすいので、防護服など、それをいかした分野に用いられる傾向がある。 図―3は複合材料の用途別シェアである。航空・宇宙用途において生産量ベースと価格ベースのギャップが著しいのは、ガラス繊維と比較して軽量・高価な炭素繊維の使用が多いこと、その中でも高価なものが使われるためだと考えられる。スポーツ用途には様々な価格帯のものが混在しているが、テニスラケットやゴルフクラブなどで炭素繊維が使用されるため、若干価格ベースが上回っているのであろう。
図―4は、付加価値ベースで見た世界の複合材料産業の鳥瞰界図である。強化繊維メーカー、樹脂メーカー、成型加工メーカーが主要なプレイヤーといえよう。一般的に強化繊維メーカーは寡占的であり7、逆に成型加工メーカーは多数の中小企業からなる傾向が強い8。熱硬化性樹脂を用いる複合材料はFRP、熱可塑性樹脂を用いるものはFRTPと呼ばれる。後者は複合材料の弱点であるリサイクルに対応しやすい長所を持つが、高温高圧設備が必要であり、大型製品の成型が困難なことなどから、図の通り複合材料の主力にはなっていない。
ガラス繊維や炭素繊維が統計上「繊維」に分類されないことは前述したが、表―2のように複合材料「業界」は様々な産業分類にまたがっており、特定の産業分類を対象に分析できないことは注意を要する。
III.ガラス繊維分析の意義 ガラス繊維は研究者の盲点に入ってきた産業である。拙稿(2002)で指摘したとおり、社会科学による繊維分析は衣料用繊維に集中しており、ほぼすべてが非衣料用であるガラス繊維は分析されてこなかった。一方自然科学の分野でも、科学として成熟しているガラス繊維よりも新規性のある炭素繊維が注目されがちである。結果として、メディアでの注目も低い (表-3)。また近年日本のGFRP(ガラス繊維強化プラスチック)需要は伸び悩んでおり、途上国への生産移転も進行している。
しかしながら、筆者は以下の理由でガラス繊維の分析も重要であると考える。第1に、科学としての注目度と事業とは別であり、ガラス繊維は今なお図―2のように複合材料の分野で圧倒的なシェアを占めている。第2に、GFRPの使用分野はきわめて広範であり、日本など先進国が優位を持ちうる分野もある。第3に、V・VIでみるように繊維加工や成形の分野において、技術や事業で炭素繊維とつながりを持つ。 日本のGFRP(ガラス繊維強化プラスチック)需要は近年縮小しているが、それは最大用途である住宅向け需要(浴槽、浴室ユニット、浄化槽)が、住宅着工件数の低迷に伴って減少しているためである(図―5)。これは景気の影響が大きいが、人口減少社会を迎える中、大きな回復は期待できない。
とはいえ、表―4のようにGFRPの用途は多様であり、マクロの動きのみで論じるのは適切ではない。例えば土木・建築向けは、我が国でのGFRP用途比を10年間でほぼ倍増させている(図―6)9。欧州でガラス繊維による下水道の補修が大きな需要を生みつつある10ように、比較的可能性の高い分野だと考えられる。
また、ガラス繊維の重要な物性として電気絶縁性の高さがあり、それをいかした用途にプリント配線板用のガラスクロス(織物)がある11。東アジアとの国際競争も激しいが、サーバー向けや自動車向けのような高い信頼性が必要なもの、そしてその時々で相対的に細い糸を用いるものでは日本製品が競争力を持っている12。「細い」糸が求められるのは、電子機器の軽量化と高機能化(多数の配線板を用いる)のため、「薄い」配線板が必要とされるためである。薄さに加えて寸法安定性・表面平滑性が求められる上、僅かな毛羽でも銅箔を傷つけてしまうところが技術的に難しい13。 ガラス繊維の中でも有機繊維との技術連関が強いのは、ガラス繊維メーカーと織機メーカーとで開発する、ガラスクロスの織機である。エアジェットルームによる高速織りが一般的であるが、有機繊維向けの織機をそのまま用いることはできない。有機繊維が「引っ張りながら加工する」ことができるのに対し、ガラス繊維は張力による不具合が生じやすいからである14。 欧米に比べて日本での使用量が少ないのが自動車向けである。2001年の日本のFRPのうち輸送機器向けが6.2%であるのに対し、アメリカでは31%にのぼり、GFRPが自動車外装、フード下回り、装飾部品、トレーラーやバスの部品等に使用されている15。欧州でも同様の傾向があり、とくに生産量の少ない車種では、鋼板のプレス加工設備の投資回収が難しいことなどから、GFRPが用いられることがある16。我が国でも、近年少量生産で自動車業界に参入した富山県の企業は、車体をFRP(GFRPが主、一部CFRP ) で製造している17。 日本でも近年、軽量化とモジュール化による一体成形の要請の中、フロントエンドモジュールやドアモジュールに軽量樹脂のポリプロピレンを採用したGFRPの使用が増えている18。後藤(2003)には、GFRPによるモジュール製造に伴う自動車メーカーの試行錯誤が描かれている。強度を増すため樹脂の粘度を上げるとガラス繊維が切れてしまうジレンマに直面していたのだが、「味噌にそうめんを入れてかき混ぜると切れてしまうが、味噌汁なら切れない」という技術者の指摘をヒントに、粘度を下げることで成形に成功したという19。 IV.炭素繊維の動向 社会科学の分野で産業用繊維の分析が少ないことは再三指摘したが、例外は経営学の分野における合繊メーカーの新事業進出の分析であり、その多くが炭素繊維に関わっている。社会科学の既存研究で活用できるのは、この分野である。 炭素繊維が注目される理由は、第1に需要が拡大しており、将来的にも拡大が予想される素材であること、第2に日本企業が圧倒的な世界シェアを持っていること、第3に世界の多くの企業が参入しながら撤退を余儀なくされており、残る企業の「勝因」が経営学の関心を引くことなどであろう。 炭素繊維の素材としての特徴は、表―1の示す通り圧倒的な比強度と比弾性率、即ち軽さと強度・変形し難さの両立である。加えて熱膨張係数の低さ(航空宇宙などで重要)やX線透過性の高さ(医療機器)、織り目の美しさによる意匠性(自動車装飾部品など)が意味を持つこともある。かつては航空用途とスポーツ用途が大半を占めていたが、現在では表―5のように多様な分野で使用されている。
現在生産されている炭素繊維にはPAN系20とピッチ系21がある。強度に勝るPAN系が量的に大きく、以下もPAN系を中心にみていくが、ここでピッチ系炭素繊維についても触れておく。ピッチ系は弾性率の高さ、すなわち変形しにくさが特徴である(表―6)。「軽くてたわまない」点をいかして、工業用のロール(フィルム製造用など)が大型になる場合に使用されている。また、他の素材に比べて振動の収まるのが早いため、液晶用の大型ガラス基板を搬送するアームや、自動車のボディプレス用のアームなど、重量物を扱うため振動の収束が生産性に影響を与える分野にも用いられる22。
PAN系・ピッチ系ともに研究室レベルでは日本で生まれ、その後欧米(とくに米国)企業によって開発が進められ、現在では日本企業が生産の主力になった(表―7)という歴史を持っている23。初期の開発が米国中心だったのは、きわめて高価であったゆえに、用途が冷戦を背景とした宇宙・軍事部門に偏っていたためであろう。
1970年代以降、PAN系炭素繊維の開発で先行してきたのは、日本の東レである。その経緯や背景については、経営学の分野の當間(1996)、高松(2002)、青島・河西(2005)や、実体験にもとづく松井醇一(1998-a)など多くの分析がなされてきた。東レが競争優位を築いた要因としては、(1)別の目的で開発した化合物が、炭素繊維の生産性や性能向上に貢献した、(2)アクリル繊維製造技術に優れ、原料となるアクリル繊維の開発で優位に立った、(3)長繊維製造技術に優れていた24、(4)繊維加工技術に優れ、いち早く織物の製造に成功した25、(5)樹脂技術にも優れ、航空機向けプリプレグを開発できた、等の理由があげられている。 このうち(2)(3)(4)はまさに繊維の技術であり、有機繊維と炭素繊維の技術連関を示している。繊維部門からの撤退・後退の歴史をたどってきた欧米のケミカルジャイアント(合繊をルーツとする巨大化学企業)と異なり、途上国の追い上げで衣料用繊維の縮小を余儀なくされつつも、繊維に軸足を残してきたことの、一つの結果であろう。 PAN系炭素繊維の需要を牽引したのは、70年代は釣竿やゴルフシャフト、80年代は航空機向けとテニスラケット向けであり、90年代初めまでは趣味性の強いスポーツ向けと、比強度・比弾性率の優位が大きい航空機向けが2大用途であった。その他の産業向け(業界の統計的慣習で「産業用」と呼ばれる)が急増するのは90年代半ば以降である26。その背景にあるのが2度の供給過剰による価格低下である。 1度目は90年代初めのものである。80年代後半に、軍事部門の国内調達政策に押された米国企業の能力増強と、欧州やアジアでの新規参入によって世界的な生産能力の増加が起こっていたのだが、冷戦構造崩壊と湾岸戦争後の航空機不況によって価格が急落し、多くの企業が撤退に追い込まれた。2度目は2000年前後のものであり、日本企業の能力増強に、欧米のラージトゥ・メーカーや台湾プラスチックの増設が加わったものである27。 図―7に国内を対象としたデータを示すが、2度の価格低下は明らかに国際市況の影響を受けている。そして「産業用」用途の開拓と日本勢のシェア上昇は、むしろこれを契機としている。例えば高松は、「日本では、もともと航空宇宙分野への依存が欧米に比べて少なかった上に、圧力容器や建造物の補強材などの産業用途を開拓することにより、航空宇宙分野での低迷とスポーツ分野の成熟化に対処し、むしろ増設が行われた。」28と述べている。ちなみに2004年以降は再び需給が逼迫して価格が上昇しており、これが産業用途にどのような影響を与えるのか予断を許さない。
航空用途はボーイング社のB787やエアバス社のB380といった、炭素繊維使用比率の高い大型機の開発によって着実に需要が増加している。「産業用」のこれを上回る増加によって相対的な割合こそ低下しているが、炭素繊維市場の需給を左右する最大用途であることは間違いない。 「産業用」の内訳を示すデータがないので推測するよりないが、土木・建築は炭素繊維でも有力な市場であろう。拡大が予想されるのが高速道路の橋脚等、建造物の耐震補強である。通常は鉄板による補強だが、大型の重機が入れない地理的条件の場合は炭素繊維が用いられる。 圧力燃料容器や海底油田のケーブルなどエネルギー関連も可能性が大きいといわれるが、エネルギー政策、石油価格、そしてエコ・カーの技術開発の方向などに左右されるであろう。自動車用途が開ければ大きいが、コスト要求がきわめて厳しいため、現状ではプロペラシャフトなど一部の部品や高級車の装飾部品等に限られている。軽量化による燃費効率改善の要求がさらに強くなれば、使用が拡大する可能性はある。 V.ヒアリング調査―北陸企業の対応― 北陸地域は、繊維産業のうち織布・染色加工など川中部門を担ってきた産地である。扱ってきたのは、かつての天然繊維やレーヨンにしろ、戦後主力となった合成繊維にしろ、いずれも有機繊維である。その技術や経験は、同じく繊維を扱う複合材料と、どのように関連するのだろうか。以下は筆者が近年、北陸地域で複合材の生産・開発に取り組む企業からヒアリングした内容である。 〔A社〕29 A社は福井県の大手染色加工企業であり、水産資材など産業用繊維への展開にも取り組んできた。近年、炭素繊維をテープ状に加工する開繊加工、開繊したものを織物にする開繊織機、開繊糸の織物やシートを加工したプリプレグなどを開発している。 炭素繊維加工でのA社の優位(コアコンピタンス)は、マルチフィラメント技術、すなわち繊維の束を扱う技術である。これは同社が昔から培ってきた技術・ノウハウである。開繊加工する際もそうだが、炭素繊維の束を扱う時には、テンションをそろえるのが難しい。これにばらつきがあると、半分の仕事しかできなかったりする。 開繊することによって、同じ太さの糸から、より薄く、軽い製品ができる。また樹脂を含侵させやすく、樹脂内のボイド(空隙)による不具合が生じにくい。薄いプリプレグを積層加工すれば、均質性が高く剥離しにくい成形品ができる。 樹脂によるコーティングにも、A社の磨いてきた染色加工のノウハウが使える。関連会社でやっている製造装置の開発や、それを使うノウハウも同様である。織りも、縦糸に横糸入れるのは有機繊維と同じである。大きな違いは、伸び縮みしない(弾性率が高い)ことである。 炭素繊維は、ガラス繊維と競合しているという感じはあまりしない。価格帯が大きく違うこともあるが、導電性など物性が異なるからである。 〔B社〕30 B社は富山県に本拠を置く、10社からなる協同組合である。主力の下着製品製造の中国進出に伴い、国内では高付加価値品の開発に取り組んできた。その一環として複合材料がある。基盤となっているのは、長年培ってきた編みの技術である。 長い時間をかけて、エスカレーターステップ用のガラス繊維製プリフォームの開発に取り組んできた。FRPでステップをつくるには、ガラス繊維を立体的に溝の形に編む必要があり31、これが他社にはまねできない。アルミと違って彩色できる点に注目したが、開発中にアルミの方も彩色技術が進歩し、それだけでは対抗できなくなった。その後苦心して透明感のある素材を開発した。色鮮やかな広告用として期待している。樹脂はビニルエステルを用いている。 さらに、航空機向け洗面台製造で実績のある石川県の企業と共同で航空機の内装材向けに、ガラス繊維をハニカム構造で編み込んだ素材を開発した。ハニカム構造のまま立体的に成形できるのが他社にない特徴である。立体編みは腑型力が高く、金型での成形が容易である。織物だとシワになりやすい。 将来的には炭素繊維も使いたい。また、T型やH型の加工にも取り組みたい。現在では樹脂の技術者も加えてスタッフを強化している。複合材料は原糸メーカーの技術力が強く、開発でも主導権を持ちやすい。中間加工の業者は、何か強みがないと淘汰される可能性がある。 〔C社〕32 C社はユニフォーム向け織物などを主力とする石川県企業であるが、現在炭素繊維やアラミド繊維を用いた製品開発に取り組んでいる。 開発しているのは、炭素繊維の扁平糸織物である。完全に薄くする前に織り、後加工で隙間を小さくする。隙間を小さくする、撚りをかけない、幅のばらつきを小さくする、などの繊維の要素技術の集積である。 炭素繊維は低速でないと織ることができない。従って、エアジェットルームなどの高速織機は使えない。レピアなどの低速機をベースに、精密さを付加した織機を開発してきた。付加価値が高ければ、低速でも生産性が低いとはいえない。炭素繊維が高価格なのは糸が高いからであり、織りを高速化してもコストの削減は知れている。 アラミド繊維も手がけており、炭素繊維とのミックスもやっている。炭素繊維は高機能だけではなく、高級感のあるデザイン性が長所になることもある。 〔D社〕33 D社は新潟県上越地域の企業であり、20世紀初頭のレース織物事業をルーツとしている。戦後の早い時期からガラス繊維織物の製造を始め、現在ではガラス繊維・炭素繊維・アラミド繊維を用いた織物・テープなど複合材料向け繊維加工品、プリント配線板材料、FRP成形品などを製造している。 ガラス繊維・炭素繊維・アラミド繊維は、織りなどの加工の他、樹脂含侵などでも相互に応用のきく部分が多い。汎用品のガラスクロスは台湾など海外へ出て行く傾向が強い。日本に残るのは、薄物などその時々の先端製品である。薄くて毛羽を出さないなど品質面で差別化しないとだめである。ガラス繊維技術は相対的に標準化されてきているが、炭素繊維は新しい用途が出てくる分、職人技の余地がある。 D社は繊維加工、樹脂コーティング、成形の3つの技術を持っているのが強みである。繊維加工だけでの差別化は苦しい。コーティングを加えると、例えば樹脂の組み合わせなどで差別化の余地が広がる。同社は各種技術の組み合わせで、変化の激しい顧客ニーズにこたえてきた。製品のロットが大きくなると、大手や韓国企業が出てくるので、次のニーズを開拓していく。 現在伸びているのが、携帯電話やノートパソコンなど電子機器の曲がる部分の配線に用いるフレクシブル配線板である。銅箔をポリイミドフィルムではさみ、エポキシ樹脂で接着しており、同社のコーティング技術がいかされている。 〔E社〕34 石川県のE社はスカート裏地などの衣料用繊維製品の製造を行っていたが、現在では様々な炭素繊維製品の開発・製造に取り組んでいる。 炭素繊維は要求される機能が千差万別であり、しかも金属と違って評価基準が確立されていないところが難しい。そのため試験に長い時間がかかる。同社が開発に取り組んできたフライホイール(電気エネルギーを回転エネルギーとして保存する円盤)も、10年以上も試験を繰り返さねばならなかった。他では音響機器や建物の補強材などが有望だと考えている。 繊維加工だけでは競争力を持てない。樹脂のわかる者が必要であり、信頼できるパートナーを見つけることが重要である。また、技術や素材だけを売り込んでもだめであり、肝心なのは用途である。たとえば機械に組み込むのなら、組み込んだものを見せないと顧客は振り向かない。「繊維」や「織物」の技術をアピールしても、顧客はピンとこないのではないか。 よく話題にされるスポーツ用品は、もはや技術的に成熟していて、製造はほとんどアジアで行われている。かつて成功したゴルフシャフト・釣竿・テニスラケットに加え、スノーボードやバットなど多くの製品が登場しているが、どこまで炭素繊維ならではの機能をいかしているかは疑問である。 〔F社〕35 福井県のF社は衣料用繊維製品を主力としてきたが、現在産業用へのシフトを進めている。一つの工場では、ポリエステル中心だが、ファッションの割合を減らし、カーシートやハップ剤基布へシフトしている。もう一つの工場で炭素繊維製品の開発を行っている。ガラスやアラミドも手がけている。ファッション用途と産業用途の違いを一言で言うと、重要なのが前者は感性、後者は数値(スペック)である。 現在進めているのが、燃料用の高圧タンクである。かつて原子力研究開発機構と原発火災用消火器を開発し、その後通常の消火器に応用しようとしたが、価格が安く成立しなかったので、燃料用に切り替えた。 タンクに繊維をまきつけて成形するフィラメント・ワインディング(FW)製法の設備を開発した。同社がやってきた織りや編みとは異なるが、糸を巻いたり引きそろえたりする技術では共通している部分がある。 現在、炭素繊維の需給は逼迫しており、使用する企業は糸の確保に悩んでいる。アラミドやSガラスまで不足してきた。 VI.技術・事業の相互連関 それでは、ガラス繊維、炭素繊維、複合材料の産業としての位置づけを、相互の関連や有機繊維との技術連関に着目し、図―1の工程に沿って整理してみよう。 糸を製造するメーカーは、ガラス繊維と炭素繊維では異なっている。糸の段階でとくに有機繊維との技術的関連が強いのがPAN系炭素繊維である。PAN系炭素繊維において原料となるアクリル繊維の組成や紡糸の技術が競争力を左右してきたことは、多くの既存研究が指摘している。ただし異業種の技術である高温焼成技術と組み合わせる必要があった36。 ガラス繊維の紡糸も有機繊維の溶融紡糸と共通性がある。が、ガラス繊維の競争力を左右するのは、紡糸よりもカップリング剤やガラス組成などであり、世界的にも繊維よりもガラスをルーツとする企業の方が多い37。 繊維加工の分野でも、ガラス繊維・炭素繊維とも有機繊維技術と様々な連関があり、織り、編み、準備工程などの応用が見られる。なかでもガラスクロスの織機は、技術的に有機繊維のエアジェットルームに近い。炭素繊維は弾性率が高いため高速加工に向かず、各社が独自の加工を工夫しているが、有機繊維の技術が基盤になることは間違いない。ちなみに、糸メーカーが繊維加工も行うことも多い。 Vでみたように、川中の繊維企業がその技術やノウハウをいかせるのは、主にこの繊維加工の部分である。ただし繊維の技術がそのまま複合材料に結びつくわけではなく、製品開発に成功しているのは一部の企業である。多くの企業が指摘するように、樹脂のわかるパートナー(企業、研究機関など)が必要である上、最終製品の用途についての情報把握が簡単ではない38。 プリプレグを含めた繊維加工、そして成形では、ガラス繊維と炭素繊維(あるいはアラミド繊維)の両者を使用している企業や、「今はガラスだけだが将来は炭素もやりたい」という企業が多くみられる。加工や樹脂含侵などで応用可能な部分があるためであろう。それぞれの国や地域のガラス繊維加工技術の裾野の広さは、長い目でみて炭素繊維関連産業の集積に影響を与えるのではないだろうか。 ガラス繊維も炭素繊維も、そのままで製品になることはなく、樹脂と組み合わされて複合材料に加工される。したがって樹脂を供給するメーカーや、繊維と樹脂の接点に位置する成形加工メーカーは、複合材産業の重要なプレイヤーである。また繊維・樹脂・中間加工・成形そして最終用途をトータルでとらえた製品の開発・設計が必要であり39、情報の把握や共同開発のための企業間連携が不可欠である40。 VII.「繊維」の概念と用途展開 社会科学では「繊維」の定義が議論されることはまれであり、漠然と「衣料になるもの」として意識されてきた。しかし衣料にならないガラス繊維や炭素繊維を含めてとらえるには、繊維の原点に帰った定義が必要である。 産業論では製品の物理的・化学的性質に注目するが、「繊維」とはまさに物理的形状である。ここでは「繊維」を、「細くて長いsingle fiber41を構成要素とするもの」と定義したい。ここから出発して、繊維製品は様々な機能を持ち、様々な用途に結びつく。図―8は衣料と複合材料に重点を置いて、それを示したものである。
繊維状のものは、繊維方向(軸方向)に引っ張った時に強い。それを骨組みとして入れて強度を増した樹脂が、複合材料である。また織りや編みの加工をほどこすことにより、寸法安定性や意図した形状を持たせることもある。衣料用繊維の場合は、織物や編物の糸の滑りによってしなやかさが生まれる。逆に複合材料では、樹脂によって滑りを止めることで形状を安定させる。 細長いものを集積させた素材は隙間がたくさんできる。すると表面積も大きくなり、ろ過を目的とするフィルターやふき取りを目的とするワイパーに適した性質を持つ。フィルターやワイパーは、有機繊維による非衣料用製品の重要な分野である42。 また、フィルターとは何かを通して何かを通さないことであるから、保温・通気などの機能をもたせることができる。しなやかで丈夫なこと、保温通気性、そして隙間が多いことによる軽さが、衣料に繊維が用いられる理由であろう。 隙間が多いことは、複合材料の場合は樹脂を含侵させることに役立つ。複合材料も軽さに特徴があるが、これは隙間によるのではなく、素材であるガラス繊維・炭素繊維・樹脂が、競合材料である金属等と比べて軽いことによる。 このようにガラス繊維や炭素繊維は、たんに「繊維」の名称を持つのみではなく、その物理的形状が、通常「繊維」として意識される衣料用の有機繊維と、技術や事業で関連を持つ背景にあるのである。
参考文献
|