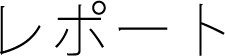
取材日6月25日
地域志向科目「富山のものづくり概論」は、富山県の重要な産業の一つである材料開発・製造を題材とし、歴史や現状を工学的な視点で理解することが目的。学生同士のディスカッションやアクティブラーニングを取り入れ、ものづくりの魅力を学んでいる。
6月25日に行われた授業は、「あなたはだあれ?」というユニークなテーマを設定。材料の特性や診断方法を学んだ。
担当の柴柳敏哉教授は、ニッケルアルミ合金製のジェットエンジンのタービン翼(実物)を見せ、工業製品素材の破損は、それが航空機や自動車の部品であれば、大きな事故につながると解説。そこで、「強い材料ってなんだろう?」というトピックスを立てて考察した。例えば、「硬さ」を評価項目にした場合、セラミックスは金属に勝るが、「落としても割れない」強さを指標にすると金属に軍配が上がる。「この考察を基に、『強さ』の定義にはいろいろあることに気づいてほしい」と述べ、「要求される性能が発揮できるよう材料の内部状態を最適化するのが材料工学者の仕事であると述べた。
さらに見た目の損傷や摩耗だけでなく、組織の変化を見る方法も紹介。分析技術を駆使して、材料の内部状態とそれが支配する材料特性を調べることは、「もの言わぬ材料との対話」であると解説し、透過電子顕微鏡による金属の結晶の画像を示しながら、正しい質問と適切な問いかけ方をしないと材料は黙して何も教えてくれず、時には嘘の情報を返してくることもあると話した。
また、この授業では、富山や出身地域の未来を切り拓くものづくりについて、学生同士が「あったらいいなあ、こんなの作ってみたいよね」という話題で語り合い、富山を宣伝するポスターを制作するワークも実施している。授業は今回で9回目となるが、柴柳教授は6年前の着任以来、富山の観光地やグルメ、産業、歴史など、自身が興味を抱いたことを毎回の授業で紹介。学生たちに富山への関心を引き出す糸口を提供してきた。コンセプトは、「外国人に富山を売り込むとしたら?」「富山の良さをひと言で売り込む」。学生たちは数人のグループに分かれ、アイディアを出し合った。
工学部のグループは、「材料」をキーワードに、伝統産業の体験観光を提案。「行ってみよう。作ってみよう」という趣旨でポスター案を検討していた。また、経済学部のグループは、富山のお土産やグルメに着目。富山ブラックラーメンや白えびせんべい、日本酒を使ったチョコレートのPRについて話し合った。芸術文化学部のグループは、藤子・F・不二雄氏が高岡出身であることから、藤子氏が育った場所を巡るツアーを発案。ドラえもんのポケットを富山県の形にするアイディアを、スケッチを描きながら検討し合っていた。
学部ごとにそれぞれ異なる着眼点で取り組むワーク。学生たちも他グループのアイディアに刺激を受けている様子が感じられた。

都市デザイン学部の柴柳教授

ポスターの内容について検討する学生

ポスターの内容について検討する学生