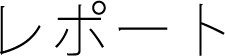
取材日7月3日
地域志向科目「富山の地域づくり」は7月3日、五福キャンパスにおいて、和歌山県田辺市たなべ営業室主任の鍋屋安則さんをゲストスピーカーに迎えて行われ、学生は地域活性化につながる事業や、それを担う人材の育成について理解を深めた。
鍋屋さんは田辺市の職員で、富山大学地域連携推進機構の金岡省吾教授に「価値創造プロジェクト検討委員会」の委員長を依頼、金岡教授から助言を受けていた。このような縁から田辺市と富山大学地域連携推進機構は2016年1月に「人材育成の連携に関する覚書」を締結、同年7月に「たなべ未来創造塾」を開設した。同塾は30代の受講者が中心で、さまざまな職種の人が集い、地域活性化につながるビジネスを立案、実行していくことを目的としている。
この日の授業では鍋屋さんがまず、公務員になったきっかけや業務内容、田辺市について紹介した。
「実家は和歌山県のウメ農家です。大学4年生になってやっと就職について考え始めました。就職浪人して公務員試験を受け、合格。公民館に勤務した後、楽しい地域づくりをしたいという思いからイベントばかり手伝うようになりました」。
続いて、「イベントを行うことで、地域活性化になるのか」と問題を提起し、和歌山県田辺市の地理的な特徴や、産業・農業などについて紹介。「どうすれば田辺市は生き残れると思うか?」と学生からの意見を求めた。田辺市上秋津地区の地域づくり団体「秋津野塾」では、1998年に地域づくりの最高栄誉である「天皇杯」を受賞している。しかし鍋屋さんは「ボランティアだけでは持続できない」と指摘し、次の段階としてどうビジネスにつなげたのかを述べた。
「まず、地域住民の出資で、直売所を立ち上げました。2003年には施設を拡大して加工場を作り、オレンジジュースを製造販売すると、これが大ヒット! 2008年には農家レストランを作り、年間2億円あまり稼げるようになって地域の雇用も生まれました」。
学生からの質問にも気さくに応じる鍋屋さん。オレンジジュースでは利益が生まれているかとの質問には、「これまで安価で売っていたジュース用の柑橘類が高い値段で売れるようになり、農家の所得が上がった」と回答した。
地域活性化については、「人を育てないとダメ」と提言し、富山大学地域連携推進機構との協定締結や、「たなべ未来創造塾」の成果などを紹介した。鳥獣被害がひどい地域で、地域の若手農家がチームを組んで、捕獲。解体処理施設や同じ塾生のシェフ、カフェバーなどと連携し、「ジビエバーガー」を開発、人気を得ていることなどが成功事例として挙げられた。
最後に、「富山でどんなグリーンツーリズムがあると、課題が解決されるのか」という課題が出された。学生は雨の季節に有効なおしゃれな傘の開発や、立山青少年自然の家を拠点とした農業体験、子どもが農業に参加する催し、売れていない魚介類を使って鍋のだしを作るなどのアイデアが出された。

コーディネーターの説明を聞く学生

ゲストスピーカー:和歌山県田辺市たなべ営業室主任 鍋屋安則氏

講義終了後、それぞれのアイデアをとりまとめる学生