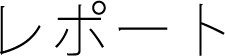
地域創生 in TOYAMA 2018
〜地域をマナブこと,地域へツナグこと〜
ALL富山COC+の取組も終盤の4年目となり,地域志向を高める教育と地域課題解決力の開発が一定の形となった本事業の活動報告とCOC+事業の終了後を見据えた自立化を探ることを目的に,第一部のシンポジウムで基調講演とCOC+の取組状況の報告がおこなわれ,第二部の分科会では「地域企業の採用力向上」「地域協働活動のあり方」「学生の課題解決型人材育成」の3テーマに分かれて活動報告やディスカッションがおこなわれた。
開会挨拶
本日は,ALL富山COC+に関わる多くの皆様にお集まりいただきありがとうございます。富山県全体の皆様からご協力いただいた本事業は今年度で4年目となり残り1年の活動となりました。皆様のご協力に深く感謝いたします。本日のシンポジウムは,地方の企業にどのように力を集約し,人を集めて発展に繋げていくかを組み立てていただきました。様々な意見,様々な形が生まれるよう期待しています。富山県の企業は素晴らしい企業が多く,産業力や企業力の高さを改めて感じています。伝統でつくりあげた企業の力を新しい形で発展させていくことを期待しています。
多くの皆様を迎えてシンポジウムが盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げると共に関係の皆様に感謝申し上げます。現在日本全体で高齢化が進行し特に地方では顕著に進んでいます。全国的に地方創生に取り組んでおり,富山県でも取り組んでいます。全国的に高等教育機関の協力を得た積極的な取組みが課題となっています。地方創生の目的は地域の活性化であり,雇用があること,産業経済が活性化していることが基本です。ALL富山COC+の取組には県としても感謝しています。このシンポジウムで出てきた課題や解決法を皆さんで共有していただき,さらに地方創生へ取り組んでもらうことを期待します。
COC+に関する大学・自治体・地域の皆様の日頃からの尽力に心から敬意を表し深く感謝申し上げます。東京一極集中の是正は国を挙げて取り組む喫緊の課題です。「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業」は,大学が地方公共団体や企業と連携して学生にとって魅力ある就職先を創出するとともにその地域が求める人材を生み出すために必要な教育カリキュラムの改革を断行する大学の取組を支援することで地方創生の中心となる人の地方への集積を目的とするものです。東京一極集中の解消を推進し,大学改革や地方大学の振興を牽引するものとして極めて重要であります。関係者の注目度も非常に高くなっており,文科省としても地方創生へ向けた各大学の取り組み支援に全力を尽くします。
このシンポジウムが関係者の皆様のご尽力により開催されましたことに心よりお喜び申し上げます。地方と東京圏の転出入均衡という目標を目指して,ライフスタイル・ライフステージに応じた地方創生の充実強化を図っていく必要があります。富山県においては,企業や自治体等と協力して地元就職率の向上を目指し,地方創生に結びつく「地域課題型人材育成プログラム」を通して地(知)の拠点として地域に貢献するという取組がおこなわれ,数多くの学生を「未来の地域リーダー」として育成し成果を上げています。富山大学では各地域でCSVを目指した人材育成に取り組み,地域活性化に成果をだしており,県内外で高い評価をもらっています。北陸財務局でも地域の課題やニーズの把握に努め,地域の課題解決に向けた取組を積極的に進めています。財務局のネットワークを活用し,自治体・地域住民・事業者等と直接向き合い,国の機関と横の連携を一層図りながら,各地域の主体との繋がりを果たすことで,地域の課題解決を後押しして地域・日本経済の活性化に貢献することを目指しています。地域の課題を解決し,地方創生を図るには,地域の皆様をはじめ産官学金関係の皆さんが地域共通の課題を認識・共有し,密接な信頼関係を構築しながら協働して取り組んでいくことが必要です。連携を深め,地域との信頼の循環を更に進め,点から線・面へ拡げることが重要です。

1,基調講演
世界的な大企業でも人材の獲得に危機感を持っています。何年かに1回は今から10年以内の最悪のシナリオを考える仮想ミーティングをして常に問題意識・危機感を意図的に高めています。人材定着のキーコンセプトについて,新入社員の入社当初は,現実と理想のギャップによる不安や幻滅,喪失感が強まる「リアリティショック」が,会社を「辞める」「辞めない」の重要なファクターとなっています。社会や企業が学生にリアルな姿を伝えていないことが要因です。入社前に現実の姿と会社の魅力を正しく伝え理解させることが重要です。入社7年目には,仕事への慣れや停滞感などで会社への愛着が低くなる傾向があります。対策として,会社を冷静に俯瞰して見る,会社と自分の関係を客観視する経験を与える必要があります。また,会社と社員との心理的契約のメンテナンスも必要で,個別の事情にあわせた柔軟な部分や具体的な対応コミュニケーションが必要です。人材の多様化は避けられません。多様な人材を引き止め,活躍へと繋げていくためにも働く個々人との明確な心理的契約の形成が重要となります。採用革新の考え方として,自社の採用上のポジションを分析,自社の採用リソース,求職者のジョブの理解という3つの視点から自社が採りうる採用戦略を立てることが大切で,自社なりの優秀さを自社なりの言葉で定義することが必要です。地域に人が留まるのは,そこが好き(情緒的),メリットがある(継続的),義務だから(規範的)の3つのコミットメントによります。「良い経験」の蓄積,「そこにいるメリット」と「そこを去るデメリット」の認識,「価値観」の形成が必要となり,若い世代にタイミング良くアプローチすることで地方就職に繋がっていきます。

2,COC+活動報告
平成27年のキックオフから現在までのALL富山COC+の変遷について説明。地域と連携を取り学生の意識変化に取り組み,統計分析に基づいて取組内容の拡大と充実を図り,学生の富山県内就職に対する魅力を向上させ企業に対しても採用等に係る意識の変革を働きかけるなど変化成長をしてきました。社会人教育による地域連携の学びや社会人の活躍が学生に良い影響を与えました。県内就職10%UPの目標に対しては県内出身学生の減少の中健闘しており,インターンシップ参加者数10%UPの目標に対しては順調に達成しています。未来の地域リーダー育成のCOC+関連科目の設定も進み,富山大学では65.7%の学生が履修するまで進みました。学生のヒアリングから就活における活動内容や企業選択のプロセスを分析し,企業と共有化を図っています。地方創生や地域で役に立ちたいという学生は増えてきています。地域就職については,企業と学生の考えにズレがあったり,企業の強みや商品・サービスの特徴が学生に伝わってないことなどがヒアリングを通じ見えてきました。地域ライフプランの授業についてのアンケートでは,地域を自分ごととして捉えた授業形態をとった時に地域の魅力が伝わる手応えがありました。地域と連携した大学の地域貢献プロジクトに学生が参加したり,地域再生人材育成事業での社会人修了生が授業に登壇するなどCOC+事業と連動し信頼の循環が強化されてきました。COC+事業の入口戦略としての高校生へ向けた発信,学生の地域活動を推進する未来の地域リーダー塾を開催し,出口戦略としての新たな取組「Monthly Work Cafè」「TOYAMA採用イノベーションスクール」を開催しました。COC+も残すところ1年となり,これまでの大学間の連携・企業との連携を深め,学生が地域に残り活躍できる場を実際につくっていくことが最終年度にやるべきことであります。引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

第一部閉会挨拶
東京一極集中に歯止めをかけることは実際には大変でありますが,この取組はこれからもずっと続けなければならない事業であります。地域に定着する人材をどう生み出していくか, 地域に愛着を持たせ若者を惹きつけるにはどうすればよいかが課題です。現在の採用は売り手市場で企業は採用難になっています。企業だけではなく大学の努力も必要で,企業と大学が連携して地域に若者を惹きつける力をつけることが重要です。このCOC+事業もその一環で,地域課題を解決するプラットフォームをつくることでスタートしています。この取組を発展させていく必要があると思っています。この事業は5年期限で来年度までですが,これまでやって来た事業をもっと発展させ,事業を継続していく必要があると思っております。大学コンソーシアム富山は,富山学・観光産業学・地域ライフプランの講義を来年度から引き継ぎ,今後も県内大学で続けていくことになりました。地域課題解決型の取り組みやプラットフォーム的な組織で継続させていきたいと考えています。今後更に富山に定着する人材,地域に愛着を持ち地域で働きたいと思う人材を育てることが大きな課題となります。本日参加の皆様には今後ともよろしくご協力お願いします。
