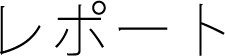
地域創生 in TOYAMA 2018
〜地域をマナブこと,地域へツナグこと〜
ALL富山COC+の取組も終盤の4年目となり,地域志向を高める教育と地域課題解決力の開発が一定の形となった本事業の活動報告とCOC+事業の終了後を見据えた自立化を探ることを目的に,第一部のシンポジウムで基調講演とCOC+の取組状況の報告がおこなわれ,第二部の分科会では「地域企業の採用力向上」「地域協働活動のあり方」「学生の課題解決型人材育成」の3テーマに分かれた活動報告やディスカッションがおこなわれた。
地域に貢献する大学としてこれまでにも社会貢献活動に取り組んできました。平成25年度に文科省COC事業に採択され地域との協働に積極的に取り組み,27年度よりにCOC+事業の参加校の一つとして県内の各高等教育機関,企業と連携を取りインターンシップやキャリア形成教育の充実に努めてきました。本分科会では富山福祉短期大学、県立大学からこれまでの地域協働活動の取組状況等についての報告とパネルディスカッションを予定しています。今後とも大学・地域・企業が協働し地域に貢献できる学生を育て,若者の地域定着に向けて努力してまいります。この分科会を契機により一層のご支援ご協力を賜りますようお願いします。
本学の地域協働活動は平成25年度に文部科学省の地(知)の拠点事業に採択されたことから始まります。工学心で地域とつながる地域協働型大学の構築を目指して,教育・研究・地域社会貢献の分野で全学的に地域課題に取り組んでいます。文科省の事業は昨年度で終了し本年度から独自に継続している状況です。本学の地域協働活動の中心は地域協働授業で,少人数ゼミで様々な地域課題に取り組み,主体性・課題解決力・コミュニケーション力を育んでいます。学生の96%が受講し,平成25年からの受講生は延べ3100名になる。授業以外にも学生が自主的に地域協働活動をおこなっています。学生自らが大学へ企画申請し大学が予算配分し年間10件程度おこなっています。学生が中心となって活動してもらおうと立ち上げた学生団体「地域協働研究会COCOS」では本学の地域協働活動のサポートや地域との自主的活動をおこなっています。地域協働活動についての学生へのアンケート結果には地域課題や解決のための知識が深まり,仲間へのコミュニケーション力や対外的なコミュニケーション力が身についたという回答が多く得られています。
課題解決型と文理融合型の2種類のインターンシップを実施しています。本学ではキャリア形成科目の単位認定でインターンシップを開講しました。院生を対象におこなった課題解決型の狙いは学生が企業の課題を見つけ,グループワーク力と共に自ら解決しようとする力を養うこと,課題解決に取り組むことで学生が達成感を感じて,最終的にその企業に愛着を持って就職につなげてもらうことです。同時におこなった文理融合型インターンシップでは,富山国際大学の学生と共同研究をすることで,互いに刺激を受けることも狙っています。インターンシップは長期間の受入を希望していましたが,10日間ほどの受入が多くなりました。過去3年間で協力企業は延べ12社(実質7社)であり,参加学生は24名うち県外学生は15名でした。過去2年の進路状況は就職者18名のうち5名の学生が受入企業での就職につながりました。。成果として,参加学生は研究への取組や自分の進路に対してより積極的になったことと,一般学生より県内就職率が高くなったことがあげられます。課題として,受入企業側から人員や時間確保が難しく現場の理解が得にくいという話が多いです。大学側では教員や学生への周知を深める必要がある他,研究活動との時間調整やインターンシップ先までの交通の確保など課題があります。また,受入企業と学生双方に合った課題を見つけることも問題となっています。
本学は「地学一体」を掲げ,地域と一体となって課題に取り組み「共創福祉センター」を立ち上げた。平成30年4月には地域課題解決拠点となる施設(USP)を建設した。地域に学ぶ,地域で学ぶということで1年必修で前期「地域つくりかえ学」で外部講師による講義,後期「富山コミュニティ論」で地域へ出て学ぶ他,年に一回はボランティア体験をして学んだことを発表する仕組みをつくっている。本学と連係をとる行政,社会福祉法人との地域連携会議を開催し,学生に取り組ませる地域課題を検討し,その課題を学内でマッチングして半年間活動し報告会をする形で地域のニーズに沿った学習をとっている。富山コミュニティ論の狙いは幅広い一般的な観点から地域課題について学ぶことで学生の学びの幅を広げている。課題としては、ゼミ単位で取り組むので教員の個々の力量にかかり担当教員の負担が大きいこと,学生と地域の人との時間・日程の調整が難しいことの2点が改善していきたいことで模索しているところである。


分科会に多くの産官学の皆さんに参加いただきありがとうございます。学生を主役とした地域協働の芽を育て地域定着へ結びつけていく仕組みができあがってきたと思っています。これまで以上に地域・企業とともに学生を育てていくことが,これまでの共同研究・協働開発より進んだ地方の産学官協働の新しい姿になると期待しています。地域に根ざす学生を育てていくために今後とも長い目でご支援をお願いします。
