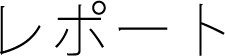
地域創生 in TOYAMA 2018
〜地域をマナブこと,地域へツナグこと〜
ALL富山COC+の取組も終盤の4年目となり,地域志向を高める教育と地域課題解決力の開発が一定の形となった本事業の活動報告とCOC+事業の終了後を見据えた自立化を探ることを目的に,第一部のシンポジウムで基調講演とCOC+の取組状況の報告がおこなわれ,第二部の分科会では「地域企業の採用力向上」「地域協働活動のあり方」「学生の課題解決型人材育成」の3テーマに分かれた活動報告やディスカッションがおこなわれた。
本学独自の地域課題探求型学習を核としたとやま地域創生人材育成プログラムを実施しています。様々な地域課題解決学習や地元学の学習を試み,地域志向科目を現代社会学部,子ども育成学部ともに約30科目設け学生に修得を呼びかけています。富山短期大学でも取り組んでいます。両学の特徴は地元就職率が圧倒的に高いことです。富山国際大学で約85%,富山短期大学で約95%が富山県内へ就職する地元密着型の大学です。地元定着性の高い学生をいかに生み出すかを大きな課題としています。地域に愛着を感じ,将来地域で活躍するリーダーをいかに育てるかに重点を置き取り組んでいます。

このプロジェクトは平成27年度からスタート。総人口の減少と人口構造の変化から地域の衰退・東京一極集中を背景に地域再生・活性化の拠点となる大学形成の取り組みとして,COC事業/COC+事業に取り組んでいます。大きな狙いは課題解決型人材育成。具体的なカリキュラムとして地域志向科目を設定,学生に地域のことを具体的に学んで理解してもらい地元に愛着を持ってもらうことを狙っています。現代社会学部で31科目,子ども育成学部で29科目の実習・講座を設定。柱となるのが「コア・カリキュラムの体系化」で学年進行・正課科目履修モデルによる課題解決型人材育成です。学年ごとの4段階を設定し最終段階で地域課題解決型テーマによる卒業研究へとカリキュラムの体系化をはかっています。学生の課題解決能力を客観的数値で測定するため能力特性評価テストを行い,操作的定義の尺度構成や項目分析で成長度の検証を行って事業の裏付けを取っています。結果,両学部とも3・4年次の課題解決能力は向上していると言えます。課題解決能力の向上に実習等の体験学習が効果を上げています。学生一人一人の体験学習への取り組み方・参加意欲度をどう高めるかが実習を行う上での課題です。IRの観点からもデータ整備をして,個人の成長度を測るためにも分析が必要であり,5年10年と続けてデータを取り続ければ役立つ資料ができると考えています。

学生と地域団体が連携した実践的な活動を2点紹介させていただきます。1つ目は滑川商工会議所青年部とのふるさと龍宮祭りの企画運営をした事例です。学生13人がイベント運営に参加。社会経験活動として祭りの協賛企業まわりや学生視点での広報活動,イベント企画に取り組みました。様々な企業を回るなかで良い社会体験もできました。広報活動としてYouTubeやInstagramを活用したPRを取り入れ,学生ならではの広報活動を行いました。2つ目は特許庁が実施する地域ブランド総選挙に魚津漁業協同組合と連携して取り組んだ事例です。魚津バイ飯のPRを学生と魚津漁協で連携して行いました。取材と販売,Instagramによる情報発信に取り組み,事業展開としてバイ飯の知名度向上に向けた学生視点での提案を発表しました。地域との連携のきっかけは外部から大学へのアプローチがあったことで,それに対して興味がある教員・学生が一緒になって実施したという経緯です。学生の視点を地域の団体にも広げることができたのは連携の成果です。学生と地域団体が活動することでマスコミに取り上げてもらうこともできました。学生にとっても地域を理解することで大きな学びがあり,社会人との交流を通じ社会体験もできました。課題は活動の評価が曖昧になりやすいと感じているところです。学生の自主的な活動に対する評価の仕組み,時間の調整や継続性も今後の課題です。
現在も継続中の取り組みである「子ども食堂」の新たなニーズに関する調査研究は,学生たちが数ある課題のなかで,子どもの貧困という問題に着目したことから始まりました。実態を把握したうえで現場へ身を投じ生の声を拾い上げ,必要なものや課題を挙げ,対応策を考えてきた実践事例です。この事例は昨年度の大学コンソーシアム富山「学生による地域フィールドワーク研究」の助成金をいただき,優秀賞を受賞しました。単年度で終わらせないで2年3年と継続していくことに意義があります。1年にわたり丁寧に調査し,支援ニーズを捉え学生なりにアクションリサーチし,そのなかでソーシャルアクションを考えてきました。調査に基づき地域密着の富山型・多機能子ども食堂の展開を提言しました。
1年目の調査では,子どもが遊べる場や学習支援,保護者の育児相談及び交流などの機能を子ども食堂に求める声がありました。私たち学生の強みを生かした子ども食堂を開くことで地域社会の求めるニーズに挑戦できるとの考えで,3年目となる来年度の本格オープンへ向けて形を模索し「私たちにできる 私たちにしかできない こども食堂」開設に向け準備しています。組織作り,学生自身の学び,行政・企業・地域との連携,開催準備の4つのプランを実施しました。定期的に学習会を開催し,県内の子ども食堂や地域ニーズの調査を行い,他の子ども食堂や地域企業との連携・協力体制を構築します。実施する食堂を地域の人々の強みを生かした,地域で持続可能なものとなるように開催へ向け具体的に準備し,年内に第1回のこども食堂をプレオープンさせます。
福祉学科は学科開設から23年,平成31年4月から「健康福祉学科」へさらに進化します。富山短大は、2007年に文科省学生支援GP「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」に採択され、『地域をキャンパスとした人間力向上の取り組み』〜学科の特性を生かした社会参加活動の開発・支援〜プログラムを展開しました。このプログラムでは、学内に「ボランティア・地域活動センター」を設置し,特色ある地域活動プログラムの開発,学生の地域活動への参加促進,「Webボランティア手帳」システムの構築,地域の諸団体との協働・ネットワークづくり等を推進し,学生の人間力向上に向けての取組みを始めました。福祉学科では,自分たちが学科での学びを生かし、考案したボランティア活動を地域の施設に出向き、一緒に取り組んでいます。具体的には,健康体操やレクリエーションゲーム,昔の遊びなどの伝承交流,化粧やハンドマッサージ,在宅介護などの活動を班毎に行ってきました。活動班は4月に2年生が1年生に紹介し、1年生は自分が参加する班を決めます。班別に活動内容を学生が決め、施設に交渉をします。活動が決まれば、Webボランティア手帳に登録,活動日の連絡や記録などをスマホ・ネット上でおこない活動内容や成果などの共有化を図っています。10年が経ち、4班編成に見直し、今後はトミタン4学科の強みを活かした連携を取っていくことが大切であると考えています。

本日は、学生の課題解決型人材育成カリキュラムの体系的展開と実践的試みについて,富山国際大学の多くの学生さんに参加いただき活発な分科会を開催することができました。これを機に、学生の課題解決能力をどう高めていくかが課題であるかと思います。それぞれのカリキュラムの更なる人的サービスを活かしながら情報発信をして、学生にとって魅力的なカリキュラムを設定することが課題であると考えられます。学生が地域に残って活躍していくためには、地域を自分のこととして捉えるアプローチがとても必要になってきます。今後ますます学生の視点・課題解決能力を大切にした地域創生が大学・短大に求められており,努力を積み重ねていかなければいけません。地域で学び,地域で成長する取組みを今後さらに増やしていきたいと思っています。
