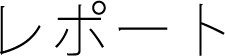第2期 TOYAMA 採用イノベーションスクール
第3回ワークショップ
講演②「ジョブ理論に基づいた採用」
開催日時:令和元年9月12日(木)10:00~
開催場所:富山県民会館 第3回ワークショップ702号室・講演②611号室
第3回目となるワークショップのテーマは「人材要件と募集手法・選考手法のブラッシュアップ」。はじめに、前回の開催(8/29)から2週間を振り返り、各参加者が仕事やプライベートなどを含た今の気持ちを話しました。
コンチネンタル(株)の中村裕太郎さんは、自社で富山県および県内企業関係者の企業視察があったことを、また、立山電化工業(株)の三浦亜希さんはインターンシップ実施中の感想を述べるなど、それぞれが過ごした2週間について報告しました。
3回目ともなると、参加者同士のコミュニケーションも深まり、予定時間をオーバーするほど和やかにトークが進みました。
続いて、北陸コンピュータ・サービス(株)コーポレート本部人事部の合田郁夫さんが自社で実施したインターンシップについて報告。①他社との差別化を図る ②業界の仕組みを知ってもらう ③将来担う役目を体感してもらうという3つのポイントを紹介しました。「グループワークでは、大学も学部もバラバラだったので、最初はお見合い状態。どう接していいかわからないと戸惑いを見せる学生も多かったが、回を重ねるごとに学生たちの表情が変わっていくのがわかった」と語り、「北陸は大学同士の交流が少ないことから、グループワークを効果的に取り入れるなどの工夫も必要」とアドバイスしました。
この後、前回のブラッシュアップとして、参加者が「人材要件」について発表。宮越工芸(株)の宮越文美代さんは「評価する人材要件」として、「①誰とでも平等にコミュニケーションでき、柔軟に物事が進められること ②職人気質で、一つのことに粘り強く真剣に取り組むことができること」を掲げ、これらの資質をもった人材を獲得する手法を「彩り採用」と名付けたと発表しました。これは、同社の特長である「色彩のプロフェッショナル」にちなんだ命名であるという解説に、会場からは「なるほど」の声と共に拍手が起こりました。
各参加者の発表、セッションを経て、今回のワークショップを振り返り、午前の部は終了。
午後からは会場を移し、神戸大学大学院経営学研究科 服部泰宏准教授が「ジョブ理論に基づいた採用」をテーマに、近年の採用事情と学生の志向などについて講演しました。
服部准教授は、近年の就職活動事情について「東京の企業はすでに、需要(求人側)と供給(求職側)のバランスが完全に崩れている。東京の企業は地方で採用活動を展開している」と述べ、学生の動きについては「各大学に就職活動サークルが出現し、企業とダイレクトにつながっているなど、多様な形が見られる」と解説しました。
このほか、選抜方法の種類と、選抜の結果から学生が入社後に達成しうる業績を予測する精度について紹介し、「仕事内容にリアルに近い試験を課し、実際にどのくらいできるかを、より現実的な方法で見極める企業が増えている」と話しました。
企業と人材の望ましいマッチングについては、「入社当初、新入社員は過剰な期待を抱きやすく、5年目前後は停滞感を覚える。7年目は会社を俯瞰することで『ここで頑張ろう』と感じられるような経験のできることが望ましい」と解説。学生が入社前に抱いた期待と入社後のギャップを解消していくことを求めました。
続いてリアリティに基づく募集広告の好事例として、100年以上前、ロンドンの新聞に掲載された広告を挙げ、5,000人を超える応募者が集まった内容を検討、「なぜ、多くの人に響いたか」を考察しました。(※広告の内容は以下の通り)。
「南極探検隊」
求む男子。
至難の旅。わずかな報酬。
極寒。暗黒の日々。絶えざる危険。
生還の保障は無い。
成功の暁には栄誉と賞賛を得る。
「チャレンジに重きを置き、楽観的な考え方の人材を募っている」と広告の方向性を解説し、メルカリが「世界にはみ出す人、求む。」というキャッチコピーの日経新聞の全面広告として掲載したこととの共通性を指摘。優秀なエンジニアが応募してきた成果があったと解説しました。
また、エントリー要件の引き上げ、多様な入り口の設定、採用のタイミングを変更、他企業と協力した採用の実施、新卒一括採用の停止、SNSの活用、スカイプでの面接など、企業の多彩な取り組みについても紹介しました。
服部准教授は、現在の求職者について「初期のキャリアにおける成長や、働きがいなどを重視しており、働き方へのこだわりがある」と分析し、「自社の採用上のポジションや、採用に使えるリソース(武器)と合わせて検討し、皆さんの企業にとっての有効な採用戦略を考えてみてほしい」と伝えました。
続いて参加者は消費者とメーカー担当者それぞれの役割を担って「どういう気分の時にチョコレートを買うか」をテーマにディスカッションを行いました。ニーズを掘り下げることで消費者の意向を理解することを考え、採用活動に生かす道筋を探りました。
司会進行の尾山真特命准教授 ディスカッション中の参加者
なお、次回のワークショップは、9月26日(木)です。その様子も順次レポートしていきます。