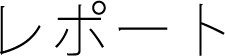とやま塾 in HIMI 2019 成果発表会
開催日時:令和元年9月20日(金) 13:00〜
開催場所:ハマナス荘(氷見市島尾1882) 会議室
~とやま塾 in HIMIとは~
県内の学生が地域課題について学び、その課題をともに考え、解決策を探求する「合宿型セミナー」。
学生たちが、①地域の人々や他の高等教育機関の学生と交流してコミュニケーションを伸ばし、②氷見市の素晴らしい自然や文化に触れることで、その良さを知り、富山への愛着を深め、③氷見市に代表される地域の課題を理解し、その解決策を協働しながら模索し、地域貢献の態度を醸成するとともに、協働力、課題解決力を高めることを目的としています。
「とやま塾 in HIMI 2019」は、9月18日〜20日の3日間にわたって開催。利賀村、朝日町と続き、3年目の今年は氷見市を舞台とし、富山大、富山県立大、富山国際大から計20名の学生が参加しました。 1日目は、ワークショップを通して氷見に関する情報を収集、2日目は6つの小グループに分かれて研修先を訪問し、見学や体験、ヒアリングを通して各課題について考えました。そして最終日の3日目は、グループで得た解決策を発表し合う、成果発表会を実施。学生の他、研修先や氷見市役所の方々も参加しました。 冒頭、富山大学地域連携推進機構地域連携戦略室COC+統括コーディネーター・尾山真特命准教授が「とやま塾」の趣旨や目的、今回の各グループの課題の説明が行われ、その後Aグループから順番に発表しました。Aグループの課題は、「次回TEDxHimiを開催するときのSpeakerを探す」こと。「TEDxHimi」は、「広める価値のあるアイデア」を世界に発信しようとするローカルコミュニティ。学生たちは、そのスピーカーとなる人物を自分たちで探す体験を通して、人選の難しさと労力を感じ取りました。
学生たちが紹介したのは、着物で世界を一周した伊藤研人氏。実際に電話で話をし、さまざまなアドバイスを受け、「人選や集客をスムーズに進めていくためには、もっと『TEDxHimi』を認知してもらうことが必要」とまとめました。
Bグループの課題は、「とやま塾終了後、大学生の皆さんが定期的に氷見市を訪れるようにする方法を考える」こと。氷見市への移住を支援するIJU応援センター「みらいエンジン」で研修した学生たちの提案の1つ目は、簡易マップだけで行う「町なか散歩」。「氷見の方は気さくな方が多いから、もっと人と話ができて関係も深まるのではないか」と述べました。2つ目は、大学生が氷見特有の職業を体験できる「氷見キッザニア」の実施。この2点から「氷見の魅力を活用して豊かな暮らしを実現することが、氷見に人が来てくれるための第一段階」と発表しました。
Cグループの課題は、「魚問屋が始めたワイナリー『SAYSFARM』の手法を活用し、日本・世界の人が氷見産品を欲しくなるようにするにはどうしたらよいか」。実習から学んだ、「自ら足を運び学んだことを地元にアレンジする」や「こだわりを貫く」といった「SAYSFARM」がもつ心構えの重要性を訴えました。
グループの学生は「何も知らないところからワイン造りを始めた行動力に感銘を受けた。『やってみよう』の精神を大切にしていきたい」と述べました。
Dグループの課題は、第三の居場所としてのさまざまな企画し運営する「ヒラク」が「『ヒラク』を活用して、子供や青少年の居場所づくりの企画・実施計画を作り、スタッフを募集する」こと。小・中・高生の利用を増やすため、子供達が興味をもつことは何であるかをキーワードで出し合い、「リアル脱出ゲーム」を実施したらどうかという提案が出されました。ゲームの具体的なストーリーまで話し合い、学生も「この先本当に実施したい」と意気込みをみせていました。
Eグループの課題は、「KOPPEを支援拠点として活用し、地域のために何ができるか考える」こと。「KOPPE」とは現在、商店街の空き店舗をリノベーションし開店準備をしているパン屋さん。リノベーションを体験した学生は、「まだ使えるものがたくさんあったので、フリーマーケットの開催を提案したい。店舗の改装資金が賄えるだけでなく、宣伝につながる」と発表しました。さらに、地域の人々の集いの場にするため、「フリーノートの設置」を提案。「ノートがあれば、情報収集や相談のきっかけになり人が集まってくれるのではないか」と提案しました。
最後のFグループの課題は、氷見の漁業の課題でもある「越中定置網を東南アジアに定着させるための説明資料を作る」こと。図を使いながら定置網の特徴やメリットを説明し、「定置網は一度設置したら固定したままであり、なかなか次の世代への継承が難しいと聞いた。まず日本で漁業と子供との関わりを増やすことが大切」と述べました。そして、「東南アジアでも定置網の良さに気づいてもらい、現地の方の信用を得ることで教育の機会を提供できるのではないか」と提案しました。
MIRAIENGINE 藤田智彦氏
全グループの発表を終えて、IJU応援センター「みらいエンジン」の藤田智彦さんは、「研修の後にまた氷見に顔を出してくれることが、氷見の方は一番嬉しいと思う。今後もどんどん氷見とかかわってほしい」とメッセージしました。
市役所の方
市役所の方は、「若いということで可能性はたくさんあるので、できることから始めてほしい。多くのことを行政にも生かしていきたい」と感想を述べました。
発表会終了後、一人ひとりに修了証を授与。最後に富山県立大の堺勇人COC+コーディネーターは、「他大学、学年も異なる学生同士で、悩んだり話したりして過ごした密度の濃い3日間だった。この体験をそれぞれの場所でいかしてもらいたい」と述べ、閉講しました。
[参加学生の感想]
「とやま塾は、富山の人とのつながりが広がる素晴らしい学びの場。これまで3年連続で参加しており、氷見のことも第2の故郷のように思うようになった」
「氷見は、海風を感じられ商店街活性化のための新たな場所があっておもしろい。違う土地から来た者だからこそ見つけられることもあるのだと感じた」
「氷見に住んでいても知らないことがたくさんあった。こんなにも地元氷見のことを考えてくれる人がいてうれしい」