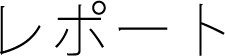まず服部准教授は、新潟市内に本社を置く米菓子メーカー「三幸製菓」の事例を紹介。
・出前全員面接会:5人仲間を集めて会場を準備してくれたらどこへでも行く(人を巻き込む力、調整能力、段取り力を見る)
・ガリ勉採用:「学生時代は勉強した」という人を採用(就活巧者ではなく、勉強に対しての継続力と集中力を評価)
・ニイガタ採用:「新潟が好き」な人を採用(地方企業であるという発想を逆転)
・おせんべい採用:おせんべいへの愛を語ってもらう(おせんべいへの愛を重視して採用)
三幸製菓は、新潟という地域性や米菓子を扱う企業であるという独自性を生かした採用活動で成果を上げています。このことから服部准教授は、「自社のポジショニングを知り、採用基準を導くという戦略を持つべき」と提言。超人気業界の人気企業と同じ発想で学歴や協調性などにこだわるのではなく、そういう視点をあえて棄てて「見ない勇気」を持ち、独自の方法で採用すべきであると伝えました。
また、採用と育成をどう関連付けて考えるかなどの方針や、米国の採用シーンで起こっていることなどを紹介。「魅力的なサイトは、魅力的でない休職者も引き付ける」「確実にSNSの活用が広がっている」などと述べました。「組織(企業)と個人の関わり合いは、それぞれに特異なものとなり、かつそれが個人と組織の双方にとって理想的な物になりつつある」と紹介し、それぞれの企業独自の採用のあり方を考える必要性を示しました。