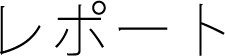
令和元年度ALL富山COC+シンポジウム
地方創生に向けた奮闘の記録と今後の展望
富山県内の地域人材の育成,地域定着を目的に県内高等教育機関と自治体・企業が蜜に連携を図り様々な活動をしてきたALL富山COC+の取組が今年度で一区切りすることから,これまでの活動を総括し,今後の在り方・継続の仕方を議論するシンポジウムが開かれ,高等教育機関関係者はじめ行政,県内企業関係者など約200名が参加した。
開会挨拶
本日はお忙しい中集まりいただきありがとうございます。ALL富山COC+は,これまで富山県内の地域人材の育成,地域定着を目的に掲げ,大学と自治体・企業と密に連携を図り様々な活動を展開してきました。5年間の事業期間が今年度で終え一区切りとなることから,これまでの活動を総括し,今後の在り方・継続の仕方を議論いただくためにこのシンポジウムを開催しました。報告やパネルディスカッションを通じ活発な議論をいただきたいと存じます。
来賓挨拶
本日の開催を心よりお祝い申し上げます。我が国において人口急減・高齢化という大きな課題に直面してることから地方の人口減少・地方経済縮小への歯止めをかけ,各地域の特性を活かした自律的で持続的な社会を創生するため,意欲と能力のある若者が地域で活躍できる魅力ある就業先や雇用の創出,地元定着が求められています。平成27年県内高等教育機関におけるCOC+事業が採択を受け県内就職率10ポイント向上を目標に県内高等教育機関と地方公共団体・企業が連携したALL富山で学生の地元定着や雇用創出による地方創生の取組が進められてきました。県においても高等教育機関における取組の支援に加え,富山未来創生産学官連携会議を設立し,本県中核産業である医薬品やアルミの分野において最先端のプロジェクトに取り組み,地域で活躍する人材の育成や大学等を核とした県内産業の活性化,若者の県内定着に向け積極的に取り組んでいます。COC+事業ではこれまで数多くの取組が実施され,全国的にも高い評価を受け地方創生の推進に尽くしていただきました。今後の事業終了後も引き続きCOC+事業で構築された連携体制を活かし地方創生の取組が一層発展するように大きな期待を寄せています。

COC/COC+活動報告
COC+取組事業について報告。人口減少高齢化社会での目指す将来像実現へ向けた求められる人材(未来の地域リーダー)育成するため,地域愛着心と地域課題解決の力を身に付けてもらう取組(教育戦略),富山県内就職10%アップへ向け地域定着への取組(出口戦略)と地元出身者維持へ向けた高校へ対する取組(入口戦略)の3つを柱に取り組んできた目標及び達成状況について報告。県内就職率に最も影響のある入口戦略としての高校と連携した取組内容等についてや,地域志向の教育プログラムとして5年間の教育戦略の概要について地域課題解決型人材プログラムについて講義内容や目標値と達成状況について紹介報告。教育プログラムの改善点やアンケート調査による効果や課題などの因子分析,学生の変化や成果について報告した。地域定着意識と県内企業就職について出口戦略として取り組んだ内容について,インターンシップやキャリア教育セミナー,採用イノベーションスクールについて説明。地域で活動した学生の地域就職意欲が高まることが実証され,学生の地域志向を受け入れるため,大人が地域の社会人としてどの様に迎え入れる準備ができているのかを具体的に示すことが必要であり,学生の地元への不信感を払拭できる。COC+で培ったメカニズムを活用して地域のために役に立つ大学になっていきたいとCOC+5年間の報告を終えた。

富山県内7校の学生取組活動について報告。各校の学生活動やCOC+プログラム等への参加体験,地域活動についての発表報告がおこなわれた。
富山大学 前田拓海「とやま塾in HIMI」
富山県立大学 中田美雨「地域協働研究会COCOSの活動」
富山国際大学 宿波美麗「できること探し〜地域創生プログラムの活動から〜」
富山短期大学 渡辺菜月「これまでの私,これからの私」
富山福祉短期大学 老田未彩「地域活動支援サークル ちょっこりNEOの活動報告」
富山高等専門学校 松坂拓郎「工学徒から見た富山県」
高岡法科大学 大谷侑莉「COC+活動報告」
パネリスト
富山市長・富山市長会長 森 雅志
富山県商工会議所連合会長 髙木繁雄
活動報告を行った学生(富山大学/前田拓海,富山県立大学/杉山悠,富山国際大学/宿波美麗,富山短期大学/渡辺菜月,富山福祉短期大学/老田未彩,富山高等専門学校/松坂拓郎,高岡法科大学/大谷侑莉)

●武山:
COCは平成25年から・地域再生・活性化の核となる大学をつくり,取組に対しての連携自治体の評価を成果目標に始まり,全国77大学,富山からは県立大と国際大がが採択され取組始めた。さらに地元定着を深く取り組むことなり平成27年よりCOC+が新しい事業として始まった。目標は若年層の東京一極集中の解消で成果目標は連携自治体・企業の評価に加え,地元就職率・雇用創出数が評価指数が評価に設定。今年度最終年度となり区切りをつけるが,予算が無くとも自走して続けなければいけない。本日は自治体の代表として森市長,経済界を代表して高木会長,報告いただいた学生と議論を交わしていきたい。
●武山:
7校の学生の報告を振り返っていきたい。富大前田さんは,氷見でのとやま塾に参加して体験と食事会で学びがあったとのことですが。
前田:
大人の人の意見が聞ける場が大学生活だけでは得られないので大変良かった。話し合える機会があれば参加していきたい。
●武山:
県立大学COCOSではMAPを富大芸文の学生と作ったそうだが,他大学の学生と協働してどうだったか。
杉山:
他大学の方とは毎年何かしら活動しているが富大芸文の学生とは初めてでデザインの勉強ができたことは良かった。
●武山:
国際大の宿南さんは子供食堂を実際やってみて,色々な多くの方との連携があったと思うが感想を聞かせて欲しい。
宿波:
学生だけの意見でなく大人の方と交流することで相互に意見を交わすことができ良い経験となった。
●武山:
富山短大の渡辺さんは保育士に憧れ目指し,実践力と子供の目線について取り上げているが子供の目線について詳しく聞かせて欲しい。
渡辺:
子供の目線というのは実際に今の学生視点で子供たちへの楽しませ方や話しかけ方を実習で子供と関わって学ぶことができた。
●武山:
福祉短大の老田さんは障害者が活動できるサークル活動についてだったが,五感を使って体験させる体験させるという取組は素晴らしかった。
老田:
サークルのメンバー5人と先生,当事者の方々と皆で考え取組を進めてきた。
●武山:
富山高専の松坂さんは海外に関心を持ち県内就職しても海外へでられる機会があり自分の世界が広がるという新鮮な観点の発表だったがこの辺をもう少し詳しく説明して欲しい。
松坂:
県内企業で就職したら県内だけの活動になるイメージが私の中にあったが,海外Uターンで実際海外で活動する県内企業を見て,県内へ就職しても県外国外での活動フィールドがあること知ることができた。
●武山:
高度な先進的な学びや文化が東京にあるので出て行ってしまうと指摘いただいたが,文化については富山県には結構あると思う。文化とメディアが発信している情報は区別していく必要があり,地元の人がチャンと自分たちの文化を発信していないことが今回の取組でも触れる機会があって富山にもイイものがあったと気づかせてもらったのではないか。
●武山:
法科大学大谷さんは正規授業では限界があり課外活動をもっと取り入れるサポートが必要ではないかという指摘でしたがその辺を詳しく。
大谷:
私自身が富山の良さに気づいたのは座学ではないボランティア等で活動した結果わかった。座学も良いがプラス何かがあれば良いと思った。
●武山:
学生からの発表を受けて聞きたいことや感想等お願いします。
高木会長:
楽しき聞かせてもらい大変良かった。特に感銘受けたのはこども食堂で,自分たちでやったことは素晴らしい。また,2チームの障害者に寄り添って活動していった報告も素晴らしい。一番大切なのは一緒になって支援し活動していくこと,行政がやっていくなら高額の税負担が必要となる。地元定着についての課題提起や社会安全ボランティアとやま塾での自治体財務への気付き,学校学部を超えての交流も良かった。
●武山:
COC+という形で取り組んできた感想等お願いします。
森市長:
私や高木会長も同じだが東京へ進学して富山へ戻ってきている。東京へ出て行っても帰ってきている人は多い。県の発表だと最近は6割ぐらいがUターン率だという。県外から県内の大学へ学びに来て4年で富山の魅力を体感していただくには短いように感じる。様々な切り口やシーンやステージに立ってもらい経験してもらうことはありがたい。自治体としては各大学の学生さんに大変協力いただいている。行政の課題解決や各分野の現場での研究や実習など地域を支える戦力として県内の各大学に大変お世話になっている。大学の垣根を越えて横の繋がりを持つことはこれからの課題でLABOのような交流の空間を作ることは行政の役目と感じた。県外や国外など何処で学んでも生涯全体で考えて故郷との関わりを常に意識して欲しいと思う。
●武山:クリッカーを利用して学生へ質問してみたい。
Q1「地域活動で富山の魅力を発見したか?」
A1「発見できた」7票100%
Q2「富山の就職何が嫌?」
A2「遊ぶとことが無い」「車が無いと生活できない」「やりたい仕事が無い」「給料が安い」「人間関係が濃い」
Q3「就活の難しいところは?」
A3「やっていけるか不安」「やりたいことが見つからない」「企業の求める人材がわからない」
●武山:
企業の人材がわからないとありますが高木会長お願いします。
高木会長:
富山の嫌なところは同感。北陸3県の幸福度がNO1という調査があるがアミューズメントの項目が無い。大都市と地方の決定的な差であり地方都市の課題でもある。企業がわからないというのは企業側の責任,県も市も責任がある。大学で講義もしたが富山産業観光図鑑を富山商工会連合会で作成し県内190企業を紹介している。学生だけでなく親にも今の企業の姿を知ってもらいたい。企業見学は就職希望者だけでなく広く一般へ対象とすれば富山観光の一翼となる。
●武山:
富山市でもポートラムが完成したとき全国から大勢の視察団が訪れた聞いているが,富山を知ってもらう機会という意味では産業観光と通じるのではないか
森市長:
最先端の技術を持つところは秘匿性が高く産業観光の最も関心の高い企業は公開してくれないことを理解しなければいけない。これからの企業は入社させてから社員教育をやる時代ではなく,自分で自分の能力を高めていかなければ相手にしてもらえない時代になっていく。かっての日本の産業構造の時代とは大きく変わってきている。自分の得意技を人よりも磨いていくことを在学中からやってもらいたい。最低限度の語学力をつけることも必要である。また,東京での収入は大きいが居住費用生活費など富山と比べられないくらい高額である。遊ぶところも与えられることを待つのではなく富山に無ければ出かければ良い。1969年4月2日から1970年4月1日に生まれた学年(現在49歳)富山市に6080人(高校3年時)が,高校卒業以降24歳を底にドンドン減少している。そこから回復し現在17歳時の98.5%(男性)99.8%(女性)まで戻している。県外へ進学・就職しても故郷へ戻ってきている,産業界が頑張って雇用をつくってくれているおかげである。
●武山:
期待がふくらむデータの紹介ですね、高木会長からも情報提供をお願いします。
高木会長:
なぜ地方創生が求められているのか,人口は2008年をピークに減少し10年後には5%,20年後は10%減少で毎年富山県の人口分が減る推測がでている。地方は12年早く進むので10年後には10%減っていく。その中での喫緊の課題解決のために地方創生やCOC+no取組がある。富山市は20年前からコンパクトシティに取組、人口が減っても選ばれるまちづくりを目指している。地域の施設の共有化をはかっていき公共施設の無駄を無くすべきである。官に頼らず自分たちの力で何かやってみる成功失敗を経験していくことが皆さんの成長エンジンになっていると思う。
●武山:
COC+はCOCの流れから継続してやっているが県内では国際大学と県立大学が両方に関わっておられる。会場の各校からコメントをいただきたい。
富山国際大学高木学長:
大学の使命は学生に教育し社会へ送り出すこと。教育の充実は基本だが,先進的なITやAI,最近ではSDGsの観点での拠点として大学の魅力づくり・キャンパスとしていきたい。
富山県立大学中島副学長:
大人と学生との間にギャップがあることを感じた。COCの目的の一つは与えられたことから枠を決められていたことをやっていたことを自分たちが裁量を与えられて自由にやってみることであった。学部の垣根を無くしていろいろやってこれたのが良かった。今後も大学としては続けていきたい。
●武山:
能力特性評価テストを参加校学生にしてもらった。COC+の効果について読み取れることができたようですが。

富山国際大学長尾教授:
今回のCOC+の大きなテーマである課題解決能力をデータに基づきを成熟度を計るため,心理テストを利用して50項目の測定できるようにした。問題解決について問題発見,課題設定,コミュニケーション,協働の作業(コラボレーション),実際にやり遂げることの5つにおいて7校学生にデータをとらせてもらった。詳細の分析まで至っていないが協働力においてはかなりの成熟度が増している。他の項目については今後の教育の実施について課題となる。
●武山:
COC+で学生の協働力の成熟度が高まったことが確かめられたのは大きな成果だったと思う。これから連携が大事となりますコンソーシアム富山の長でもある富山大学齋藤学長からも意見を伺いたい。
富山大学齋藤学長:
県内の7つの大学は富山で育った人の50%ぐらいしか収容できない。地元に残った学生も県外からの学生も大事にしたい。人の幸福度は衣食住だけで無く社会・地域の貢献度や充実度も関係していると思う。充実度・幸福度を上げることが大切。子供を産み育てる幸福度は都会地では低い。富山県民の一人あたりのGDPは国内5位と高い。子育てについても富山市は先駆的に取り組んでいる。昨年の元文科大臣との話しだが,これからの日本は終身雇用の時代では無くなるため,大学はシニアだけではなく30代40代へのリカレント教育をしてほしい,新しい仕事・技術を大学で学び直してスキルアップして仕事にもどす役割を求められてた。皆さんも就職後に学び直したい時には大学へ戻るという選択もある。自らをブラッシュアップして社会貢献でき幸福度があがる活躍をしてもらいたいと期待している。
●武山:
学生のみなさんの感想をもらいます。
大谷:
座学以外の選択肢を増やして欲しいのと,課外活動への金銭的サポートや教職員の関わりを増やして欲しい。
松坂:
話にあった人口減少に伴う地方財政の減少について考えさせられた。富山じゃなくても良いという話しに繋がらないよう方策を考えなければいけない。
老田:
富山県の魅力について考える機会が中高で無くて気づかず県外へ出てしまっている人が多い。中学校ぐらいから富山県の魅力を再確認させる機会をもっと増やしたら良いと思う。v
渡辺:
沢山の人が活動されてきたと思うが,自分自身今回を機会にCOC+の活動を知った。活動をもっと大勢の人に情報発信して多くの人に活動に興味を持って参加してもらえる様なると思う。
宿波:
自分の活動で色々な学校や学部の人と関わる事で自分の専門性以外のことも知れたので,学校を超えた交流の場をこれからもあれば良いと思う。
杉山:
とやま塾のように他大学と関われるものがあれば同じ活動をしている人との交流ができ活動を活発に出来るようになるので増えれば良いと思う。
前田:
COCについて学生はもっと知るべきだったと思った。COCから与えられ学生は受け身になって動いていたと感じた。今の学生は大人から与えてもらうのが当たり前の態度になっている。地元に残らなければいけないのか,外へ出ていっても戻ればいいのか考えさせられ,この場へ参加して本当に良かったと思った。
●武山:
どの意見も非常に貴重な意見で今後の参考にさせてもらう。ありがとうございます。
●武山:
最後に高木会長と森市長から提言をいただきたい。
高木会長:
自ら考え,自らの意思で活動していただきたい。COCは気付きの1ページであり,皆さんの発表を聞いていると自分で気付き自分でやらねばとわかってきたと感じた。今どんな企業でも中堅企業は海外へ行っている。富山の企業に入ったから富山だけという時代は去っている。富山にべースを置きながら世界へ日本人の良さを示し稼いで地方を豊にしていく気概を持ってやっていってもらいたい。
森市長:
ノーベル賞受賞した梶田さんは週末富山へ戻り暮らしを楽しんでいる。そう言う時代になっている。一つの場所に仕事も居住も家族もではなくて,色々な生き方がある。人口が減っても豊かな暮らしにすれば良い。徳川時代はイノベーションを禁止し思考停止させることで体制を維持してきた。イノベーションは大事である。ハイスペックに限らず,異なる分野の融合で新しいものが生まれる,色々な人と出会うことで自分が触発されて新しいことを生み出すイノベーションが大切なので若いからこそ色々なことにチャレンジして自分を磨きブラッシュアップしてもらいたい。
●武山:
立山連峰の眺めは宝であり,それに基づく文化があり産業がある。3月に南北接続するライトレールには全国から注目されている。富山にはスゴイ物がある。本物を考え持続可能な社会を目指す動きは世界中で求められている中で富山は世界へ発信していく役割を担うべきだと思う。皆さんの時代には世界中が富山を目指す人が増える社会を作っていってほしい。そのためにもっと富山を好きになってもらいたい。

この事業は平成27年から始まり本年で5年の区切りをつけ,国からの予算は打ち切られるが,これだけの成果があがり今後も継続していきます。富山を元気にする,若者が富山を好きになってもらい,若い人の職場を提供していく,富山の自然の中で生活の質を高めていく。都会で就職した人,学んだ人も故郷に戻ってきてリカレント教育をしていただき更に発展する形でブラッシュアップして幸せな人生を歩んでもらいたいと思っている。
こういった事業には産官学金多くの皆さんの支援があって成し得た物と思っています。改めて皆さまのご支援に感謝し,今後もこの事業を続けていき富山を魅力あるものにしていきます。これからもご支援をよろしくお願いします。