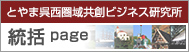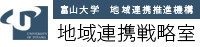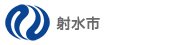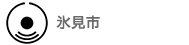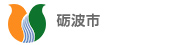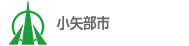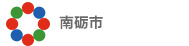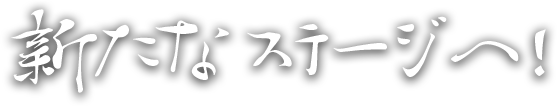
事業レポート Report
とやま呉西圏域共創ビジネス研究所第4期15日目
修了式
会場:オンライン(Zoom)
とやま呉西圏域共創ビジネス研究所第4期修了式がオンラインで開催され,研究生が約6ヶ月間にわたり学び構想した事業プランの最終プレゼンテーションがおこなわれ,高岡市長,富山大学長,協力・後援機関の関係者,とやま呉西圏域行政関係者,富山大学関係者,OB研究生等が参加した。
主催者挨拶 とやま呉西圏域共創ビジネス研究所所長
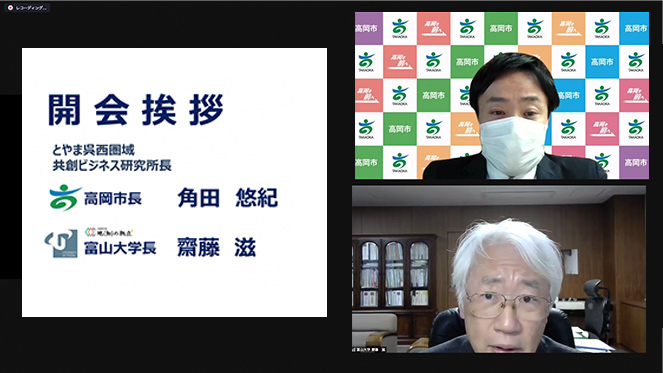
本研究所は研究生同士の連携など将来へ向けた呉西圏域の人材のネットワークの構築につながるだろう。また,本事業は産学官金が連携した地域イノベーション創出の取り組みであり,呉西圏域のイノベーション創出に取り組む人材への力強い支援をお願いしたい。
富山大学は地域活性化のニーズに応じた人材育成・地域活性化に貢献したいと考えている。地域の資源や変化・課題をビジネスにつなげる上で人材は財産である。これまでの修了生が呉西地域で活躍されている。産学官金が連携する本研究所が今後も発展し,新しいプロジェクトが生まれていくことを期待している。
経過報告 とやま呉西圏域共創ビジネス研究所事務局
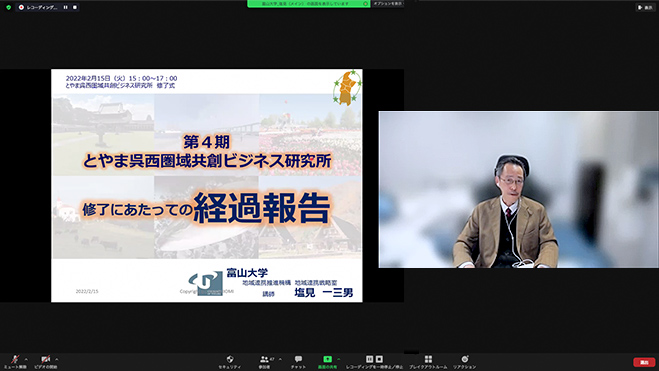
この研究所は,地域の困りゴトに対して企業がビジネスとして何をすべきかを見つめ直してもらう,民間事業者向けの地域人材育成プログラムです。企業が地域課題解決に取り組む場合は,その行為から収益を上げることは難しい場合が多いですが,それでも持続するシステムとするには,何をリターンとするかが重要となります。合計15回,約半年にわたるプログラムは,呉西圏域で活躍されるゲストスピーカーの講義,教員と研究生によるゼミを通じて,各研究生は自社の地域課題解決ビジネスのコンセプトづくりを進めてきました。この後発表がありますが,研究生の業種は何か,どういう地域課題解決を目指すのか,リターンは何か,について考えながら聞いて頂けると,醍醐味が伝わるかと思います。
地域課題解決プロジェクト報告
研究生がそれぞれ構想した事業プロジェクトについてプレゼンテーションをおこなった

- 浅井千春研究生(株式会社with one)
- タイトル:『ANATATO Project』多様な人々が出逢い繋がる場所「soup&caféもやいこ
- 感想コメント;呉西圏域の地域課題について学び,ニュースなどで認識していたテーマも具体的で身近な地名での数字を示されたことで切実な問題として考えることができた。
- 浅見直希研究生(藝術農民)
- タイトル:「交響する農村」を目指して「農村型“複業”モデル」の見える化社会実験
- 感想コメント;地域課題ビジネス事例を学び,地域課題解決へ向けた意義のあるものと感じた。研究生の多様な仲間と共通テーマで連携や夢を語れることができた。
- 浅見裕子研究生(里山Retreat&Kitchen阿迦舎)
- タイトル:SATOYAMA-Regenerative ~久目の果樹物語~
- 感想コメント;これまでぼんやり描いていたプランを肉付けする機会となった。県内での事例を学び様々なインスピレーションを得ることができた。
- 河原正嗣研究生(河原産業株式会社)
- タイトル:交流・関係人口の創出・拡大による持続可能な地域づくり
「Try country side! IN速川 ~田舎を試す!~ - 感想コメント;多様な発想や考え方を学び良かった。
- 木村広研究生(株式会社海王フーズ)
- タイトル:万葉さんぽ ―射水郡(いみずごおり)型マイクロツーリズムー
- 感想コメント;事業の中で漠然と動いていたテーマが,ゼミで明確な形とすることができた意義のある6か月間であった。
- 竹中志光研究生(株式会社TM工房、クラフタン)
- タイトル:昆布で健康 KOMBU HOUSE ~子ども達の未来のために~
- 感想コメント;学びが多く,研究生同士のつながりが深くなり,新たな出会いも多くあった。
- 宮脇友基研究生(株式会社ミヤワキ建設)
- タイトル:さよなら、労働力不足 -近くにあった、遠かった社会―
- 感想コメント;たくさんの気づきを与えて頂いた皆さんに感謝している。
- 平美穂研究生(株式会社北陸リフォーム)
- タイトル:空き家×婚活=「熊無」再生 ~建設会社による集落再生を通じた自社価値創造の挑戦~
- 感想コメント; 参加は2回目となる。仲間ができたことが自分にとって良い機会となった。事業内容の整理を受け,自分の行動が新たに見えてきた。
- 米山勝規研究生(株式会社リボン)
- タイトル:人と地域ビジネスを結ぶ事業承継屋
- 感想コメント;参加して多面的な見地から事業をとらえなおすことができた。事業をポスター化するところまでサポートして頂き学ぶことができた。
- 日名田優研究生(株式会社あつみファッション)
- タイトル:女性の移住促進に向けた働く場もある 空き家シェアハウス
- 感想コメント;自社の発展や地域内の経済循環を見越した若鶴酒造の稲垣さんの話が印象に残った。大変有意義な時間を過ごし感謝している。(欠席のため、事務局よりプロジェクト概要説明。)
修了証授与
研究所所長の角田市長が修了証を読み上げ,研究生10人のカリキュラム修了を宣言した。

研究生へのメッセージ
研究生の発表を受けた感想などのコメントやエールが送られた。
地域での生活基盤を置いて,そこに産業を形づくるという熱意を感じた。参加者が協力して新しい事業が展開できるということはこの取り組みのメリットである。今後事業を起こすにあたっても過去の修了生の方々と連携して自ら考えた事業を成功させてほしい。皆さんの一つ一つの努力が地方創生に関わり,富山県の発展のためにも求められている。今後の活躍を期待している。
皆さん方が捉えていただいた課題は高岡や富山呉西圏域だけの課題ではなく,日本全国が抱えている社会課題であると思う。それらの取り組みの解決方法の一つを呉西圏域から発信していく,皆さん方の事業がますます大きくなっていく,行政も何ができるのかをしっかり考えていきたい。
見え方だけのデザインではなく中身のデザインを注目して欲しい。見出しは考え方を一番端的に示す言葉がでてこなくてはいけない。共感してもらうことが重要でプロジェクトの考え方のベースを垣間見え,プラスを目指す具体的な表現が必要である。言葉の意味を大切にキーワードを盛り込むと伝わりやすい。
皆さんこの半年間,ご自身の地域活性化の事業のゴールをどこに置くか,
今後それぞれの目標に向かって邁進していくことを確信した。イノベーションは何かと何かを掛け合わせることで新しいものを目指すもので,人と人との繋がりが補完効果・相乗効果をもたらすと思っている。
地域課題をじっくり考えて,良い面悪い面を見つけそれぞれの企業を活かした取り組みや方針を出されたと感じた。研究会で皆さんが対話・意見交換する中で様々な気づきに背中を押された。今後の活躍を期待している。
地域に人を呼び込むだけでなく地域の様々な方と共に進めようという姿勢に感銘を受けた。将来像として企業利益のためだけでなく社員教育やヤリガイ醸成の考察力や情報発信力を持っていることは素晴らしい。横のつながりを大切に今後も頑張ってもらいたい。
地域金融機関も外部機関と連携して地域活性化に取り組んでいる。協力機関である地域金融機関にもできることがある。皆さんの地域活計化プロジェクトを実行して富山呉西圏域の活性化に取り組んでいきたい。今後の活躍を期待している。
事業プランを実行し,継続していく上で金融機関に何ができるのか,ご相談いただきたい。
地域課題の難しいテーマへの取り組みは大変参考になった。これから現状分析やテーマを発展させ実践されるということで連携し相乗効果を出していくと感じた。
事業として継続していくにはコストに見合うリターン獲得や思いもよらない壁にもぶつかっていくと思う。周りを巻き込みながら進めていくことが肝要。人口減少高齢化社会を改善し事業発展させてほしい。仲間と共に進める事業は必要であり,そのような企業が評価される社会にならなければいけない。
自分たちの街のことを様々な視点で知ることが大切だと思った。引き続きチャレンジしてほしい。人脈・ビジネスのストーリー・発信力が大事。何時までどうするという時間軸を考えて取り組んでほしい。また持続可能であることも考慮いただきたい。
閉会挨拶

第4期となり年々レベルが上がってきたと感じた。継続することは大きな力である。修了生の方々が講師となり次の世代を育てていくようになればと願う。仲間ができたことは大変心強く,普段考えないコトや観点に繋がったと思う。