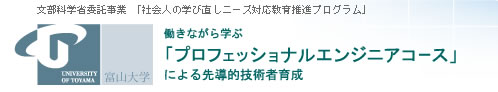ホーム > 受講生の皆様へ > 講義内容(シラバス)> 先端環境・バイオ工学特論Ⅰ
講義内容(シラバス)
先端環境・バイオ工学特論Ⅰ
授業科目名 |
先端環境・バイオ工学特論Ⅰ |
||
担当教員(所属) |
《富山大学大学院理工学研究部(工学系)》遠田浩司、加賀谷重浩 |
||
開講日程 |
1月-3月 土曜日 1,2限 |
単位数 |
2単位 |
連絡先(研究室、電話番号、電子メール等) |
遠田浩司 工学部化学棟3階3302 |
オフィスアワー(自由質問時間) |
土曜講義終了後30分程度。 |
授業のねらいとカリキュラム上の位置付け(一般学習目標) |
|||
環境への負荷を低減しつつも持続可能な社会を構築するために、環境問題をより化学的に考える力をつけることを目的とする。そのために、大気、水質の問題をはじめその分析法、廃棄物の処理問題やリサイクルについて解説する。 |
|||
達成目標 |
|||
今日の環境問題(地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、水質汚濁、廃棄物など)と、それに対する対策(環境分析、水処理技術、リサイクル等)に利用されている要素技術の原理と現状を理解する。それにより、環境と社会、企業、そして人間との係わりを自ら化学的に考え対処してゆく力を付ける。 |
|||
授業計画(授業の形式、スケジュール等) |
||
第1回 |
環境計測Ⅰ:概論 |
|
第2回 |
環境計測Ⅱ:化学センサー法特論 |
|
第3回 |
水処理技術Ⅰ:汚水処理特論 |
|
第4回 |
水処理技術Ⅱ:水質有害物質特論 |
|
第5回 |
環境分析Ⅰ:機器分析法による環境汚染化学物質の測定 |
|
第6回 |
環境分析Ⅱ:クロマトグラフィーによる環境汚染化学物質の分析 |
|
第7回 |
環境分析Ⅲ:固相抽出法による環境試料の前処理 |
|
第8回 |
環境分析Ⅳ:有害化学物質における健康影響 |
|
第9回 |
大気圏の環境Ⅰ |
|
第10回 |
大気圏の環境Ⅱ |
|
第11回 |
水環境分析Ⅰ:試料の前処理法 |
|
第12回 |
水環境分析Ⅱ:オンサイト計測法 |
|
第13回 |
環境調和型材料Ⅰ:セッコウのリサイクル |
|
第14回 |
環境調和型材料Ⅱ:セッコウのリサイクル |
|
第15回 |
まとめ |
|
キーワード |
地球温暖化、水質汚濁、水処理、環境分析、廃棄物のリサイクル |
履修上の注意 |
化学・物理の基礎知識(大学卒業程度)を必要とする |
教科書・参考書等 |
授業で指定する |
成績評価の方法 |
出席とレポート |
関連科目 |
環境化学、分析化学 |
備考 |
|
先端環境・バイオ工学特論Ⅰ:授業計画
回 |
主題と位置付け |
学習方法と内容(講義概要) |
1 |
環境計測Ⅰ: (遠田) |
まず、地球規模で進行する環境問題の現状を環境白書に基づいて解説する。次に、本コースで行う大気圏・水環境、環境分析、水処理・廃棄物処理技術、リサイクル等に関する講義全般の概要を解説し、如何にすれば環境への負荷を低減し環境調和型の社会を構築できるのかを化学の立場から論じる。環境問題を正確に把握するためには環境中の化学物質の量や分布を精密に測定する必要がある。この環境計測の総論について概説する。 |
2 |
環境計測Ⅱ: (遠田) |
川水や排水等の水環境中の有害重金属イオンや有害有機物質を連続的にモニターできる化学センサー法について解説する。化学センサーを電位応答型(ポテンシオメトリーセンサー)、電流応答型(アンペロメトリーセンサー)、光学的特性変化型(オプティカルセンサー)に分類し、それぞれの電気化学的および光学的応答の原理について説明する。また、センサー作製法、測定法について述べ、化学センサー法での環境モニタリングがどこまで可能なのか論じる。 |
3 |
水処理技術Ⅰ: (加賀谷) |
事業場の各工程から発生する廃水(汚水)は、含有する有害物質などを除去し、水質汚濁防止法に係る排水基準の許容限度以下であることを確認した後、公共用水域などに放流しなければならない。ここでは、汚水処理技術に関する要素技術、特に物理化学的処理技術(固液分離、pH調整、酸化還元、吸着・イオン交換など)について基礎原理を中心に概説する。 |
4 |
水処理技術Ⅱ: (加賀谷) |
排水基準項目であるいくつかの有害物質、特に重金属類、シアン、アンモニア・亜硝酸・硝酸、農薬類、揮発性有機化合物(有機塩素系化合物、ベンゼンなど)について、各種要素技術を用いた除去・分解技術について概説する。また、これらの除去・分解技術に関する最近の研究動向について紹介し、実用性や課題などについて議論する。 |
5 |
環境分析Ⅰ: (井上) |
現代社会で流通している化学物質は5万種類以上といわれている。我々は、無意識の内に一般環境中でこれらの化学物質に曝露されている。また、一般環境中に存在する化学物質は多種多様であり、同時に複数の化学物質による複合曝露を受けていることとなる。従って、多数の化学物質を高精度に測定する必要がある。本講義では、環境分析の意義と、環境分析に用いられる機器分析法について概説する。 |
6 |
環境分析Ⅱ:クロマトグラフィによる環境汚染化学物質の分析 (井上) |
環境中に存在する化学物質は極微量であると同時に多種多様である。そのため、環境分析に用いられる分析手法には、高精度・高感度と共に、多成分一斉分析が可能であることが要求される。クロマトグラフィは分離と検出が高度に融合された分離分析手法であり、環境分析には欠かすことのできない分析手法である。本講義では、クロマトグラフィの基礎と実際について概説すると共に、環境分析への応用例について紹介する。 |
7 |
環境分析Ⅲ: (井上) |
微量化学物質の測定においては、試料中の夾雑物質による妨害が大きな問題となる。これら夾雑物質を如何に除去あるいは低減させることができるかが、分析値の信頼性を大きく左右する。試料前処理法としては溶媒抽出法が広く用いられてきたが、測定精度や簡便性、さらには環境負荷といった観点から、固体吸着剤を用いる固相抽出法に移行しつつある。本講義では、固相抽出法の基礎と実際について概説する。 |
8 |
環境分析Ⅳ: (井上) |
環境や身近に存在する有害物質の濃度はppb (10-6 g/L) レベルと非常に低濃度である。例え低濃度であっても、長期に渡る連続的な曝露により、化学物質過敏症や慢性中毒、さらには発ガン等の重篤な健康被害を生み出すことがある。本講義では、有害化学物質による健康影響と、機器分析法によるそれら化学物質の測定手法について概説すると共に、アルデヒド類、臭素酸およびヒ素化合物の例を紹介する。 |
9 |
大気圏の環境Ⅰ (鳥山) |
富山高専にて講義 |
10 |
大気圏の環境Ⅱ (鳥山) |
富山高専にて講義 |
11 |
水環境分析Ⅰ: (間中) |
富山高専にて講義 |
12 |
水環境分析Ⅱ: (間中) |
富山高専にて講義 |
13 |
環境調和型材料Ⅲ:セッコウのリサイクル (袋布) |
富山高専にて講義 |
14 |
環境調和型材料Ⅳ: (袋布) |
富山高専にて講義 |
15 |
まとめ (遠田) |
環境負荷を低減し、環境調和型の持続的社会を構築するためにはどうすればよいのかを論じ、講義全体の総括を行う。 |