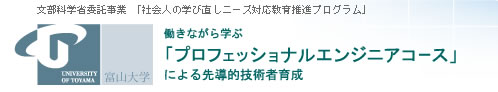�z�[�� �� ��u���̊F�l�� �� �u�`���e(�V���o�X)�� ��[���E�o�C�I�H�w���_�U
�u�`���e�i�V���o�X�j
��[���E�o�C�I�H�w���_�U
���ƉȖږ� |
��[���E�o�C�I�H�w���_�U |
||
�S������(����) |
�s�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�n�j�t |
||
�J�u���� |
8-10�� �y�j��1,2�� |
�P�ʐ� |
�Q�P�� |
�A����(�������A�d�b�ԍ��A�d�q���[����) |
�������i������5�K6506�����A |
�I�t�B�X�A���[(���R���⎞��) |
�����i�ł��邾������̍u�`�I�����オ�]�܂����j |
���Ƃ̂˂炢�ƃJ���L��������̈ʒu�t��(��ʊw�K�ڕW) |
|||
���C�t�T�C�G���X�E��ÁE�n��Ɋւ��H�w�Z�p�A�����𗘗p����L�p�����̐��Y�ȂǁA�����H�w�̌���ƍ���̍L����𗝉�����B |
|||
�B���ڕW |
|||
1.��ÁE�n��Ɋ�^����o�C�I�Z���T�̊J���Ɣ��W�ɂ��ė�������B |
|||
���ƌv��i���Ƃ̌`���A�X�P�W���[�����j |
||
��P�� |
�u�`�T�v�i���̍u�`�ʼn����w�Ԃ��A�܂��������҂��邩�j�Ɨ\�� |
|
��Q�� |
�o�C�I�Z���T���Ēm���Ă܂����H�i�o�C�I�Z���T�̊�{�\��������p�܂Łj |
|
��R�� |
�o�C�I�Z���T�̔��W�Ɖ��p(��`�q�H�w�E�זE�H�w�̗��p���琶�̖͕�Z���T�܂�) |
|
��S�� |
�A���C�Z�p�A���ʕ��͑��u�A�����c�m�`�V�[�N�G���T�[���̐i���Ƌ��ɔ��W�������q�����w |
|
��T�� |
�ŐV�H�w�Z�p�ɂ�鎾���̉𖾂Ǝ��� |
|
��U�� |
�R�̈��Ƃ́H |
|
��V�� |
�R�̍쐻�̐V�Z�p |
|
��W�� |
���G�Ȕ]�̂����݁@�i�w�K�E�L�����J�j�Y���𒆐S�Ƃ��āj |
|
��X�� |
�]�Ƌ@�B���Ȃ��Z�p�@�iBrain Machine Interface�j |
|
��10�� |
��[��Âɗ��p�����H�w�Z�p |
|
��11�� |
�זE����g�D�����g�D�Đ���H�w |
|
��12�� |
�����|�{�Z�p�̐i�W�J�i��ʔ|�{�Z�p���瓮���g�D�̔|�{�܂Łj |
|
��13�� |
�����n�����p�����L�p�����w�������Y�@�̊J�� |
|
��14�� |
����������͗��_�̐V�W�J�i���[�����g��͖@�j |
|
��15�� |
�V�K�����Z�p�i���L�����[�ޗ��AHILIC�A���̕��q�ԑ��ݍ�p��͓��j |
|
�L�[���[�h |
�����H�w�A���C�t�T�C�G���X�A��ÁA�n��A�o�C�I�Z���T�A�o�C�I���͋@��A�R�̈��A�]�Ȋw�A�H�i���� |
���C��̒��� |
�����w���w�Ŋw��ł���K�v�͂Ȃ����A�ł�����莩�ȗ\�K�i���{�̐����w���x�j������邱�Ƃ��]�܂����B |
���ȏ��E�Q�l���� |
�e�u�t������̍u�`���Ɏw�����܂��B |
���ѕ]���̕��@ |
�o�ȓ_�A�u�`���̏��e�X�g�y�у��|�[�g��o�̑����_�łU���ȏ�����i�Ƃ���B |
�֘A�Ȗ� |
���E�o�C�I�P�A�@�핪�͂Q |
���l |
�����w�A�����Ȋw���w�ŗ��C���Ă��Ȃ��ٕ���̎�u�҂ł��킩��悤��b���狳�����A����A�w���ŗ��C������啪��̋߂���u�҂ɂ��\���ŐV�̒m�����C���ł���悤�ɔz������\��ł��B |
��[���E�o�C�I�H�w���_�U�F���ƌv��
�� |
���ƈʒu�t�� |
�w�K���@�Ɠ��e�i�u�`�T�v�j |
�P |
�u�`�T�v�Ɨ\��A�����ču�`�̐i�ߕ��Ɋւ��鑊�k (���j |
���̍u�`�̊T�v�Ɨ\����������ƂƂ��ɁA��u���̃o�b�N�O���E���h�≽�����҂��ė��C���ꂽ�����A���S�����Ă�u�`�ɂȂ�悤���k���܂��B |
�Q |
�o�C�I�Z���T���Ēm���Ă܂����H�i�o�C�I�Z���T�̊�{�\��������p�܂Łj (���j |
��Ðf�f�A�n��X�N���[�j���O�A���v���A�H�i�Ǘ��ȂǂŖ𗧂��Ă���o�C�I�Z���T�̊�{�\���A�v������������p�܂ł��Љ�܂��B�y�f�Z���T�A�Ɖu�Z���T�A�������Z���T�Ȃǂ���������������Đ������܂��B |
�R |
�o�C�I�Z���T�̔��W�Ɖ��p�@ (���j |
��`�q�H�w��זE�H�w�Ȃǂ̃o�C�I�e�N�m���W�[�̔��W�Ɣ����̋Z�p�E���w�v���Z�p�Ȃǂ̃G���N�g���j�N�X�̐i�W���h�b�L���O�����V�K�ȃo�C�I�Z���T�̊J���A����ɂ͖��o��k�o�Ȃǐ��̋@�\��͕킵���p�^�[���F���^�o�C�I�Z���T�̊J���ɂ��ďЉ�܂��B |
�S |
�A���C�Z�p�A���ʕ��͑��u�A�����c�m�`�V�[�N�G���T�[���̐i���Ƌ��ɔ��W�������q�����w (���V�j |
2000�N6���̃q�g�Q�m����NJ������_�@�ɁA�o�C�I�e�N�m���W�[�͐����w�̔��e���o���A�d�q�E���H�w�Z�p�Ƃ̗Z�����ւčX�ɔ��W�𑱂��Ă���B���݂̃|�X�g�Q�m������������x���Ă���̂́A�ԗ��I��͂��s�����߂̍��������x�@��̊J���ƁA����ꂽ�c��ȃf�[�^�[���������邽�߂̏���Z�p�ł���B�{�u�`�ł͂����ŐV�̃e�N�m���W�[���Љ��B |
�T |
�ŐV�H�w�Z�p�ɂ�鎾���̉𖾂Ǝ��� (���V�j |
��4��̍u�`�Ɉ��������A���̍ŐV�̃e�N�m���W�[�A�o�C�I���͎�@��@��̕a�C�̐f�f�E���Âւ̉��p�Ȃǂɂ��ďЉ��B |
�U |
�R�̈��Ƃ́H (�镔�j |
���݁A�R�̈��ƌĂ����i�����ڂ��W�߂Ă���B�l�͖{���A�̓��ɐN���E���������ٕ�������� (�R��)����̂���邽�߁A�u�R�́v���Y�����Ă���B���̍R�̂��Ƃ��ėp���邱�ƂŁA����܂ŗL���Ȏ��Ö@���Ȃ��������E�}�`����ɑ��ėD�ꂽ���ʂ����R�̈�J���������B�{�u�`�ł͌��݂ǂ̂悤�ɍR�̈���p����Ă���̂��ɂ��ĉ������B |
�V |
�R�̍쐻�̐V�Z�p (�镔�j |
�R�̈��́A�{���q�g���Y�����鐶�̖h�䕪�q�𗘗p���邱�Ƃ���A����p�����Ȃ��傫�Ȍ��ʂ����҂ł���B�������A���Ì��ʂ̍����R�̂��J������ɂ́A�L�v �ȍR�̂��ł��邾�������I�ɒP�����A���Y�Ɍ��т���K�v������B�{�u�`�ł͌��݂ǂ̂悤�Ȏ�@�ōR�̂̃X�N���[�j���O���s���A�ǂ̂悤�ɐ��Y����Ă��邩�ɂ��ĉ������B |
�W |
���G�Ȕ]�̂����݁@ (�쌴�j |
�]�̋@�\�́A�l�X�Ȑ_�o�זE�����݂��Ɍ������Đ_�o��H���`�����邱�Ƃɂ�蔭�������B���������āA�]�����ł́A�X�̗v�f�̐����ƏW�c�̃}�N���Ȑ������ǂ̂悤�Ɋւ���Ă��邩��ǂ��������邱�Ƃ��d�v�ł���B�{�u�`�ł͐_�o�זE�̓d�C�I��������A����炪�\������_�o��H�̐����A�����āA�]�̒��̗l�X�ȗ̈悪�ւ��w�K�E�L���Ɋւ��ĊT������B |
�X |
�]�Ƌ@�B���Ȃ��Z�p (�쌴�j |
�ߔN�A�l�X�Ȑg�̓I��Q�����l�̋@�\��⊮���邽�߂ɁA�]�̐_�o�����𑪒肵�A����Ɋ�Â��ĕ⏕����@�B�����Z�p�̊J�������݂��Ă���B���̋Z�p�͏�Q�����̂��߂����ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̔]�@�\�i����\�́j���g��������\������߂Ă���B�{�u�`�ł́A������p���������𒆐S�ɔ]�_�o�����̑���Z�p�Ɛl�ւ̉��p����_���T������B |
10 |
��[��Âɗ��p�����H�w�Z�p�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(����) |
�f�f�@��A���Ë@��ȂLj�Â̌���ɂ����Ă͗l�X�ȍH�w�Z�p�����p����Ă���B���̂����݂⌴����ʂ��āA�H�w�Z�p�������Ɉ�Â̐i���Ɗւ��A�v�����Ă��邩���������B |
11 |
�זE����g�D�����g�D�Đ���H�w �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(����) |
���a��O���Ȃǂɂ���Ď���ꂽ�g�D���@�\���זE�̗͂�p���ďC���E�u���E�Č��E��������Đ���Â�g�D�H�w�B���̊�b�ƌ���A���_���T�����A�Ő�[�̌����ɂ��ďЉ��B |
12 |
�����|�{�Z�p�̐i�W�J (����j |
�����̑�Ӌ@�\�����p�����������Y�⓮�A���g�D�ɂ��e�퐶�������]���E���f�����Ȃǐ�����p�����Z�p�J���͂��̗p�r�̍L����ƂƂ��ɋ}���ɐi��ł���B���ɁA�|�{�Z�p�́A�����̑�ӁE�@�\�𖾂ȂǂƂƂ��ɂ��̐����̓������\�����������邽�߂̔|�{�f�ނ̊J���A�|�{�����A�|�{���u�Ȃǂ��s���Ă��蒍�ڂ����Z�p�ɂȂ��Ă����B�{�u�`�ł͔������ɂ��H�Ɖ���ڎw������ʔ|�{�Z�p����畆���̎O�����|�{�Z�p�܂ōŐ�[�ȋZ�p���Љ��B |
13 |
�����n�����p�����L�p�����w�������Y�@�̊J�� (����j |
�����A�y����A���y�H�i����̓��̏����ǂȂǂł͑��푽�l�Ȑ������������Ă���B�����̊��ł́A���퐶���ԋy�шَ퐶���Ԃ̕����ړ��E�ڐG�Ȃǂ̑��ݍ�p�ɂ��A���̑�ӂ╨�����Y�̒����E���䂪�s���Ă��邱�Ƃ�����ɖ��炩�ɂȂ��Ă����B�����ŁA���̂悤�ȋ����n�����p�����������Y�̎�������グ�A�����Ŋ��Ă��鐶���̕��͕��@�A�����n��͔|�{�Z�p�Ȃǂ��������ƂƂ��ɁA����̓����ɂ��ēW�J�ɂ��ďЉ��B |
14 |
����������͗��_�̐V�W�J (�{���j |
�����t�̃N���}�g�O���t�B�[�́A�o�C�I�e�N�m���W�[�A��w��w��t�@�C���P�~�J���Ȃǂ̗l�X�ȕ���ŕ��L���g�p����Ă���B���̕�����������͂���ꍇ�A�]������u�i���_�v�Ɓu���x�_�v�����p����Ă����B���݂ł͐V���ɁA���[�����g���_���N���}�g�����n�̕ێ����t�╨���ړ����x�̒�ʓI�ȉ�͂ɗ��p����Ă���B�{�u�`�ł͎�ɁA���[�����g��͗��_�̊T�v��������A�N���}�g�����n�ւ̓K�p�ɂ��ďЉ��B |
15 |
�V�K�����Z�p (�{���j |
�����t�̃N���}�g�O���t�B�[�ɂ́A���݂��X�Ȃ鍂���\���A�������ƃ~�N�������v������Ă���A����ɑΉ������V�K�����V�X�e������сA�l�X�ȍ\���I�����i�`��⑽�E���j��L���镪���ނ��J������Ă���B�{�u�`�ł͐V�K�����n�̋�̗�Ƃ��āA���L�����[�����ނƐe�������ݍ�p�N���}�g�O���t�B�[�iHILIC�j���̂�グ�A���̕����������������B�܂��N���}�g�O���t�B�[�n�𗘗p���鐶�̕��q�ԑ��ݍ�p�̉�͖@�ɂ��āA���̊T�v���Љ��B |