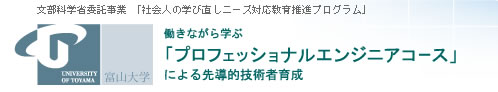�z�[�� �� ��u���̊F�l�� �� �u�`���e(�V���o�X)�� ��[�@�핪�͓��_�U
�u�`���e�i�V���o�X�j
��[�@�핪�͓��_�U
���ƉȖږ� |
��[�@�핪�͓��_�U |
||
�S������(����) |
�s�x�R��w��w�@���H�w�������t |
||
�J�u���� |
10���|12���@�y�j��1�C2�� |
�P�ʐ� |
�Q�P�� |
�A����(�������A�d�b�ԍ��A�d�q���[����) |
�x�R��w�@�핪�̓Z���^�[�@076-445-6825 |
�I�t�B�X�A���[(���R���⎞��) |
�ؗj���P�U���ȍ~ |
���Ƃ̂˂炢�ƃJ���L��������̈ʒu�t��(��ʊw�K�ڕW) |
|||
��[�Ȋw�Z�p�̔��W�ɂ́A�����̃i�m���x���ł̍\���Ƌ@�\�Ɋւ����d�v�ł���B�{���Ƃł́A�ŐV�̑�^���͋@���p���������̉�͂Ȃ�тɕ��͂̌����Ɖ��p���������B���A���K�ł́A�@�핪�͎�舵���̎��ۂ��w�C����B |
|||
�B���ڕW |
|||
1.��^���͋@��𗝉��ł��� |
|||
���ƌv��i���Ƃ̌`���A�X�P�W���[�����j |
||
��P�� |
��^���͋@��Ƃ́@�A�@���͋@��̓��ӁE�s���ӁE����͈͂ɂ��� |
|
��Q�� |
���q�\����͂��̂Q�@�c�m�`�V�[�N�G���T�[��p������`�q���̉�� |
|
��R�� |
���q�\����͂��̂R�@�M���͂̊�b�Ɖ��p |
|
��S�� |
���q�\����͂��̂S�@���w�E����Y�Ƃɂ�����M���͂���тw�������@�̉��p |
|
��T�� |
���q�\����͂��̂T�@�j���C����p���镪�q�\����͂̊�b�Ɖ��p �@ |
|
��U�� |
���q�\����͂��̂U ����p�������͋Z�p�̊�b�Ɖ��p�@ |
|
��V�� |
���q�\����͎��K�P�@�M���͖@ |
|
��W�� |
���q�\����͎��K�Q�@�j���C�����u |
|
��X�� |
�����E���͂��̂P�@�U�������v���Y�}�����������͂̊�b�Ɖ��p |
|
��10�� |
�����E���͂��̂Q�@�N���}�g�ɂ�镪���E���͂̊�b�Ɖ��p |
|
��11�� |
�����E���́E�\����͂��̂P�@�k�b�|�l�r�^�l�r |
|
��12�� |
�����`�ԕ��͂��̂P�@�����d�q�������̊�b�Ɖ��p |
|
��13�� |
�����`�ԕ��͎��K�P�@��^�����ώ@�E��`�q�����ƃ��A���^�C����� |
|
��14�� |
�����`�ԕ��͎��K�Q�@���œ_���[�U�[�������ώ@ |
|
��15�� |
�܂Ƃ� |
|
�L�[���[�h |
�����@���w�@���w���́@��^���͋@�� |
���C��̒��� |
�����E���w�̊�b�m��(��w���ƒ��x)��K�v�Ƃ��� |
���ȏ��E�Q�l���� |
���ƂŎw�肷�� |
���ѕ]���̕��@ |
�o�Ȃƃ��|�[�g |
�֘A�Ȗ� |
�����@���w�@�ő̕����@���͉��w |
���l |
|
��[�@�핪�͓��_�U�F���ƌv��
�� |
���ƈʒu�t�� |
�w�K���@�Ɠ��e�i�u�`�T�v�j |
�P |
�E��^���͋@��Ƃ� (�����j �E���͋@��̓��ӁA�s���ӁA�� �@���͈͂ɂ��ā@�@ (�ܕz) �E���q�\����͂��̂P�@ �w����͂̊�b�Ɖ��p (�����j |
�E�{�u�`�̂͂��߂Ƃ��āA�@�핪�͂̒�`�ƁA�x�R��w�@�핪�̓Z���^�[�Ƃ��̏����E�o�^�@��̊T�v���������B |
�Q |
���q�\����͂��̂Q (����j |
�����̈�`�q����A,G,C,T�̂S��ނ̉���ŃR�[�h����Ă���A�����4����̔z��ɂ���`�q�Y���i�^���p�N�����j�̋@�\�����߂��Ă��܂��B���̂��߉���z�����ǂ��邱�Ƃ���`�q�Y���̋@�\���𖾂�������ƂȂ�܂��B�{�u�`�́A����z��@�Ɋւ����{�����������ł��ADNA�I�[�g�V�[�P���T�̋@�\�������ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��܂��B���p��ɂ͒��߂������Ȃ���A�����̕��X�����������Ă�悤�ɍu�`�������Ȃ��\��ł��B |
�R |
���q�\����͂��̂R�@ (���R�j |
�䂪�������E�ōŏ��ɊJ�������M�V���̋Z�@�𒆐S�ɁA�e��M���͖@�̊�b�I�����A��͖@�𗝉����A�ϔM�����A�M�A���ޗ��̌����E�i���Ǘ����ւ̉��p�ɂ��Ēm��B |
�S |
���q�\����͂��̂S�@ (�݁j |
�͒ʏ�L�@���̌̂ł����āA�����I����щ��w�I�����̈قȂ鑽���̌������`�����݂��邱�Ƃ����X����B���̌������`�̗l�X�Ȑ������������邽�߁A���낢��̕��͎�@���g����B�{�u�`�ł͐����Ƃ̌������ŐV��̒T�����珤�i���Ɏ���܂ł̉ߒ��ŁA�̕����]���ɕK�v�ȔM���͋y�тw�������̗l�X�Ȗ����ɂ��ďq�ׂ�B |
�T |
���q�\����͂��̂T (���c�j |
���q�̍\�������肷��ł��ėp�I�ŏd�v�ȃv���g���A�Y�f���̊j���C���X�y�N�g�����葕�u�̌����ƁA��̓I�ȃT���v����p���ăX�y�N�g���̑���@���C�����A���肵���X�y�N�g���̉�͂ɂ��\�������肷����@���C������B |
�U |
���q�\����͂��̂U�@ (���X�j |
�����O�z���X�y�N�g���́A��ʂɓd�q�J�ڂɂ���ċN������z���ł���B����A�ԊO���z���iIR�j�ƃ��}���U���́A���q�U���ɂ���Ĉ����N�������B�����̃X�y�N�g�����牽�������邩�A�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɗL�p���A��͂͂ǂ̂悤�ɍs�����A�ɂ��Đ�������B |
�V |
���q�\����͎��K�P �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(����) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
��3��A��4��ŏK�����������Ɋ�Â��A�M�d�ʑ���i�s�f�j�A�����M���́i�c�sA�j�̊�{�I�ȑ�����@���K�����A����ꂽ�f�[�^�̉�͂��s���B�܂��A�M���͉ߒ��Ŏ������甭�������C�̂��l�r���́i�s�f�|�l�r�j�ɂē�����s���B |
�W |
���q�\����͎��K�Q�@ (�x��j |
��5��Ŋw�K�����j���C�����u�iNMR�j�̊�b�Ɋ�Â��A ���莎���̒����@��e�푪���@�����ۂɍs���܂��B�{�u�`�ł́A ����@��̑�����@����P�Ɋo���邾���łȂ��A ���u�̌����Ƒ���@��̌n�I�ɗ��������p�\�͂�{���܂��B�܂�, ���ۂɓ���ꂽ�X�y�N�g�������͂��s���\������̎�@���w�ԂƂƂ��ɁA ���������L�̍\�����j���C���X�y�N�g�����猈��ł��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B |
�X |
�����E���͂��̂P�@ (����J�j |
�U�������v���Y�}�����������́iICP-AES�j�́A���n�t���̌��f��ʂɍL���p�����Ă��܂��B����Ώی��f�������A��K�X�A�n���Q���A���f�A�_�f�Ȃǂ�������70��̌��f�̓����萫�E��ʂ��\�ŁA���o�\�Z�x��ppm�`ppb�i10�|3�`10�|6 g�^L�j���x���Ɣ�r�I�����x�ł��B�����ł́A���q�����̌����Ƒ��u�̍\���ɂ��ĊT������ƂƂ��ɁA���p����������Љ�܂��B |
10 |
�����E���͂��̂Q (�����j |
�����̕��͂ɂ����āA�ǂ̂悤�Ȑ������A�ǂ̂悤�ȏ�ԂŁA�ǂꂾ�����邩�͂���ꍇ�A�قƂ�ǂ����m���ł���B���̂悤�ȕ����̒萫�E��ʕ��͂ɂ́A�܂��A���͑O�ɖړI�������������鑽�����ƕ��������̂��ړI�����̕��͍s���B�{�u�`�ł́A�����̑��ݍ�p�𗘗p���ĕ�������N���}�g�@�̕��͌����A����щ��p������Љ��B |
11 |
�����E���́E�\����͂��̂P�k�b�|�l�r�^�l�r (�a���j |
�{�u�`�ł́A�������͂̊�{�ł��镪�q�ʂ𑪂鎿�ʕ��͖@�́A�ŐV�Ȋw�Z�p�̒��ł̈ʒu�Â��𗝉�����B����ɂ킽�鉞�p����̒��ł��A���ɁA�n�t�������t�̃N���}�g�O���t�iliquid chromatography�A�k�b�j�ɂ�莎������������Ƀ^���f�����ʕ���(tandem mass spectrometry�A MS/MS) �@�ɂČ��o����k�b�|�l�r/�l�r���u�𒆐S�Ƃ������͌����A����щ��p������T�ς���B |
12 |
�����`�ԕ��͂��̂P (�����j |
���݁A�ޗ���͂́A�傫�������āA���w���͂ɂ�镨�������͂Ə�Ԋώ@�ɂ��`�Ԋώ@�ɕʂ��B���̂����A�`�Ԋώ@�ł́A�������ɂ���͂��嗬�ł���B�{�u�`�ł́A�\�ʊώ@�p�̑�^���͋@��ł��鑖���d�q�������̌������牞�p�������B�܂��A���ۂ̃t�B�[���h�łǂ̂悤�ȉ�͂ʼn��p����Ă��邩�������A�����d�q�������̉�͕���ł̈ʒu�t����K�p�����Ƌ��ɁA�@��Ƃ��Ă̎g�p���@�����킹�ĉ������B |
13 |
�����`�ԕ��͎��K�P�@ (����j |
�u����^���d�q�����v�͏]���̂r�d�l�ł͂ł��Ȃ������ܐ������̐���{���x�̊ώ@�����Ɋȕւɂł��邽�߁A������H�i�A�@�ۂȂǗl�X�Ȏ����̔��\���̊ώ@�ɗ��p����Ă���B�{�u�`�ł́A�����������ώ@����Ƌ��ɁA�����Ɋ܂܂���`�q���A���A���^�C����`�q�������u��p���đ������A��͂���B |
14 |
�����`�ԕ��͎��K�Q�@ (�����j |
���œ_���[�U�[�������́A�זE���̓���̕��q���u���F�f��u���R�̂ŕW�����A���̋Ǎ݂��ώ@���邽�߂ɗp���܂��B�p�r�͌u���ώ@�@�Ɍ����܂����A���[�U�[�����Ƌ��œ_���w�n��p���邱�ƂŁA�œ_�� (XY����)�Ɛ[��(Z)�����̑S�Ă̕����ŕ���\�����߁A���w�������̕���\�̗��_�I���E�ɔ��镪��\���������A���܂�זE���x���ł̐����Ȋw�����ɂƂ��Ă͕K�{�̋@��ƂȂ��Ă��܂��B���̎��Ƃł́A�u���ώ@�@�̊�b�̐���������ۂ̎����ώ@�̃f���܂ōs���܂��B |
15 |
�܂Ƃ�
|
�܂Ƃ߂Ƃ��āA���^�����������Ȃ��A�{�u�`�œ������ʂ���������B |