
|
期待される効果 |
グローバル化社会の中で先進各国は、人材、国力を高めることの原動力としての機能が大学に存在するとの認識で戦略的な拠点と位置づけ、そこで行われる教育・人材育成に重大な関心を寄せるようになってきた。翻って我国においても、国際社会・情報化社会で活躍できる高度な社会人養成が大学に求められていると同時に、18歳人口の減少などにより多様な学生が大学へ入学してくるようになっている。このような世界情勢、社会的背景を受けて、地方の国立大学は、地域社会に貢献できる人材の養成が一層求められており、教育における効果を広く地域社会に提示していく必要がある。
|
| 本学ではこれまでも、多様な学生への進路選択支援に対応するため、様々なキャリア支援に取組んでいる。学生のキャリア開発に関する授業として、富山県に縁のある第一線で活躍する社会人を講師に招いて講義する「富大流人生設計講座」及び「インターンシップ」を正課授業として実施している。中でもインターンシップは、2000(平成12)年に県内の高等教育機関と経済諸団体で組織する富山県インターンシップ推進協議会が発足し、本学はその中心メンバーとして毎年度の実施計画に参画し、体験学生は2007(平成19)年度までに延べ1,000名を越えている。 |
 |
一方、このような地域社会に支えられ企業・団体などの協力のもとで行われている就業体験は、発達段階に応じた中等教育段階でも実施されている。すなわち、昨年度の教育再生会議でも事例報告された県内の全中学校が全国に先駆けて実施している「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」は、富山県の地域社会全体で若者を育成しようという土壌に根ざした中等教育段階でのキャリア教育の取組である。他県では受入企業・団体の確保が困難な状況の中で、富山県では地域の企業・団体との連携協力がうまく実施されている。
2006(平成18)年度には、このような中等教育段階での就業体験を経験してきた学生がインターンシップに参加するようになり、参加者増に繋がったことなどが地元新聞紙上に大きく掲載された。ところが、このような学校間で功を奏している取組は、成長・発達段階におけるそれぞれの役割を認識しながら実践されてはいるものの、相互に接続連携するまでには至っていない。本プログラムでは、新たなキャリア開発支援方策を検討するために昨年度に実施した卒業者進路追跡実態調査のデータを基に、地域社会に支えられた総合的な学校種間接続連携による組織体系を構築し、学生へのインターンシップの参加目的の明確化と達成効果を高めると同時に、『14歳の挑戦』からはじまる中等教育段階におけるキャリア教育との連携を目的としている。さらに、総合的学生支援体制の下にキャリア開発支援を軸とした学生へのエンロールメント・マネジメントの実践にも取り組む。
|
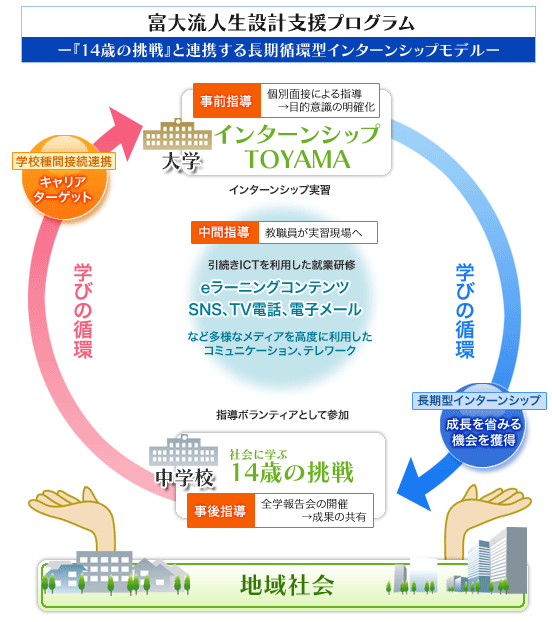 |
|
|
|