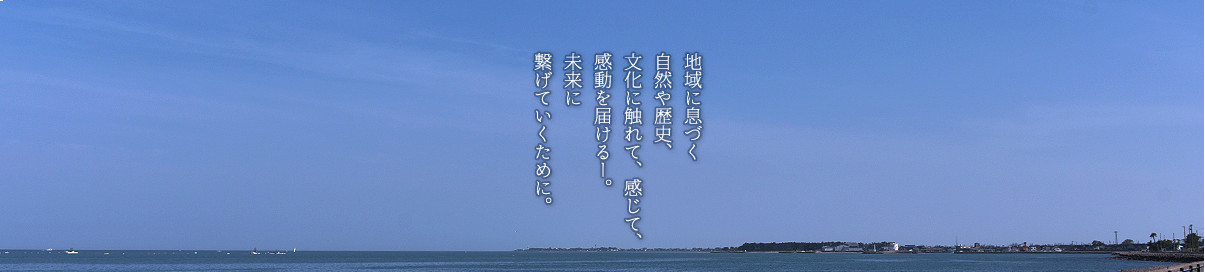現状と企画にあたり

魚津市は人口4万3千人を擁し,平成の市町村合併以前の県内において富山市,高岡市に次ぐ第3の中枢的な都市という位置づけにあります。市内には,水族館・埋没林博物館・歴史民俗博物館の3つの博物館があり,各館の特性を生かした展示・普及活動が行われています。 人口減少社会・少子高齢化時代となり,全国的に公共施設の統廃合が検討されるなか,博物館そのものの在り方が問われている一方,教育機関としての大学においては,その地域での役割が博物館同様,問われています。
富山大学は,「人材育成や課題解決で地域に貢献」に重点を置いた取組を展開することとしておりまた学生の教育のみならず,自治体と連携し,地域活性化の核となる社会人教育にも重点をおいています。大学のナレッジ(知恵・知識)を利用し,「地域のシンクタンク機能」をもつことで,富山大学は,「地域の拠点となる大学」を目指しており学生・社会人の教育・人材育成の過程や結果をさらに大学の学部教育の発展につなげていく傾向にあります。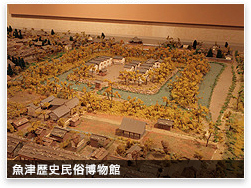 教育機能としての役割を担う博物館においても,大学と同様に地域連携が求められています。博物館の主要な責務に,資料の収集・保管,調査研究,普及啓発があげられ,地域の資料を取り扱い,その地域で活動を行う博物館において,その館が地域に求められる,必要とされる博物館となることは,当然といえます。その地域の活性化を担えるような博物館が求められていると考えています。これまでの博物館施設から,1歩踏み出し,模索しながらも変革している事例について,魚津市の博物館職員も,これらの取り組みを「知り,学び,考えて」いくことが必要と考えています。
教育機能としての役割を担う博物館においても,大学と同様に地域連携が求められています。博物館の主要な責務に,資料の収集・保管,調査研究,普及啓発があげられ,地域の資料を取り扱い,その地域で活動を行う博物館において,その館が地域に求められる,必要とされる博物館となることは,当然といえます。その地域の活性化を担えるような博物館が求められていると考えています。これまでの博物館施設から,1歩踏み出し,模索しながらも変革している事例について,魚津市の博物館職員も,これらの取り組みを「知り,学び,考えて」いくことが必要と考えています。
勉強会・報告会の目指すところ

魚津市内にある3博物館の連携のあり方,有効的な活用策について,各館の職員(学芸員)が自ら考え,行動できる人材の育成と職員の意識改革を図ります。併せて人口4万人規模の自治体が所有する3館の今後の方向性や将来像について,勉強会や報告会をとおして,「地域に必要とされる博物館」とはどのような姿なのか,共通認識を構築していきます。 ひとつは,地域連携(地域貢献),地域活性化についての方向性(ビジョン)の共有。 多様な団体が多様な連携を図りながら,活動する国内の先進事例を知ることで,自分たちの館におきかえるとどのようなことができるのか考えていく。 ふたつに,富山大学民間等共同研究員として「“魚津市全体をひとつの博物館”として捉えるエコミュージアム構想を3館の連携・活用策の柱とし,“地域活性化に寄与する博物館”を目指す」という,研究テーマについても,その方向性を示していきたいと考えています。