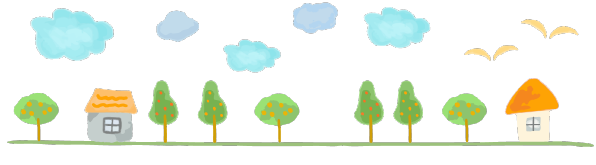双子の育児、「サポート」ではなく「当事者」である大切さ
vol. 4 荻原 寛人 様(芸術系総務・学務課主任(令和3年度当時))
育児休業を取得してよかったことは?
何よりも嬉しかったことは、子どもの成長を肌で感じられたことです。特に新生児期の成長の速さは驚く程早く、この短くも貴重な時間を家族で過ごしたことで、何事にも変え難い経験をすることができました。また、育児の不安や悩みを家族で共有しながら子どもに向き合うこともできました。夫婦で試行錯誤しながら、「何がダメだったのか、次はこうしてみよう」といった会話を積極的に交わすことによって、互いの精神的な負担を減らすことができたのではないかと思います。
育児休業中に大変だったことは?
多胎育児のため、特に授乳・オムツ替えが大変でした。双子といえども別々の人間ですから、授乳・オムツ替えのタイミングはどうしてもバラバラになり、手がとられる時間も長くなります。また、常にどちらかが泣いていたり、あるいは両方が泣いていたりで、気の休まる時間はあまりありませんでした。
日々の慌ただしさに加え、寝不足で疲労が溜まっていたため、子どもの対応が疎かにならないように常に意識する必要がありました。授乳時間やミルクの量、排便の有無等をノートに記録して夫婦間で情報共有し、こまめに確認しながら対応していました。
この時期は育児に専念するため、ネットショッピングや夕食宅配サービス等、家事の負担を減らすための方法を積極的に取り入れ、何とか日々の生活を送ることができていました。しかし、オムツ代やミルク代、その他育児用品にかかる費用に加え、これらのサービスを多用したことによる経済的負担も悩みの一つでした。
育児休業取得にあたっての周囲とのやりとり
生まれてくる我が子が双子だと分かった時点で、ハードな育児になることが予想されたため、妊娠初期の段階で育児休業の取得を希望していることを当時の上司に伝えました。また、異動時期とちょうど重なっていたため、当時の上司と異動先の上司の両方に相談をしたのですが、どちらの方からも「家族を優先に考えてほしい」とご返答いただきました。育児休業中の担当業務の調整等にもお力添えをいただき、本当に感謝しています。そして、休業中に私の担当業務に分担して取り組んでくださった同僚の方々にも同じ思いを伝えたいです。また、以前同じ部署で働いていた上司が、男性の事務職員として初めて育児休業を取得されていたことも、自身の選択の後押しになりました。制度があることは知っていましたが、実際に取得された方が身近にいたことで実感が湧きました。
復帰後、ご自身に起きた変化はありますか?
業務の効率をこれまで以上に重視するようになりました。仕事と家庭との両立を図るためには、子どもの生活リズムに合わせて仕事に費やす時間を調整していく必要がありました。結果として、勤務時間内に仕事を終わらせるにはどうしたら良いかということを最優先に考えるようになり、これまでの仕事への取り組み方を見直す良い機会となりました。
また、業務以外の面では、子育ての先輩である大学の先生方や同僚の方から、子どもの様子について折に触れて声を掛けていただいたり、お下がりの育児用品をいただいたりすることが増え、周囲からの温かい心遣いに大変嬉しく思っております。
職場のパパたちや社会に対してメッセージをお願いします。
もし、育児休業を取得すべきかどうか迷っている場合は、是非前向きに検討していただきたいです。短い期間であっても、そこで経験した苦労や喜びは家族の財産になります。子育てを「手伝う」のではなく、「当事者」となることで、今後も続いていく子育ての基礎をしっかりと築くことができます。育児休業が明けた今でも、常に主体性をもって子どもと接するよう意識しています。
今回、育児休業取得者に対するインタビュー記事掲載という形で、自身の経験を伝える機会を与えていただき感謝しています。子どもは、私達にとってかけがえのない宝物であるとともに、未来の社会を築いていくという重要な役割を担う存在だと考えています。男性の育児休業取得の普及により、一人でも多くの人が子育てに関心をもち、家族だけでなく地域全体で子ども達の健やかな成長を見守り、後押しできるような社会になることを願っています。この記事が僅かながらその一端を担うことができたら幸いです。