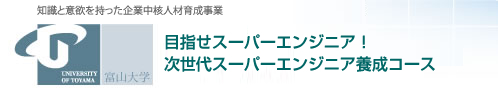ホーム > 受講生の皆様へ > 講義内容(シラバス)> エネルギー工学特論
講義内容(シラバス)2011
エネルギー工学特論
授業科目名 |
エネルギー工学特論 |
||
担当教員(所属) |
《富山大学大学院理工学研究部(工学系)》 |
||
授業科目区分 |
|
授業種別 |
|
時間割コード |
|
対象所属 |
|
開講日程 |
10月−12月 木曜日6,7限 |
対象学年 |
|
単位数 |
2 |
||
連絡先(研究室、電話番号、電子メール等) |
升方勝己 masugata@eng.u-toyama.ac.jp |
オフィスアワー(自由質問時間) |
|
授業のねらいとカリキュラム上の位置付け(一般学習目標) |
教育目標 |
(工学部JABEE区分用) |
|
エネルギー・環境・経済の3者調和を図ることが人類存亡の鍵となる。本講義では、電気・熱エネルギーをいかに有効に利用するかをテーマとし、その基礎から最先端技術までを講義する。各種電気機器の特性を理解し、省エネ機器の開発の方向性と効率の良い利用、電力変換・輸送におけるロスの低減についてその基礎と最新技術を紹介する。また、熱力学、伝熱工学に基づき、自動車エンジン等の熱機関や熱利用機器の特性の基礎と最新技術を紹介する。 |
|||
達成目標 |
|||
電気回路、熱力学の基礎物理を理解すると共に、半導体電力変換技術、ヒートポンプ技術などを、その基礎から近年の開発動向まで理解する。 |
|||
授業計画(授業の形式、スケジュール等) |
||
第1回 |
エネルギー問題(電力発生の概要、エネルギー資源、環境・経済との調和) |
升方 |
第2回 |
電気回路の基礎(電気の種類,電流・電圧・電力,位相と力率) |
大路 |
第3回 |
電気機器の種類と特性,効率的運用(回転機) |
大路 |
第4回 |
電気エネルギーの効率的利用 |
升方 |
第5回 |
半導体電力変換装置・パワーエレクトロニクスの基礎 |
作井 |
第6回 |
半導体電力変換装置・パワーエレクトロニクスの基礎 |
作井 |
第7回 |
パワエレ先端技術 |
松本 |
第8回 |
パワエレ先端技術 |
松本 |
第9回 |
熱力学の基礎 |
手崎 |
第10回 |
燃焼現象と燃焼技術 |
手崎 |
第11回 |
内燃機関の基礎と動向 |
手崎 |
第12回 |
伝熱工学の基礎 |
平澤 |
第13回 |
エネルギー有効利用のための伝熱工学の応用 |
平澤 |
第14回 |
熱機関最新技術 |
高林 |
第15回 |
熱機関最新技術 |
高林 |
キーワード |
電気エネルギー、省エネルギー技術、パワーエレクトロニクス、電気機器、熱力学、ヒートポンプ |
履修上の注意 |
|
教科書・参考書等 |
|
成績評価の方法 |
出席及びレポート |
関連科目 |
|
備考 |
|
エネルギー工学特論:授業計画
回 |
主題と位置付け |
学習方法と内容(講義概要) |
1 |
エネルギー問題 (升方) |
経済発展、環境調和の観点からエネルギー利用の現状と問題点、将来展望について概説する。水力・火力・原子力等の現状の発電技術の概要と問題点に加え、新たな電力発生技術について概説する。 |
2 |
電気回路の基礎(電気の種類,電流・電圧・電力,位相と力率) (大路) |
直流と交流(単相・三相),過渡現象,歪み波交流について概説する。回路中の電流・電圧・電力や位相・力率(交流)などの諸状態を学習することで,電気機器の運転に必要な電気理論を修得する。 |
3 |
電気機器の種類と特性,効率的運用(回転機) (大路) |
電気機器の基礎として回転機(直流機,交流機)について概説する。回転機の効率的運用として,新しい構造や特徴を持つ回転機について紹介する。 |
4 |
電気エネルギーの効率的利用 (升方) |
電気エネルギーの効率的利用の観点から、電力損失、力率、電圧変動、瞬時停電、高調波、等の影響と対策について説明する。また、電熱・照明機器の特性を示し、それらの効率的運用について概説する。 |
5 |
半導体電力変換装置・パワーエレクトロニクスの基礎 (作井) |
まず、電力変換装置の構成要素として用いられる電力用半導体素子の種類、構造、特性などを説明する。次に、電力用半導体素子を用いて電力変換を行う基本的な回路である整流器、直流チョッパ、インバータなどの回路構成、動作原理などについて説明する。 |
6 |
半導体電力変換装置・パワーエレクトロニクスの基礎 (作井) |
交流を直流に変換する整流回路は高調波を発生し、力率の低下や各種の障害の原因となる。そこで、整流回路から発生する高調波を低減する方法について説明する。また、直流をを交流に変換する装置であり、省エネに大いに貢献しているインバータの出力電圧の波形を改善する方法についても説明する。 |
7 |
パワエレ先端技術 (松本) |
電力変換装置で用いられる最新の電力用半導体素子の構造、特性などについて解説する。また、新デバイスを応用した機器を紹介し、その導入効果などについて解説する。さらに、今後の電力用半導体素子の技術動向についても解説する。 |
8 |
パワエレ先端技術 (松本) |
パワーエレクトロニクス技術を誘導機や同期機などのモータ制御分野、直流や交流電源の電源分野、直流送電などの電力分野、太陽光発電や風力発電などの新エネルギー分野に応用した事例を紹介し、その応用技術などについて解説する。 |
9 |
熱力学の基礎 (手崎) |
熱力学の第一・第二法則、エントロピー、サイクルなどの基本的考え方について、それらの理解のつぼを解説する。 |
10 |
燃焼現象と燃焼技術 (手崎) |
熱機関の多くは、その熱源に燃焼を用いている。燃焼の基礎として、燃焼形態・火炎伝播・着火などを解説し、その特性が燃焼器の構造などにどう活かされているか、といった技術面を論じる。 |
11 |
内燃機関の基礎と動向 (手崎) |
4サイクルエンジンの基礎構造と動作、ガソリンエンジン(火花点火)とディーゼルエンジンの特性、エンジン性能向上のための最新技術、新型燃焼方式などについて解説する。 |
12 |
伝熱工学の基礎 (平澤) |
熱エネルギーの移動形態あるいはその移動のプロセスを物理的に理解し、実際に経験する現象を、伝熱工学を適用して理解する能力を修得する。 |
13 |
エネルギー有効利用のための伝熱工学の応用 (平澤) |
エネルギー有効利用のための熱源、熱エネルギー利用機器、断熱手法等を概説する。さらに、最近の利用技術とその原理についても解説する。 |
14 |
熱機関最新技術 (高林) |
ハイブリッドエンジンの燃費はどのように達成されたかなど、実用化されている省燃費・CO2排出削減の最新技術とその動向を紹介する予定である。 |
15 |
熱機関最新技術 (高林) |
ハイブリッドエンジンの燃費はどのように達成されたかなど、実用化されている省燃費・CO2排出削減の最新技術とその動向を紹介する予定である。 |