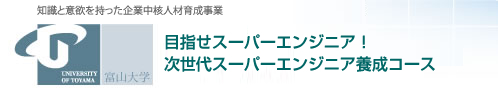ホーム > 受講生の皆様へ > 講義内容(シラバス)> マテリアルエンジニアリング特論
講義内容(シラバス)2011
マテリアルエンジニアリング特論
授業科目名 |
マテリアルエンジニアリング特論 |
||
担当教員(所属) |
《富山大学大学院理工学研究部(工学系)》 |
||
授業科目区分 |
専門教育科目 授業科目 |
授業種別 |
講義 |
時間割コード |
|
対象所属 |
理工学教育部(修士課程) |
開講日程 |
8月-10月 土曜日1・2限 |
対象学年 |
1年 |
単位数 |
2 |
||
連絡先(研究室、電話番号、電子メール等) |
寺山清志(076-445-6828、 |
オフィスアワー(自由質問時間) |
毎回の講義終了後、30分から1時間。E-mailによる質問も可。 |
授業のねらいとカリキュラム上の位置付け(一般学習目標) |
|||
本授業では、材料の基礎知識を学んだ後、金属からセラミックス,新素材,先進材料,超伝導材料に及ぶ幅広い実用材料について、豊富な実例をもとにわかりやすく基礎から製造,応用までの一貫した知識を興味を持って確実に身につけるように工夫されている。したがって、あらゆる初学者だけでなく既に実務についている産業界の研究者や技術者にとっても最新の情報が理解でき、職場において遭遇する材料に関する様々な問題に処する際の有力な指針となるよう配慮されている。 |
|||
達成目標 |
|||
1)材料の製造法が理解できる。 |
|||
授業計画(授業の形式、スケジュール等) |
||
第1回 |
講義概説、材料の基礎 |
古井 |
第2回 |
塑性変形の基礎、材料試験法 |
池野 |
第3回 |
金属材料の破壊と解析 |
長柄 |
第4回 |
アルミニウムの鋳造 |
古井 |
第5回 |
アルミニウムの熱処理・相変態 |
松田 |
第6回 |
マグネシウムの特性 |
川畑 |
第7回 |
マグネシウムのリサイクル |
井上 |
第8回 |
熱分析の基礎と応用 |
寺山 |
第9回 |
熱分析測定法の実際 |
橋爪 |
第10回 |
材料の腐食・防食の基礎と応用 |
砂田 |
第11回 |
超伝導材料の最先端 |
森 |
第12回 |
磁性材料の最先端 |
西村 |
第13回 |
薄膜材料の製造法と応用(気相法,機械的性質) |
野瀬 |
第14回 |
薄膜材料の製造法と応用(気相法,機械的性質) |
野瀬 |
第15回 |
セラミックス材料の基礎と応用 |
佐伯 |
キーワード |
材料、製造、評価、最先端材料 |
履修上の注意 |
物理・化学の基礎知識(大学卒業程度)を必要とする。 |
教科書・参考書等 |
授業で指定する。 |
成績評価の方法 |
出席とレポートを総合して成績評価する。15回の講義中8回は出席すること。 |
関連科目 |
物理・化学・数学・材料系(工学部)の授業科目 |
オープン・クラス |
受入不可 |
単位互換 |
受入不可 |
備考 |
|
マテリアルエンジニアリング特論:授業計画
回 |
主題と位置付け |
学習方法と内容(講義概要) |
1 |
講義概説,材料の基礎 (古井) |
講義全体の概説と授業計画の説明。石器,青銅器,鉄器などと各時代の冠をなす材料全般に関する背景、さらには科学技術の発展を通して人類の文明を支えている材料の基礎を学ぶ。 |
2 |
塑性変形の基礎,材料試験法 (池野) |
金属材料の塑性変形について、転位論を元に解説する。さらに材料の各種強度試験、ナノ組織解析法などについて紹介する。 |
3 |
金属材料の破壊と解析 (長柄) |
金属材料の延性,脆性破壊,疲労破壊のメカニズムやそれらの解析方法を紹介する。 |
4 |
アルミニウムの鋳造 (古井) |
アルミニウム合金の連続鋳造の発展は、鋳塊の表面性状の改善がその駆動力となっている。現行のDC鋳造法をベースに、HOT-TOP鋳造法や電磁鋳造法について、原理・仕組みや製造される鋳塊の特性などについて紹介する。 |
5 |
アルミニウムの熱処理・相変態 (松田) |
新旧のアルミニウム合金を紹介し、とくにナノ組織制御を中心とした相変態について解説する。 |
6 |
マグネシウムの特性 (川畑) |
実用金属で最も軽いマグネシウム合金について、その工業的背景と耐熱性の向上に関する最近のナノ研究動向について紹介する。 |
7 |
マグネシウムのリサイクル (井上) |
実用金属中で最も軽いマグネシウム合金のリサイクルの現状とその研究動向について紹介する。 |
8 |
熱分析の基礎と応用 (寺山) |
我が国が世界で最初に開発した熱天秤の技法を中心に、各種熱分析法の基礎的原理,解析法を理解し、耐熱試験,熱劣化,原材料の検査・品質管理等への応用について知る。 |
9 |
熱分析測定法の実際 (橋爪) |
実験室,研究室における実際の熱分析の測定、その手段と分析・解析について紹介する。実際の注意点や、手法,装置設定等についても、具体例を混ぜながら解説する。 |
10 |
材料の腐食・防食の基礎と応用Ⅱ (砂田) |
材料の耐食性を評価する方法として最近の電気化学的測定方法を解説し,各種方法で作製された材料の具体的な事例を紹介する。 |
11 |
超伝導材料の最先端 (森) |
超伝導材料の開発の歴史を学び、金属超伝導体と酸化物超伝導体の基礎的特性を理解する。最新の超伝導材料における開発の現状を学ぶ。 |
12 |
磁性材料の最先端 (西村) |
フェライト磁石,希土類磁石の開発の歴史を学び、希土類磁石の基礎的物性と特性を理解する。最新の希土類磁石の開発の現状と市場の動向を学ぶ。 |
13 |
薄膜材料の製造法と応用 (野瀬) |
PVD法を中心として薄膜材料の形成法とその原理について説明する。薄膜材料の中で硬質薄膜をとりあげ,その特性と用途について概説する。 |
14 |
薄膜材料の製造法と応用 (野瀬) |
PVD法を中心として薄膜材料の形成法とその原理について説明する。薄膜材料の中で硬質薄膜をとりあげ,その特性と用途について概説する。 |
15 |
セラミックス材料の基礎と応用 (佐伯) まとめ |
伝統的で基礎的な固相反応・焼結を紹介すると同時に応用として機能性セラミックス材料において液相が関与する製造法や、反応例について紹介する。 |