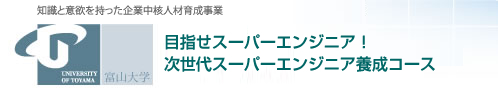�z�[�� �� ��u���̊F�l�� �� �u�`���e(�V���o�X)�� �@�B�ޗ��H�w���_�T�i��b�j
�u�`���e�i�V���o�X�j2013
�@�B�ޗ��H�w���_�T�i��b�j
���ƉȖږ� |
�@�B�ޗ��H�w���_�T |
||
�Ȗ� |
�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�n�j |
||
�敪 |
�X�[�p�[�G���W�j�A�{���R�[�X |
���Ǝ�� |
��w�@�C�m�ے����H���� |
�Ώۏ��� |
���H�w���畔 |
||
�J�u���� |
5���|7���@�y�j��1�A2�� |
�Ώۊw�N |
�Љ�l�Z�p�ҁA��w�@�� |
�P�ʐ� |
�Q |
||
�A����(�������A�d�b�ԍ��A�d�q���[����) |
���F�K�ׁiTEL076-445-6776�j�A |
�I�t�B�X�A���[(���R���⎞��) |
|
���Ƃ̂˂炢�ƃJ���L��������̈ʒu�t�� |
|||
�����𒆐S�Ƃ����ޗ��̌����\������ѕ����̊�b�m�����w�сA���m�Â���̂��߂̗l�X�ȉ��H���@�E�������@�̌����Ƃ��̎d�オ���Ԃւ̉e���ɂ��ė�����[�߂�B |
|||
�B���ڕW |
|||
�E�����ޗ��̑g�D�A�����̊�b�������ł��� |
|||
�u�t�̏Љ� |
||
��1�� |
���V�@�ǒj�� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
�����גጸ�̂��߂̃G�l���M�[���p�̊�b�����A���M�~�M�̌����A�����ޗ��̔M�����Ɋւ��錤���ɏ]�� |
||
��2�� |
���V�@�ǒj�� |
�i����j |
��3�� |
�ː�@���� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�y�����j |
�f�`�ނ̍ޗ����������B���Ԋ�Ɓi�������[�J�[�j�ł̃A���~�j�E������у}�O�l�V�E�������Ɋւ���25�N�Ԃ̌����J�����o�āA��N��茻�E�ɒ��C�B��Ɍy�����ޗ��̋Ìőg�D���䓙�ɂ�鍂�@�\�E�����x������������ |
||
��4�� |
���J�@���u�� |
�i�x�R��w�n��A�g���i�@�\�Y�w�A�g����@�y�����j |
�����ޗ��w�A�������ޗ��w�iNi ������ANb ����AW-Mo ������j�A�����_���E�������H�H�w�A�����Z�̕����w |
||
��5�� |
�r��@�i�� |
�i�x�R��w���_�����A�� �k���E�Ɣ\�͊J����w�Z�Z���j |
��S�����ޗ��̃~�N���g�D�Ɋ�Â��ޗ��̍\����͂Ƌ@�\�]���A�V�K�ޗ��̊J���Ɋւ��錤���ɏ]�� |
||
��6�� |
���ҁ@���v�� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
�A���~�j�E����������у}�O�l�V�E�������̔M�ԉ��o�����H�A��������f���H |
||
��7�� |
��c�@�N�v�� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�y�����j |
�}�O�l�V�E�������̌ʼn����`�A�����g�D�\���̔�������уi�m�����\���̍쐻�Ɋւ��錤���ɏ]�� |
||
��8�� |
���R�@�\�ꎁ |
�i�x�R�������w�Z�@�@�B�V�X�e���H�w�ȁ@�y�����j |
��������i���J�j�J���A���C���O�A�����ޗ��̍����˂���iHPT�j���H�ɂ��ʼn����`�j |
||
��9�� |
�R�c�@�Ύ� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�y�����j |
�e�퍇���̔�퐫�]���A�@�B���H�p�H��̐v |
||
��10�� |
�Ė��@�q�Ǝ� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
�n�ږ���w�A���C���a�ڍ� |
||
��11�� |
�����@���� |
�i(��)�s��z�@�J���{���@���Ɖ����i���`�[�t�j |
��12�� |
���c�@���� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
�d�C���w��p�������H���J�j�Y���̉� |
||
��13�� |
�����@�~�� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
�����ޗ���@�\���Z���~�b�N�X�̐����v���Z�X�̊J���Ɖ�͂𒆐S�Ƃ����ޗ��H�w�AX��������͊w�̋��猤�� |
||
��14�� |
���c�@���� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
�d�q��������p�����g�D�ώ@�Ɋ�Â��ޗ��̍\����͂Ƌ@�\�]���A�V�K�ޗ��̊J���Ɋւ��錤���ɏ]�� |
||
��15�� |
���F�@�K�� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
������J�A�g���C�{���W�[�A�@�B���i�̌��S���]���Ɋւ��錤���ɏ]�� |
||
�L�[���[�h |
�ޗ��A���H�A�����A�]�� |
���C��̒��� |
|
���ȏ��E�Q�l���� |
���ƂŔz�z���鎑�� |
���ѕ]���̕��@ |
�o�Ȃƃ��|�[�g |
�֘A�Ȗ� |
|
���l |
|
�@�B�ޗ��H�w���_�T�i��b�j�F���ƌv��i�u�`���e�A�J�×\����A�u�t�j
�� |
���ƈʒu�t�� |
�w�K���@�Ɠ��e |
�P |
�`�M �i���V�j |
�M�G�l���M�[�̈ړ����ۂ͈ꌩ���ĕ��G�ł��邪�A�M�`���A�Η��`�M�A�ӂ��˓`�M�A���ω��`�M�Ȃǂ̓`�M���ۂ������I�ɐ��������ʂł���B�����̔M�G�l���M�[�ړ��`�Ԃɂ��Ċ�b���������A���ۂ̌��ۂɌ��т���\�͂�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B |
�Q |
�f�M�ޗ��ƒf�M�Z�p �i���V�j |
�ȃG�l���M�[�邢�͔M�G�l���M�[�L�����p�̂��߂ɂ́A�����\�̒f�M�ނ̗��p�����Ɍ��ʓI�ł���B�������A�f�M�ޓ����̓`�M�@�\��M�ړ����ۂ͎�X�̕������ۂ����߁A���ɕ��G�ł���B�`�M�̊�b�����𗝉�������ŁA���ۂ̒f�M�ޓ����̕������ۂƓ`�M�@�\�Ƃ̊ւ��𗝉�����ƂƂ��ɁA�`�M���ۂ̐������@�Ȃǎ��H�I�Ȓm���̉��p�͂�g�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B |
�R |
�����E�Ì� �i�ː�j |
�����Ƃ́A�n�Z�������������^�ɗ������Ìł����邱�Ƃɂ��ړI�Ƃ��镔�i�`�����@�ł���A�Y�����H�Ȃ�тɕ�������@�ȂǂƋ��ɋ������i�̎�Ȑ����@�̈�Ƃ����B�����ł́A���p�����@�̎�ނƓ����ɂ��Ēm��A�����Ŋe�����& �����̋Ìŋ����Ƃ����̎����i�����ւ̉e���ɂ��ču�`����B |
�S |
�S�|�ޗ� �i���J�j |
�S�|�ޗ��͋ɓ�ނ��獂���x�ށA�ቷ�ނ��獂���ށA�\���ނ���@�\���ޗ��܂ŗl�X�ȕ���ōL�͈͂ɗ��p����Ă���B����͓S�̎����ݓI�Ȑ����ɉ����A�Z����₤�l�X�ȋZ�p�̊J���ɂ��Ƃ��낪�傫���B�{�u�`�ł͗p�r�ʂɍ|�ނ̓����������Ƌ��ɁA�ߔN�b��̍Ő�[����ŗ��p����Ă���|�ނ̊J���Z�p�ɂ��Ă��Љ��B |
�T |
��S���� �i�r��j |
�����̒�`�̓�����l����B�c��Ȕ�S�ޗ��̓��A��ƂȂ錳�f��I�����Ĉ�ʓI�������q�ׂ�B����ɁA��������ޗ���I�����A���قȌ��ۂ��������B |
�U |
�����ޗ��̕ό`�ƑY�� �i���ҁj |
������b���ȂǗl�X�ȑY�����H�ɂ����āA�ޗ��̕ό`��͂���H�@�B�̔\�͐ݒ�ɍۂ��ĕK�v�ƂȂ�Y���͊w�̊�b��������A�A���~�j�E�������̉��o�����H�Ȃǂ̎��ۂ̑Y�����H�̋�̗�������Ȃ���A���̉��H�Z�p�̓����ƈʒu�t�����d�_�I�ɍu�`����B |
�V |
���^���H�̂��߂̋��^�Z�p �i��c�j |
���^���H�̂��߂̋��^�ޗ��̓����ɂ��ĉ������ƂƂ��ɁA���^�`��̕K�v������������Ȃ���`��v�ɂ��ču�`����B�܂��A�����݁E���o���E�ˏo���^�̂��߂̐��^�Z�p�̓����ƍŐV�����ɂ��Ă��u�`����B |
�W |
�� �i���R�j |
�����ޗ��́A�g�p�ړI�����ϕi��H�i���ꕔ�̋@�\���ޗ��������ď��]�̌`��Ɉ��k�E���`���ėp������B�{�u�`�ł́A�������q���͂��߂Ƃ��镲���̐����Z�p�A�����̍����A��������я[�U���@�A�ʼn����`�i���k���`�A�ˏo���`�j�ׂ̈̐��`�Z�p�A���`���������̌��q�̊g�U���ۂ𗘗p�����Č����_�ƕ��@�A�Ȃ�тɏČ��ɂ��ʼn����`�����Č��̂̕]�����@�ɂ��ču�`���s���B |
�X |
�؍������ �i�R�c�j |
���؍���ɂ��āA�肭���̐����@�\�Ɗe��̗p����������ƂƂ��ɁA��퐫��]������؍��R�A�d�グ�ʑe���A�H������A�肭���̏������ɂ��Đ�������B�܂��A�������H�Ɋւ����b�m���Ƃ��ēu���A�����܂⌤���z�Ȃǂɂ��ĉ�����A�e��H��ޗ��E�u�ޗ��̓����Ƃ��̖��Ջ@�\�ɂ��ĉ������B |
10 |
�ڍ� �i�Ė��j |
�n�ڥ�ڍ��Z�p�̊�b�w���i��Ƃ��ėn�ږ���w�j��������A�A���~�j�E���̐�[�ڍ��@�ł��門�C���a�ڍ��iFSW�j�̌����Ȃ�тɓK�p��ɂ��ďڏq����B |
11 |
�\�ʏ��� �i�����j |
��\�I�ȕ\�ʏ����̕��@�Ƃ��̓�����������A�H��̗�𒆐S�ɕ��������@�̓K�p����������B����ɐV����ւ̋Z�p�W�J�̎���ƍŋ߂̕\�ʏ����ɑ���j�[�Y���Љ��B |
12 |
���H�E�h�H �i���c�j |
�ޗ��̑ϐH����]��������@�Ƃ��čŋ߂̓d�C���w�I���@���������B���ɋȐ��������e�p�����[�^�[�̈Ӗ�����ѓ�����������A�e����@�ō쐻���ꂽ�ޗ��̋�̓I�Ȏ�����Љ��B |
13 |
�ޗ��̌����\�� �i�����j |
�ޗ��H�w�̊�b�ł�����������̊�{�I�\������A�\�L�@�A�Ώ̊W�ɂ��ču�`����B�܂��A���p�Ƃ��Č����̕s���S���≻�����ɂ����錋���̊�{�\���╨���̍\���ω��i���]�ځA���`�j�̗�ɂ��Ă���������B |
14 |
���t��Ԑ}�Ƒ��ϑԁE�M���� �i���c�j |
�A���~�j�E�������𒆐S�ɁA�����ޗ��̔M�����ɔ����ő��\�ő��ϑԂɂ��āA�}�N���A�~�N�������ăi�m�̊ϓ_�ł��̎w�������ƍd����������x���A�@�B�I�����Ƃ̊W�ɂ��ďq�ׂ�B |
15 |
�@�B�ޗ��n�i���Ǘ� �i���F�j |
���m�Â���ɂ�����i���Ǘ��ɂ��āA���̍l�����Ɩ������菇��������A��ʓI�]����@�Ƃ��Ă̓��v��͂ɂ��ču�`����B�܂��A�����v��@���ɋ����ĕ��U���͂ɂ����������ƐM�����̕]����@���u�`����B |