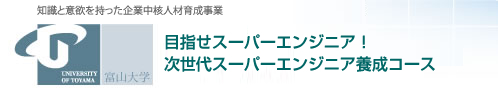�z�[�� �� ��u���̊F�l�� �� �u�`���e(�V���o�X)�� �@�B�ޗ��H�w���_�U�i���ۂƉ��p�j
�u�`���e�i�V���o�X�j2013
�@�B�ޗ��H�w���_�U�i���ۂƉ��p�j
���ƉȖږ� |
�@�B�ޗ��H�w���_�U |
||
�Ȗ� |
�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�n�j |
||
�敪 |
�X�[�p�[�G���W�j�A�{���R�[�X |
���Ǝ�� |
��w�@�C�m�ے����H���� |
�Ώۏ��� |
���H�w���畔 |
||
�J�u���� |
7���|9���@�y�j��1�A2�� |
�Ώۊw�N |
�Љ�l�Z�p�ҁA��w�@�� |
�P�ʐ� |
�Q |
||
�A����(�������A�d�b�ԍ��A�d�q���[����) |
���F�K�ׁiTEL076-445-6776�j�A |
�I�t�B�X�A���[(���R���⎞��) |
|
���Ƃ̂˂炢�ƃJ���L��������̈ʒu�t�� |
|||
�e���[�ޗ��̓����Ǝ���̉������ɁA���̊�b���琻���E���p�܂ł̒m�����K������B�܂��A���i�̐���]���A�g�p���̐M�����]���A�V�X�e���̐v�E�g���ĂȂǎ��p�Ɋ֘A�[���l�X�ȍu�`���s���A���L���E��Ɩ��ɖ𗧂悤�z������Ă���B |
|||
�B���ڕW |
|||
�E�e���[�ޗ��̌������ł��� |
|||
�u�t�̏Љ� |
||
��1�� |
���܁@���� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
�@�\����H�w |
||
��2�� |
�����@���F�� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
���������ޗ�����ђ��d���ޗ��̕������� |
||
��3�� |
���A�@���F�� |
�i�x�R�������w�Z�@�����Ȋw�H�w�ȁ@�����j |
�����q�ޗ������A���ɔ������������q�ޗ��̃l�b�L���O������͂���уv���X�`�b�N���T�C�N�� |
||
��4�� |
���c�@�F�Y�� |
�i�x�R�������w�Z�@�@�B�V�X�e���H�w�ȁ@�y�����j |
�����ޗ��H�w�A�ޗ��͊w�B��ɑ@�ۋ����v���X�`�b�N�iFRP�j�̊E�ʂɊւ��錤���A�_�Ɣp������L�����p�������ɗD���������ޗ��̊J�� |
||
��5�� |
�쐣�@���Ǝ� |
�i�x�R��w�|�p�����w�� �����j |
�����ޗ��H�w�B��Ƃ��ăX�p�b�^�����O�Z�p�̊J���Ƃ����p�����d���ی얌����ы@�\�����̌����ɏ]�� |
||
��6�� |
������H�@���� |
|
��7�� |
�c��@������ |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�y�����j |
���[�U�[����ь����p�v���A�f�W�^���摜�v���Ɋւ��錤�� |
||
��8�� |
���F�@�K�� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
������J�A�g���C�{���W�[�A�@�B���i�̌��S���]���Ɋւ��錤�� |
||
��9�� |
���@���� |
�i�x�R�������w�Z�@�@�B�V�X�e���H�w�ȁ@�����j |
�y�����ޗ�����Ƃ��A�}�O�l�V�E���A�A���~�j�E���̃��T�C�N����������Ɋւ��錤�� |
||
��10�� |
�����@�B�ꎁ |
�i�x�R��w�|�p�����w�� �y�����j |
�����ޗ��H�w�A�����ޗ����H�w����ѕ������Ȋw |
||
��11�� |
�O���@�B�� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
�����g�T����@�Ɖf�����Z�p�A�����g�`���̉����Ɖ�͋Z�p�A����`�����g�v���Ɋւ��錤�� |
||
��12�� |
�}��@�F�ꎁ |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�y�����j |
���`���ޗ��̋@�B�I�����Ƌ��x�]���Ɋւ��錤�� |
||
��13�� |
�\���v�@���� |
|
��14�� |
�ؑ��@�O�V�� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�����j |
�@�B�U���Ɋւ���v���E��́E�]���Ɋւ��錤�� |
||
��15�� |
���@���� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�j�y�����j |
�Q�̃��{�b�g�ɂ������V�X�e���̍\�z�A�摜������p���������g���ĂɊւ��錤�� |
||
�L�[���[�h |
��[�ޗ��A����]���A��j���A��J���x�A���S�v�A�U����� |
���C��̒��� |
|
���ȏ��E�Q�l���� |
���ƂŔz�z���鎑�� |
���ѕ]���̕��@ |
�o�Ȃƃ��|�[�g |
�֘A�Ȗ� |
|
���l |
|
�@�B�ޗ��H�w���_�U�i���ۂƉ��p�j: ���ƌv��i�u�`���e�A�J�×\����A�u�t�j
�� |
���ƈʒu�t�� |
�w�K���@�Ɠ��e |
�P |
�Z���~�b�N�X �i���܁j |
�Z���~�b�N�X�ޗ��̊T���ɂ��ďq�ׂ�B�Ñ�̃Z���~�b�N�X���i����A�Ő�[�Ɏ���Z���~�b�N�X�ޗ��ɂ��āA���̗��j�͉��[���A�������̃Z���~�b�N�X���i�ɂ��ĉ�����A�Z���~�b�N�X�̏������A�������@�A�@�\���ɂ��Ă����y����B |
�Q |
�����ޗ� �i�����j |
�n�C�u���b�h�J�[�ɗ��p����Ă��鋭�͎���d���U���ɂ��[�d�V�X�e���Ɋ֘A����ŐV������Ɍ����Ɖ��p�ɂ��Ď����̊�{���u�`����B |
�R |
�����ޗ� �i���A�j |
�H�ƍޗ��Ƃ��Ďg�p����Ă���e�퍂���q�ޗ��i�M�Y�������A�M�d���������A�@�ۍޗ��A�S���E�G���X�g�}�[���j�̊�{�I�Ȑ����ɂ��ĉ�����A���̗p�r�A���H���@�Ȃ�тɉ��H�����ɂ��ĊT������B |
�S |
�����ޗ� �i���c�j |
�{�u�`�ł́A�����ޗ��̋@�B�I�����A�]�����@����ѐv��@�Ɋւ����b�����ɂ��ču�`����B�܂��A�����Ԃ�q��@���̗A���@��̌y�ʉ��Z�p�ƕ����ޗ��̊ւ��ɂ��ču�`����B����ɁA�V�R�f�ނ�p�������ɗD���������ޗ��̍ŋ߂̊J�������ɂ��ču�`����B |
�T |
�����ޗ� �i�쐣�j |
�����ޗ��̔��\���͂��̋@�B�I���������肷��傫�ȗv���ł���B���̂��߁A�{�u�ł́A�܂�PVD ���̌`���@�\�ɂ��ĉ������B���̏�Ő��������Ɣ��\���Ƃ̊W�Ȃ�тɔ��\���Ƌ@�B�I�����Ƃ̊W�ɂ��Đ�������B����ɁA�����̋@�B�I��������є��\�����̊e��]���Z�p�ɂ��ĉ������ƂƂ��ɁA�e��d���ی얌��i�m�R���|�W�b�g���Ȃǂ̉��p����Љ��B |
�U |
������H �i����j |
���d���H�A�d�����H�A���[�U�[���H�A�d�q�r�[�����H�ȂǁA�l�X�ȓ�����H�̎�ނƂ����̉��H�@�̓����ɂ��ĊT������B |
�V |
���H�\�ʂ̐���]�� �i�c��j |
���w�I��@�ɂ���ڐG�ʼn��H�ʂ̌`��A�ʒu����ѐ���𑪒肷����@�Ƃ��̕]���Z�p���u�`����B�܂��A���w�I��b���_�i���B��܁B�Ό����j�ƌ��w���i�̎g�����A����̎�����������B�����āA�摜�����i�E�G�[�u���b�g�A�摜���ցA�ʑ��V�t�g�j�𒆐S�Ƃ����v���Ƃ��̑���̎�����������B |
�W |
���C�E���� �i���F�j |
2 ���̂̓��I�ڐG���Ƃ��āA�����d�Ɩ��C�͂ɂ���Đ����鉞�͏�̊�b��������A����ڐG�Ɠ]����ڐG�̍��قɂ��ču�`����B�܂����C�E���Ղ̎�ނƃ��J�j�Y���ɂ��ĉ������ƂƂ��ɁA������ጸ�����鏁���ɂ��āA�����܂̎�ނƏ������@�A����ѕ\�ʑe���Ə������̊W���u�`����B |
�X |
�����̃��T�C�N�� �i���j |
�ߔN�A�����ԓ��̔R�����A���T�C�N���̊ϓ_�ŁA���v�������X���ɂ���y�����ޗ��i�A���~�j�E���A�}�O�l�V�E���j�̃��T�C�N���̌���ь����J���̌���ɂ��ču�`����B |
10 |
�j��Ɣj�ʉ�� �i�����j |
�����A�Z���~�b�N�X���̋@�B�ޗ����j���Ƃ��̉�͕��@�Ǝ��̂��Ĕ������Ȃ����߂̑�ɂ��āA�ߋ��̎�������ƂɊT������B |
11 |
���S�E���S�̂��߂̔�j�� �i�O���j |
�ł��ėp�I�Ȕ�j����@�ł��钴���g�@�ɂ��āA�܂������g�̓��ˁE�`���Ɋւ����b���T�����A���H�\�ʂ̊O�όv���ɑ��钴���g�@�̈ʒu�t���A����сA���������o�Ɛ��@�]���@�ɂ��ču�`����B�܂��A�����g�̉�������ɂ��e���萔�̌v���̌����Ƃ��̕��@���T�����A�����g�̌�������ɂ��ގ��]������є�����H�\�ʑw�ւ̕]���K�p����u�`����B |
12 |
�\���p�ޗ��̐ÓI���x�E��J���x �i�}��j |
���͂ƂЂ��݂���b�Ƃ����ÓI�ȍޗ����x�i�j�x�j�܂��āA�@�B�\���p�ޗ��̔j���̂قƂ�ǂ��߂��J�j��ɂ��ĉ������B�܂��A��J�����i�W�Ƃ��̋��x��]�����邽�߂̔j��͊w�ɂ��ču�`����ƂƂ��ɁA�e��j��͊w�p�����[�^�̈Ӗ��ƈ������ɂ��Đ������A���S�v�̂��߂̍ŋ߂̋K�i�������ɂ��Ă��ӂ��B |
13 |
�\���v �i����j |
�Z�[�t���C�t�v�A�t�F�[���Z�[�t�v�A�������e�v�Ȃǂ̎�X�̐v��@�̍l�����̑�����������ƂƂ��ɁA�P��o�H���\���A���o�H���\���A�N���b�N�A���X�^�\���ȂǁA�\���l���ɂ��v��@�̑���ɂ��ču�`����B�܂��AFEM �Ȃǂ�p������͂ɂ��v�ƌ����ɂ��v�ɂ��Ă��������B |
14 |
�U����� �i�ؑ��j |
�@�B�V�X�e���ɔ�������U���ɂ��āA���̗��_�I�Ȋ�b��������A�U���̓`�B�⌸������щ��U��h�U�ɂ��ču�`����B�܂��A�U���̌ŗL���[�h��́A���@�B�̐U����͂ƈ��S���]���ɂ��Đ�������B |
15 |
�g���ċZ�p �i���j |
���H���i�̑g������������ѐ����ʒu���߂Ɋ֘A����Z�p�ɂ��āA�葬��]�E�����^���@�\��ʒu���߉^���@�\�ȂǁA�g���Z�p�̊�b�ɂ��ĉ������B�܂��A���H���i�̑g������������ѐ����ʒu���߂Ɋ֘A����Z�p�ɂ��āA�T�[�{����ʒu���߉^���@�\��Ǐ]�^���@�\�ȂǁA�g���Z�p�̉��p�ɂ��Ă��u�`����B |