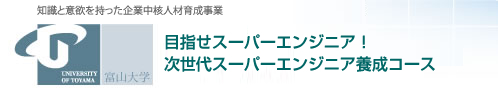ホーム > 受講生の皆様へ > 講義内容(シラバス)> エレクロトニクス工学特論
講義内容(シラバス)2013
エレクロトニクス工学特論
授業科目名 |
エレクトロニクス工学特論 |
||
科目 |
富山大学大学院理工学研究部(工学系) |
||
区分 |
スーパーエンジニア養成コース |
授業種別 |
大学院修士課程実践教育 |
対象所属 |
理工学教育部 |
||
開講日程 |
9月−11月 土曜日1、2限 |
対象学年 |
社会人技術者、大学院生 |
単位数 |
2 |
||
連絡先(研究室、電話番号、電子メール等) |
作井正昭(TEL076-445-6711)、 |
オフィスアワー(自由質問時間) |
|
授業のねらいとカリキュラム上の位置付け |
|||
高度情報化社会を支える基盤技術として、電気・電子工学は重要な役割を果たしている。本講義では、電気・電子工学の多様な分野の基礎となる電磁気の基礎物理、電気回路の基本定理や法則、電子回路(アナログ回路とデジタル回路)の動作原理や設計手法、半導体デバイスの基礎と最先端のデバイス技術、パワーエレクトロニクスの基礎と先端技術を解説する。また、フリーソフトを用いた回路のシミュレーション技術を実習する。 |
|||
達成目標 |
|||
1)電磁気の物理現象、電気回路の基本定理や法則を理解する。 |
|||
講師の紹介 |
||
第1回 |
作井 正昭氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
パワーエレクトロニクス関連技術を専門とし、風力や小水力などの再生可能エネルギー発電装置やコンバータなどの電力変換装置の高性能化、低コスト化に関する研究に従事。 |
||
第3回 |
前澤 宏一氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
I-V 族化合物半導体のエピタキシャル成長技術及びその高周波半導体デバイス、ナノデバイス、量子効果デバイスの応用。また、それらを利用した高周波集積回路の研究に従事。 |
||
第7回 |
中島 一樹氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
医用電子工学、生体計測工学や高齢者工学を専門とし、研究室だけの研究ではなく、日常生活や介護福祉の現場で真に役立つ機器や技術の開発を目指した高齢者用の福祉機器開発に従事。 |
||
第9回 |
小熊 博氏 |
(富山高等専門学校電子情報工学科 准教授) |
衛星系/ 地上系の統合通信ネットワークを対象にFPGA、組込み技術、位置捕捉(QZSS、GPS)、モバイルシステム等の研究に従事。 |
||
第11回 |
作井 正昭氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
第13回 |
松本 康氏 |
(富士電機(株) 技術開発本部 パワエレ技術開発センター応用技術開発部 部長) |
鉄道車両・産業用モータ駆動装置、太陽光PCSなどパワーエレクトロニクス装置の電気回路・制御技術分野およびSiCなどワイドバンドギャップのパワー半導体分野の研究開発に従事。 |
||
第15回 |
飴井 賢治氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)講師) |
専門分野はパワーエレクトロニクス。主に太陽光や風力などの再生可能エネルギーから最大限に電力を取り出す技術やマルチレベルインバータの効率改善、誘導加熱装置の高効率化などの研究に従事。 |
||
キーワード |
電磁気、電気回路、電子回路、アナログ回路、デジタル回路、電気機器、半導体、集積回路、パワーエレクトロニクス、電力変換、回路シミュレータ |
履修上の注意 |
|
教科書・参考書等 |
第15 回:渋谷 道雄 著、「回路シミュレータLTspice で学ぶ電子回路」、オーム社 |
成績評価の方法 |
|
関連科目 |
|
備考 |
|
エレクトロニクス工学特論:授業計画(講義内容、開催予定日、講師)
回 |
主題と位置付け |
学習方法と内容 |
1 |
電磁気基礎と回路論 (作井) |
電磁気の基礎である静磁界、電流と磁界、電磁誘導について講義する。また、電気回路は、過渡現象を含む直流回路、電気回路の諸定理、単相および三相交流回路、非正弦波(ひずみ波)交流について講義する。 |
2 |
電気機器の種類と特性・効率的運用 (作井) |
電気機器の基礎として回転機(直流機、誘導機、同期機)の構造、動作原理、特性について説明する。また回転機の効率的な運用として、新しい構造や特徴をもつ回転機について紹介する。 |
3 |
半導体物性の基礎 (前澤) |
半導体のエネルギーバンド構造、電子統計、電子輸送、pn 接合やショットキー接合などの種々の接合の性質について講義する。これらは今後の講義の基礎となる概念である。また太陽電池など、接合を利用した重要なデバイスについても説明する。 |
4 |
半導体デバイスの基礎 (前澤) |
最も多く使われている半導体デバイスである、電界効果型トランジスタ(FET)について、その動作原理、性能指針について説明する。特に現在の集積回路の基本であるSi-MOSFET の動作原理について述べる。 |
5 |
半導体プロセス技術 (前澤) |
半導体集積回路の作製に関わるプロセス技術の基本について解説する。フォトリソグラフィー、薄膜形成、エッチングなどの基本技術について学んだ後、最近のトピックとして、原子層堆積技術について述べる。 |
6 |
先端半導体デバイス (前澤) |
Si-CMOS 集積回路の最先端技術とその問題点、それを解決する試みについて述べる。また、半導体ヘテロ接合とそれを用いたデバイス、特に化合物半導体を用いた高電子移動度トランジスタ(HEMT)について講義する。 |
7 |
電子回路の基礎 (中島) |
電子回路は計測・通信・制御などのエレクトロニクスの応用分野における汎用的な基礎技術である。本講ではアナログ電子回路の基本的な動作原理を理解することを目的として、最も基礎となるダイオードの特性及びバイポーラトランジスタの基本回路について概説する。 |
8 |
アナログ回路とその応用 (中島) |
増幅器やセンサ回路などアナログ電子回路で広く用いられる演算増幅器(オペアンプ)の基本特性を理解し、オペアンプを用いた代表的な回路の動作を概説する。 |
9 |
デジタル回路の基礎 (小熊) |
デジタル回路の基本となる組み合わせ回路、順序回路、デジタル回路設計用の言語であるハードウェア記述言語及びFPGA (Field Programmable Gate Array)・PLD(Programmable Logic Device)による設計手法の特徴及び現状について講義を行う。 |
10 |
デジタル回路の応用 (小熊) |
無線通信装置等の開発事例を通してFPGA 設計の利点と課題とについて講演する. 加えて、現状の書き換え可能なリコンフィギュラブルデバイスの動向について言及する。 |
11 |
パワーエレクトロニクスの基礎1 (作井) |
電力変換装置の構成要素として用いられる電力用半導体デバイスの種類、構造、特性などを説明した後に、電力用半導体デバイスを用いて電力変換を行う基本的な回路である整流器、直流チョッパ、インバータなどの回路構成、動作原理などについて説明する。 |
12 |
パワーエレクトロニクスの基礎2 (作井) |
交流を直流に変換する整流回路は高調波を発生し、力率の低下や各種の障害の原因となっている。そこで、整流回路から発生する高調波を低減する方法について説明する。また、直流を交流に変換する装置であり、省エネに大いに貢献しているインバータの出力電圧の波形を改善する方法についても説明する。 |
13 |
パワーエレクトロニクス先端技術1 (松本) |
パワーエレクトニクス装置で用いられる最新の電力用半導体デバイスの構造、特性などについて解説する。また、新デバイスを応用した機器を紹介し、その導入効果などについて解説する。さらに、今後の電力用半導体デバイスの技術動向についても解説する。 |
14 |
パワーエレクトロニクス先端技術2 (松本) |
パワーエレクトニクス技術を誘導機や同期機などのモータ制御分野、直流や交流電源の電源分野、直流送電などの電力分野、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー分野に応用した事例を紹介し、その応用技術について解説する。 |
15 |
電気・電子回路シミュレーション技術 (飴井) |
回路シミュレーションソフト“LTSpice”を操作して、受動素子を用いた簡単な電気回路からオペアンプなどの電子回路、さらにパワーエレクトロニクス回路に至るまで様々な回路の解析を体験し、回路シミュレーション技術を修得するとともに、回路動作の理解を深める。 |