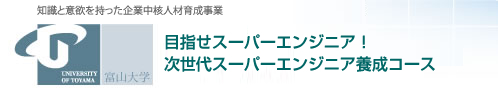ホーム > 受講生の皆様へ > 講義内容(シラバス)> 化学・バイオ工学特論
講義内容(シラバス)2013
化学・バイオ工学特論
授業科目名 |
化学・バイオ工学特論 |
||
科目 |
富山大学大学院理工学研究部(工学系) |
||
区分 |
スーパーエンジニア養成コース |
授業種別 |
大学院修士課程実践教育 |
対象所属 |
理工学教育部 |
||
開講日程 |
1月−3月 土曜日 1、2限 |
対象学年 |
社会人技術者、大学院生 |
単位数 |
2 |
||
連絡先(研究室、電話番号、電子メール等) |
篠原寛明(TEL445-6832)、 |
オフィスアワー(自由質問時間) |
随時。各担当講師に相談下さい。 |
授業のねらいとカリキュラム上の位置付け |
|||
医薬品産業に従事する企業技術者および医薬品関連技術者を志望する大学院生を対象とし、医薬品製造・開発における要素技術の基盤となる高分子化学・有機化学・固体化学・分析化学・薬物と生体との関わり・医薬品開発・再生医工学・バイオ医薬品開発の分野に関して、専門的基礎に重点を置いて講義する。この“学び直し”により、医薬品開発に関する基礎力の充実をはかり、次世代の産業技術者の育成を目指す。 |
|||
達成目標 |
|||
・医薬品開発の基盤となる化学分野の専門的基礎知識を修得する。 |
|||
講師の紹介 |
||
第1回 |
篠原 寛明氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
生物電気化学・細胞電気工学分野(培養細胞を用いる薬物・毒物の迅速簡便な検出定量方法の開発、酵素を用いる代謝物計測用バイオセンサの開発など)。 |
||
第2回 |
北野 博巳氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
高分子化学分野(医用高分子の開発、高分子と水との相互作用の解析、高分子の修飾による材料の高機能化) |
||
第3回 |
吉村 敏章氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
応用物理有機化学分野(新規硫黄窒素3重結合化合物やスルフェン酸等不安定化学種の合成及びその反応機構に基づく新規有機合成試薬の開発等)。 |
||
第5回 |
阿部 仁氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
有機合成化学分野 |
||
第7回 |
宮崎 章氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)准教授) |
精密無機合成化学分野(電気伝導性・磁性を示す有機分子・金属錯体・有機金属錯体からなる分子性結晶の開発など) |
||
第9回 |
遠田 浩司氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
環境分析化学分野(生体内環境をモニターするオプティカル糖センサの開発、環境水中重金属モニター用イオン選択性電極の開発など) |
||
第11回 |
佐山 三千雄氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)講師) |
生物化学分野(生化学、薬物代謝、放射線など) |
||
第12回 |
川原 茂敬氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
脳・神経システム工学分野(電気生理及び画像解析の手法を用いて動物の行動解析と神経活動解析を行い、学習・記憶メカニズムをシステム論的観点から研究) |
||
第13回 |
豊岡 尚樹氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
生体機能性分子工学分野(有機合成化学を用いた新規医薬品の開発、糖尿病、アルツハイマー病、ニコチン受容体に基づく脳機能改善薬など) |
||
第14回 |
中村 真人氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
生体システム医工学分野(高度な機械の手による高度な再生医療技術の開発:細胞を配置する3次元プリンターの開発、印刷技術を活用した組織工学など) |
||
第15回 |
磯部 正治氏 |
(富山大学大学院理工学研究部(工学)教授) |
遺伝情報工学分野(単一抗体産生細胞由来新規迅速抗体単離システムの開発、ゲノム解析技術を用いた疾患(がんや認知症)関連遺伝子の同定とその機能解明) |
||
キーワード |
分子設計、有機合成戦略、溶解度、結晶、X 線回折、分光分析、分離分析、薬物代謝、毒性発現、神経生理学、脳機能改善薬、抗体医薬、バイオ医薬分析、バイオセンサ、再生医工学、生体適合性高分子、有機硫黄化学、物理有機化学、有機合成試薬 |
履修上の注意 |
大学レベルの化学・生物学の基礎知識を有することを前提としますが、異分野の受講生がいれば配慮しますので、最初に申し出てください。 |
教科書・参考書等 |
各回の講師が講義時に紹介します。 |
成績評価の方法 |
出席回数、各講師の講義時の小テストあるいはレポート提出で評価します。 |
関連科目 |
|
備考 |
|
化学・バイオ工学特論:授業計画(講義内容、開催予定日、講師)
回 |
主題と位置付け |
学習方法と内容 |
1 |
緒言及びバイオセンサの開発と応用 (篠原) |
本講義のコーディネーターとして、目的、概要と予定(医薬品開発の基礎となる有機分子の設計・合成、その結晶化学、機器分析・同定、薬品の生体代謝と動物実験、薬物評価に役立つ再生医工学、有機新薬からバイオ医薬の開発トピックスまでつながって学ぶ)を説明する。 |
2 |
高分子化学 (北野) |
高分子と水との相互作用を評価する手法を紹介し、実際に医療に用いられている生体適合性材料表面の化学構造と、当該材料近傍の水の構造との相関について論じる。さらに、固体表面の高機能化に重要な、高分子による修飾法について、わかりやすく説明を加える。 |
3 |
有機分子化学1 (吉村) |
計算科学は創薬の分野においては分子設計に利用されるべく現在研究が進められているが、まだまだ発展の途上である。その内、量子化学計算を用いる方法は最も基本的な原理に基づく方法であり、有機合成や有機化学の研究の場では巨大分子や多量の溶媒分子を含む系でない限り、既によく利用されている。本授業第3、4回ではその量子化学計算の概要および利用例について学ぶ。第3回の内容は量子化学の理論に基づく分子構造の最適化、分子構造と分子の性質、いろいろな物性値、dipole moment, ionization potential, 結合距離、結合角、化学結合の理解、未知の化合物が得られた時にスペクトルのアサイメントの確認や理論的予想するための、振動解析と零点エネルギーIR・Ramanスペクトル、NMRスペクトルの計算などについて学ぶ。 |
4 |
有機分子化学2 (吉村) |
第4回の内容はパソコンを用いたMOPACまたはGAUSSIANプログラムによる実習を行い、生成熱、異性体の安定性の比較と予想、反応熱、歪みのエネルギーの見積もり、スペクトルの計算、電荷、フロンティア軌道と反応性指数からいろいろな試薬がどの原子に反応し易いかを予測する。 |
5 |
有機合成化学(基礎の部) (阿部) |
有機合成の基礎について講義する。その上で、受講生が身に付けているであろう化学の基礎的知識を総動員して、複雑な分子を構築するためのノウハウを概説する。 |
6 |
有機合成化学(応用の部) (阿部) |
多くの有機単位反応が実際の化学合成においてどのように用いられるか演習する。特に、複雑な構造を持つ天然物の合成を教材として、標的分子の実践合成法を修得させる。 |
7 |
固体化学の基礎 (宮崎) |
分子固体中の分子間相互作用について概説し、固体の溶解度・結晶化溶媒の吸脱着・結晶多形の発現などの固体の示す諸性質について議論を行う。 |
8 |
機器分析化学:X線回折 (宮崎) |
結晶学の基礎を概説し、粉末・単結晶X線回折法を用いて結晶相の同定、分子・結晶構造の決定を行う際の留意点について講義する。 |
9 |
原理・基礎・応用発光/吸光分光分析とNMR (遠田) |
電磁波と物質の相互作用を概説し、原子発光/ 吸光分析法及び分子吸光/ 蛍光分析法の原理と最新の応用例について述べる。また、分子構造解析の強力なツールである核磁気共鳴法の原理と1 次元及び2 次元スペクトルの解析法について解説する。 |
10 |
原理・基礎・応用分離分析と化学センサ (遠田) |
クロマトグラフィー及び質量分析法の原理を概説し、これらの最新の応用例について述べる。また、測定対象物質の連続的なモニタリングが可能な電気化学センサ及びオプティカルセンサについて解説する。 |
11 |
薬物(化学物質)と生体との関わり (佐山) |
薬物代謝研究の意義、薬物代謝の様式、代謝研究のドラッグデザインへの応用、代謝と毒性発現機構研究の実例について講義する。 |
12 |
中枢神経作用薬のスクリーニング法 (川原) |
神経生理学の概要(ニューロンの電気生理学と主な脳領域の構造と機能)について学んだ後、動物 (特に遺伝子組み換えマウス)を用いた行動神経科学的実験(スクリーニング法)について知識と理解を深める。 |
13 |
医薬品開発の新展開 (豊岡) |
有機合成化学手法を駆使した新規医薬品の創製例を述べる。 |
14 |
再生医工学の基礎から最前線 (中村) |
再生医療および再生医工学の概要と研究の流れを概説する。 |
15 |
バイオ医薬品開発 (磯部) |
現在世界の製薬企業で注目を集めている抗体医薬に関連する、免疫学や抗体の基礎知識から抗体医薬の応用分野、さらには最先端の抗体単離技術などを含めて講義を行う。また、近年注目されてきたバイオ後発医薬品とその課題についても概説する。 |