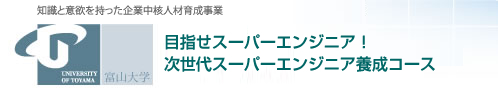�z�[�� �� ��u���̊F�l�� �� �u�`���e(�V���o�X)�� ���i�����v���Z�X���_
�u�`���e�i�V���o�X�j2013
���i�����v���Z�X���_
���ƉȖږ� |
���i�����v���Z�X���_ |
||
�Ȗ� |
�x�R��w��w�@���H�w�������i�H�w�n�j���� �X�p�� |
||
�敪 |
�X�[�p�[�G���W�j�A�{���R�[�X |
���Ǝ�� |
��w�@�C�m�ے����H���� |
�J�u���� |
1���|3���@�y�j���@3�A4�� |
�Ώۊw�N |
�Љ�l�Z�p�ҁA��w�@�� |
�P�ʐ� |
�Q |
||
�A����(�������A�d�b�ԍ��A�d�q���[����) |
�X�@�p���iTEL445-6856�j�A |
�I�t�B�X�A���[(���R���⎞��) |
|
���Ƃ̂˂炢�ƃJ���L��������̈ʒu�t�� |
|||
���i�̐����ߒ��ł́A����̔��������E���������ɂ����鏻�́A�h�߁A�����A�����Ȃǂ̑��삪�A�܂����܉��ߒ��ł͌���̏[�U�A�����A�ŏ��ɂ�镊�`���Ȃǂ̑��삪�s����B�{�u���ł́A���i�����v���Z�X�̍\���Ɗe�H���ŕK�v�Ƃ����G���W�j�A�����O����A���ɕ��̍H�w�𒆐S�Ƃ������̓��L�̌��ہA�n���h�����O�ɂ�����g���u���̎��ۂȂǂ��A��X�ȒP�ʑ����ʂ��ė������A���i�����v���Z�X�ւ̉��p�ɖ𗧂Ă邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B |
|||
�B���ڕW |
|||
�P�j���i�����ߒ�����A�̃v���Z�X�i��Ƃ��ĕ��̍H�w�j�Ƃ��đ������̓����ƌ��������𗝉��ł��邱�ƁB |
|||
�u�t�̏Љ� |
||
��1�� |
����@�N���� |
�i�x�R�����i���������Z���^�[�����j |
(��)�L�ѓ�������@�J���E�c�Ɩ{�������o�Č��E�B |
||
��@���O�� |
�i�x�R��w���_�����j |
|
���Y���w���A�x�R��w�������o�āA�{���Ƃ̎����ǂɏ]���B���͏��͍H�w�A���Ɍ����ȁA�������`�B |
||
��2�� |
�����@�ώ� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������y�����j |
�i�m�A�}�C�N�����[�^�I�[�_�[�̔����q��Ώۂɂ����A�C���A�t���ɂ�����E�ʕ����̐���ɂ��A���l�ȍ\���̋ÏW�̂̍쐻�A�Ł^�t�����A�E�ʓ��d���ۂɊւ��錤���B |
||
��4�� |
�H����@�d�M�� |
�i���i�m�V�[�Y�Z�p�ږ�j |
���̂̏�����Ɋւ�镲�̕����̑���@�E�]���@�A���ɕ��̂̃n���h�����O�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��t�������̗̂������Ɋւ���]���@�̊J���A����ѐ��Y����ɂ����镲�̗̂������Ɋ֗^������q����т��̃��J�j�Y���̌��� |
||
��5�� |
�R�{�@���s�� |
�i(��)�x�R��w���H�w�����������j |
���̂̍����E�ΐ́E�����E�ѓd���ۂ̉�͂���т��̉��p�A���q�̌`���́E��ʉ��Ȃǂ̊�b�����B |
||
��7�� |
���@�M�c�� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�����������j |
���̗����w�̊�����ł̉��p�Z�p�J���A�ő́\�C�̌n�����v���Z�X�̐v����уo�C�I�}�X���܂ތő̔p�����̔M�G�l���M�[���p�v���Z�X�Ɋւ���Z�p�����J���B |
||
��8�� |
�X�@�p���� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�����������j |
���̂������ȑg�D���@�\��͕킵�A���̂ɓK������ޗ��i���A�C���v�����g�A��ܕ��o���䐻�܁A�J�v�Z���������j�݂̂Ȃ炸�A��ʓI�ȍޗ������v���Z�X�ɔ��W�����邽�߂̋Z�p�J���B |
||
��9�� |
���X�@�`�M�� |
�i�_�ˊw�@��w��w�����j |
���s��w��w�����A�����_�H����u�t�A���k��w���u�t�A�_�ˑ�w��w��U�ȋq���������o�Č��E�B���F�����q�̃R�[�e�B���O�Ɋւ��錤���A�K�����Â̂��߂̈��i�����q���܂̊J���A�y�ь��q�̑��B�ׂ̈̃i�m�f�o�C�X�̊J�����B���{���̍H�ƋZ�p����ψ��A���{��w��ҏW�ψ��� |
||
��11�� |
�R�{�@�C���� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�����������j |
����������Ƃ��Ẳt�|�t�������U�n��C�|�t���U�n�̓��I�����Ɋւ��錤���A�t�|�t���o�v���Z�X�⏻�̓v���Z�X�Ȃǂ̐��������v���Z�X�Ɋւ����b�I���� |
||
��13�� |
�X�@�p���� |
�i�x�R��w��w�@���H�w�����������j |
���̂������ȑg�D���@�\��͕킵�A���̂ɓK������ޗ��i���A�C���v�����g�A��ܕ��o���䐻�܁A�J�v�Z���������j�݂̂Ȃ炸�A��ʓI�ȍޗ������v���Z�X�ɔ��W�����邽�߂̋Z�p�J���B |
||
��14�� |
�g�c�@������ |
�i�x�R��w��w�@���H�w�������y�����j |
���i�������̍��@�\�ޗ������v���Z�X�ɂ����銣������̍œK���E��������M�����̈ړ����ۘ_�̗��ꂩ�痝�_�I�ɉ�́A����ьv����@�̊J�������B |
||
�L�[���[�h |
���́E���́E��߁E�����E�����E�����E���` |
���C��̒��� |
�����E���w�̊�b�m���i��w���{���x�j |
���ȏ��E�Q�l���� |
|
���ѕ]���̕��@ |
�o�Ȃ���у��|�[�g |
�֘A�Ȗ� |
|
���l |
|
���i�����v���Z�X���_�F���ƌv��i�u�`���e�A�J�×\����A�u�t�j
�� |
���ƈʒu�t�� |
�w�K���@�Ɠ��e |
�P |
���_ �i����A��j |
���i�����v���Z�X�̍\���Ɠ����A�P�ʑ���I�v�l�@�Ɋ�Â��v���Z�X�̖��_�Ƌ��ʉۑ�ɂ��ďq�ׂ�B�X�ɏ��i�v�ƋK�i�A���͖@�ƌ��������̖h�~�@���ɂ��Č��y����B |
�Q |
���q�Q�̏W�ϓ��� �i�����j |
���i�̐����v���Z�X�ɂ����镲�̂̏[�U�A�����A�����Ȃǂ̊e�����ǍD�ɍs���ɂ́A�X�̗��q�̓����Ƌ��ɂ����̏W���̂Ƃ��Ă̗��q�Q�̏W�ϓ������悭�m�邱�Ƃ��K�v�ł���B�u�`�ł́A���q�a�A���q�`��A���q�a���z�Ȃǂ̊�{�I�����ɂ��Đ������A���ɋψꋅ�̌n���I�z��ɂ�郆�j�b�g�Z���A�Ŗ��[�U���_�A����ш�ʂ̗��q�̃����_���[�U�ɂ�����W�ϓ����ɂ��Đ�������B |
�R |
���������q�Q�̓��� �i�����j |
�����◱�q�w�̊�������𗝉������ŏd�v�ȁA���q�w���ɉt�̂����݂���ꍇ�̗��q�ԗ́A���q�Ԃ̕ێ��t�ʁA���q�w���̖ъǏ㏸�����A�c�����t�O�a�x�ɂ��Đ�������B |
�S |
���̑���P�F���� �i�H����j |
�����q�̏W���̂ł��镲�̂���i�Ƃ��Ă̕��Ӗ@�ɂ��āA��b�I�ȗ��_���ł��邾�����ՂɏЉ��B���ɁA�]������p�����Ă��镲�ӑ��u�̓�������їp�r���T�����������ŁA�������̂̐���ɉ��������ӕ��@�̑I���A���ӌ�̗p�r�ɓK�����镲�ӕ��@�̑I���Ȃǂɂ��čl�@����B����ɁA�V������Ă���Ă���T�u�~�N��������i�m�I�[�_�[�܂ŕ��ӂ��\�ȕ��ӑ��u�ɂ��Ă��Љ��B |
�T |
���̑���Q�F��������� �i�R�{�j |
�����̂̍����x�A�������x���A�����Ɋւ����{�I�������T�����A���̋ψꐫ�̕]���@���čl�@����B�X�ɗl�X�ȕ������@�i�����@�A�����@�A�A�������@�j�̓����ƕ������ꂽ���i�̓����ɂ��ďq�ׂ�B |
�U |
���̑���R�F�A�� �i�R�{�j |
���̈��A�nj��E���@�A���o�i�t���b�V���j���x�̊T�O�ɂ��Đ������A�l�X�ȕ��̗A�����u�̐v�v�Z�ɂ��ďq�ׂ�B |
�V |
���̑���S�F���� �i���j |
�����w�����v�ɂ�����闬���w�̌�������ь`�������╲�̗��q�Ԃ̏���p�͂ɂ��ďڏq����B�������q�̌`��A�傫������ы��x�Ȃǂ̓����ɉe����^���镲�̂̕t���E�ÏW���◬����Ԃ⌋���܂̎�ނɂ��čl�@����B�܂��V���������@�Ƃ��ăo�C�_���X�i�����܂Ȃ��j�����@�∳�̓X�C���O�����@���q�ׂ�B |
�W |
�����̂̃��I���W�[���� �i�X�j |
���̂̃��I���W�[�����́A���̑w����������ꍇ�̊�{�P�ʂł��闱�q�܂��͗��q�W���̓��m�̓������C�ɂ�錻�ۂƂ��Đ��������B���̓����͕��̂̈����E�[�U�����ɋ����e�����邱�Ƃ𗝉����邽�߁A�������̊ȕւȕ]���@�A���������ɂ��������C�̋��ߕ��A�����ߒ��̉�͖@�ɂ��ďڏq����B�܂����̂̋ÏW�E�ΐ́A�����e����ł̈��͕��z�ȂǁA���������֗^���镲�̓��L�̌��ۂɂ��Ă��l�@����B |
�X |
�ŏ� �i���X�j |
�ŏ����������邢�͕������P�Ƌn�ɂ�舳�k���ď��܂𐬌^����ߒ��ŁA���܉��̊�{�ł���B�P������у��[�^���[�ŏ��v���Z�X�̊T�v�ƕ��̓������֗^����ŏ��g���u���̔����v���A����ёŏ���Q�������N�����������ɂ��ďڏq����B |
10 |
�R�[�e�B���O �i���X�j |
�R�[�e�B���O�͏��܁A�����ܕ\�ʂ𔒓��⍂���q�̔疌���`�����鑀��ŁA�s���Ȗ���L���̃}�X�L���O�A�h���A�Ռ��A�_���h�~�A�܂��R�[�e�B���O�ܓ����𗘗p�����n�o����Ȃǂ�ړI�Ƃ���B��\�I�Ȕ햌�܂���т��̃R�[�e�B���O�@�A�܂����������܂Ȃǂ̋@�\�t�^�ɂ��ďq�ׂ�B |
11 |
���͂P�i���͂̊�b�I�����j �i�R�{�i�C�j�j |
�L�������̕�����������ї��q�Q��������Ƃ��Ă̏��͂𗝉������Ō������Ȃ���b�����Ƃ��āA�ʼnt�Ԃ̑��ω��A�ߖO�a�Ə������A�����̊j�����ہA���������̋@�\�Ƒ��x�A�����n�̕��ނȂǂɂ��ĊT������B |
12 |
���͂Q�i�H�ƓI���͑���̗����Ɍ����āj �i�R�{�i�C�j�j |
���i����̕��������v���Z�X�Ƃ��Ă̏��͂ɂ����ē��ɏd�v�Ȍ������`���ۂ��A���̈�ʓI�ȕ]���@�Ƌ��ɐ�������B�܂��A���͑���̊�{�헪�Ə��͑��u�I��E����v���A�����v���Z�X�ň�ʓI�ɗp��������͂𒆐S�ɐ�������B |
13 |
�h�߁E�������� �i�X�j |
���͂Ȃǂ̎����v���Z�X�œ���ꂽ���������́A�����E��������Ƃ��ăP�[�N�h�߂��s����B�h�ߒ�R����r�I�������ꍇ�▧�n�ŏ����������ꍇ�ɂ͉����h�߂��A����ȊO�ł��h�ߑ��x��E�t�����ɗD��鉓�S�h�߂��K�p�����B��{�I���h�ߓ����̕]���@�A�h�߂̋@�\������h�ߑ���̎��ۂɂ��ďq�ׂ�B |
14 |
�����P �i�g�c�j |
���i�����̐����i���������́��h�߁������j�ɂ����銣������͍ŏI�i�K�Ƃ��Ĕ��ɏd�v�ȈӖ������D�����@�\�̊�b�ɂ��ĊT�����A��������̍œK���E�������ɂ��Č��y����B�Ƃ��ɔM�ƕ����̓����ړ����ۂ��I�ɑ����A���̌����Ɋ�Â��Ċ���������\�����C���u�v�⑀��v���s�����߂̎w�j�ɂ��ďq�ׂ�B |
15 |
�����Q �i�g�c�j |
�^���A���������A���������A����ї��������ȂǁA��������̊�b�ɂ��ďq�ׁA�����̑��u�����ɂ��Č��y����B�܂���������Ɠ����鐻�i�̗�������[�U���̉��P�A���w�I�����̈��萫�ȂǁA�i���Ƃ̑��ւɂ��ĊT������B |