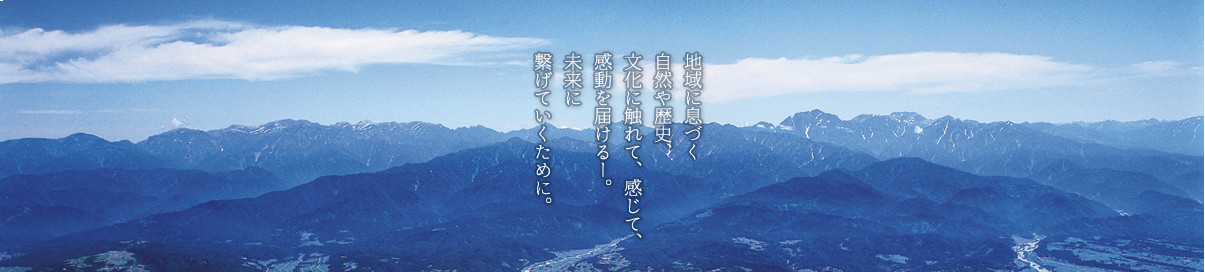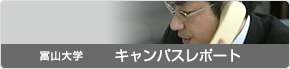- 変化する博物館
今、そしてこれからの博物館に求められるもの - 開催日時:平成28年2月4日(木)14:00~17:10
場所:魚津市役所第5・6会議室
魚津市立博物館(魚津水族館・魚津埋没林博物館・魚津歴史民俗博物館)3館の学芸員勉強会が開かれ,他県博物館の取組事例を学び,3館連携や利活用についてや将来の方向性を探った。
開催の経緯と目的
魚津市企画政策課地域資源推進班 前田久則氏・塩田明弘氏
勉強会開催の経緯と目的について説明。富山大学の共同研究員として「魚津市にある3博物館の連携,利活用,今後の方向性について」を研究テーマとし,「少子高齢化に伴う人口減少社会」や「公共施設の老朽化に伴う統廃合」などの地域課題がある中で,魚津市の博物館はどうあるべきかを検討してきた,博物館の中長期的な組織強化を図り,3館の事業連携を推進する「魚津市公共施設再編方針」が策定されたことも関連している。
3館学芸員の合同勉強会の必要性を各博物館や市教育委員会へ呼びかけ,27年から勉強会の開催準備に入り今回の開催に至るまでの経緯を説明した。また,勉強会を通じて3館の将来像や方向性を共有し,地域連携・地域貢献等の共同研究を実施し,魚津市立博物館の新展開となる提案事業の実施とアクションプランの策定をおこなうことが本勉強会の目的で,博物館による地域の活性化につなげていきたいと説明した。

講義① 地域と共に地域に貢献する博物館
兵庫県立人と自然の博物館 自然・環境マネージメント研究部門 主任研究員 赤澤宏樹先生
自然史系・環境系博物館として平成4年に開館した兵庫県立人と自然の博物館(ひとはく)の概要や今日までの改革や新展開,地域との連携や地域への貢献等の説明を受け,ケーススタディとして魚津市での取組のヒントを探った。
 同館は平成4年に兵庫県立博物館の1つとして開館。自然史系,環境系(地球科学,系統分類,生態,環境計画,生物資源)の研究型博物館で,兵庫県立大学付属の自然環境系研究所であり,展示・資料収集・普及教育・調査研究・学術交流,シンクタンク,ジーンバンク,データバンクの機能と役割を持っていると紹介。日本を代表する博物館改革となった「新展開」について説明。平成12年度に1年間をかけて博物館活動を全面的に見直し,これからの博物館活動のあるべき方向を「人と自然の博物館の新展開」としてとりまとめた背景や内容を説明。特に,館員・研究員の意識改革については県民のための博物館として,これまでの既成概念の払拭し,自分たちで企画,提案,実践して中期目標の設定まで行ったことを説明。
同館は平成4年に兵庫県立博物館の1つとして開館。自然史系,環境系(地球科学,系統分類,生態,環境計画,生物資源)の研究型博物館で,兵庫県立大学付属の自然環境系研究所であり,展示・資料収集・普及教育・調査研究・学術交流,シンクタンク,ジーンバンク,データバンクの機能と役割を持っていると紹介。日本を代表する博物館改革となった「新展開」について説明。平成12年度に1年間をかけて博物館活動を全面的に見直し,これからの博物館活動のあるべき方向を「人と自然の博物館の新展開」としてとりまとめた背景や内容を説明。特に,館員・研究員の意識改革については県民のための博物館として,これまでの既成概念の払拭し,自分たちで企画,提案,実践して中期目標の設定まで行ったことを説明。
従来の自然系博物館の枠を超えた新しい博物館として「思索し,行動し,提言する」機能を拡充した「自然・環境系博物館」となり,生涯学習とシンクタンクを新展開の基盤として「県民と共に思索し,行動し,提言する」循環システムを構築する具体策として実践した事業活動について紹介。学習機会を提供したセミナー充実による担い手養成,県民ニーズに応えた学習の場の提供としてキャラバン事業の実施,自然・環境情報の一元管理や総合的なシンクタンク活動などの事業によりビジター数や地域との連携が広がったことを説明。
新展開の実践で「地方の個から汎用へ!地域から国,グローバルへ!」ということを学んだと話し,これからの博物館の展開として生涯学習院や多様な主体が関われる仕組み,多様な評価手法の導入について,地域社会の人々の生活と其処の自然,社会環境を現地において保存し,育成し,展示することを通して当該地域社会の発展に寄与することを目的とした博物館であるエコ・ミュゼについて紹介。博物館の枠にとらわれることなくフラットな形で展開を考えていくことの重要性を伝えた。
講義② 学芸員がすべてをクリエイトする
博物館の存在意識は、自らがつくり出す
兵庫県立人と自然の博物館 企画調整室室長 主任研究員 八木剛先生
兵庫県立人と自然の博物館(ひとはく)の活動紹介と同館での学芸員の職務や考え方について説明を受け,学芸員のあり方,各自の仕事の再構築や方向性へのヒントを探った。
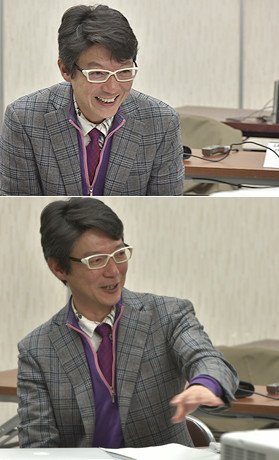 学芸員は,博物館資料の収集,保管,展示及び調査研究その他関連する事業についての専門的事項をつかさどる「博物館法」に定められた専門的職員であり,学芸員の職務は無限大であると話し,博物館の実務現場での現実問題や展覧会主義の問題を挙げ,ひとはくの学芸員は博物館法ではなく原点の教育基本法で考え「地域を愛する心を育み,地域の自然・環境・文化を未来へ継承すること」をミッションにその態度を養うために「生涯学習・シンクタンク」事業を,コンテンツ開発に「調査研究・資料収集保管」事業をそれぞれ活用する事業体系を組み立てたことを説明。博物館がこれまでの「来てもらう」から「出かけて行く」へ変革した「移動博物館車ゆめはく」の事業を紹介し,利用者総数の変化や来館エリアを示し,のキャラバン訪問の効果を説明。
学芸員は,博物館資料の収集,保管,展示及び調査研究その他関連する事業についての専門的事項をつかさどる「博物館法」に定められた専門的職員であり,学芸員の職務は無限大であると話し,博物館の実務現場での現実問題や展覧会主義の問題を挙げ,ひとはくの学芸員は博物館法ではなく原点の教育基本法で考え「地域を愛する心を育み,地域の自然・環境・文化を未来へ継承すること」をミッションにその態度を養うために「生涯学習・シンクタンク」事業を,コンテンツ開発に「調査研究・資料収集保管」事業をそれぞれ活用する事業体系を組み立てたことを説明。博物館がこれまでの「来てもらう」から「出かけて行く」へ変革した「移動博物館車ゆめはく」の事業を紹介し,利用者総数の変化や来館エリアを示し,のキャラバン訪問の効果を説明。
「教える」から「感じる」ことをテーマにした「Kid’sひとはくプロジェクト」を紹介して教育機関としての博物館の重要な役割は,地域資源を発掘し素敵なエピソードを創出することであると話した。「態度を養う」アプローチには知識や意味を勉強し,教わり,学ぶという方向と遊び,感じるエピソードを通じて学ぶという2つの方法があるが,エピソードは時間が経っても忘れることがないと話し,同館でエピソード創出型アプローチの事業事例をあげ説明した。また,館種や地域を越えた連携をはかり新たな価値を創出している事業事例やボランタリー中心の新たなプラットフォームの形態を紹介し,若者を育成し博物館ボランティアとしていっしょに歩む仲間づくりを図っていることを説明。博物館とボランティアが連携してサービス受益者のニーズに対応する現在の活動スタイルを示した。
博物館では学芸員〈研究員)がすべてなので自分のことは自分で決めるコトができる仕組みとして,同館ではひとはく企画調整室を設け,館内組織,予算配分,会議の運営,予算要求,外部評価,危機管理,局面づくりなどの役割をこなし研究員を主役としたパフォーマンスの向上に努めていると説明。また,プロジェクト制を取り,個々の研究員が外部と連携して実施している事業・研究が非常に多いことや,成果や活動の可視化や質的評価を取っていることを説明し,小説「鏡の国のアリス」の中で、赤の女王がアリスに言った『同じ所にとどまろうと思うなら、全速力で走りつづけなさい』という一節をあげ,博物館を取り巻く周囲が変動しているために、その場にとどまるために全速力で走り続けて進化を継続していかなければならないとメッセージをおくった。
質疑応答・意見交換会 「変化する博物館 ~変化と再生~」
コーディネーター
富山大学地域連携推進機構 金岡省吾 教授
富山大学芸術文化学部 奥敬一 准教授

講義を受けた魚津市立博物館(魚津水族館・魚津埋没林博物館・魚津歴史民俗博物館)の学芸員と講師による質疑応答と意見交換会が,富山大学金岡教授と奥准教授のコーディネートによりおこなわれた。3館の学芸員がそれぞれの館の現状について説明し,講義の疑問点や踏み込んだ内容について質問し,各館の抱えている課題や学芸員の悩みなどへのアドバイスを求めた。講師からはそれぞれの課題解決のためヒントや経験に基づいたアドバイスがなされた。「どんなターゲットを想定しているか?見に来てどうなるか?何を目標にしているか?を中長期で捉えること重要でそれによって評価も異なる」と八木氏と赤澤氏からアドバイス。これからの博物館に求められる将来像や方向性について活発な意見交換がおこなわれ,博物館による地域の活性化を目的とした「魚津市立博物館の新展開」へ向けたステップとなる勉強会は終了した。