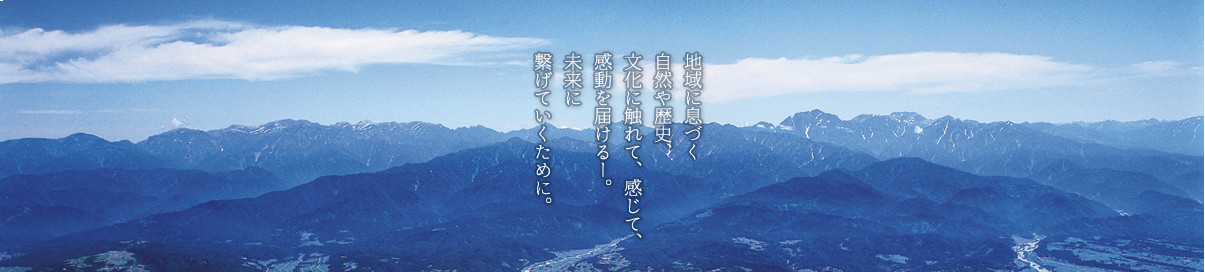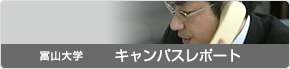- 開催日時:平成28年3月24日(木)14:00~17:00
場所:魚津市役所第一委員会室
魚津市から富山大学へ派遣された民間等共同研究員の活動および研究内容の報告会が開催され,魚津市立博物館3館(魚津水族館・魚津埋没林博物館・魚津歴史民俗博物館)の方向性について等をテーマに,副市長,教育長,総務部長はじめ担当部署課長との間で意見交換の場がもたれた。
開会
進行:魚津市企画政策課地域資源推進班 前田久則氏
前田氏より本日の配付資料の確認と進行の流れが示され、塩田氏より2月4日に開催した3館学芸員勉強会を経て,本日の報告会開催となるまでの経緯説明が行われた。

第1部・報告会①
研究活動経過報告ー25~27年度ふりかえりー
報告者:魚津市企画政策課地域資源推進班・富山大学地域連携推進機構民間等共同研究員 塩田明弘氏

25年度から27年度の研究活動の経過を報告。本報告会開催の目的は,魚津市から派遣された民間等共同研究員の活動及び研究内容についての報告とこれからの博物館に求められるもの,博物館がもつ可能性について市上層部の意見を聞き,3つの博物館の方向性について意見交換の場とすることと説明。
魚津市から派遣された富山大学民間等共同研究員の活動状況と経緯を紹介し,塩田氏が民間等共同研究員として取り組んだ研究テーマや活動内容を報告した。研究テーマは,「魚津市にある3つの博物館の連携,利活用,今後の方向性」と設定。「少子高齢化に伴う人口減少社会」や「公共施設の老朽化に伴う統廃合」などの地域課題の中,「魚津市の博物館はどうあるべきか」を検討し,先駆事例の視察やヒアリング調査を実施したと具体的な活動内容を報告。博物館による地域活性,3館の事業連携の推進を目指し,平成27年度の活動として,伊串ゼミの開催,先進地視察,3館学芸員勉強会の開催を経て,本日の報告会に至るまでの詳細を説明し,歴史民俗博物館の可能性を提案した。
第1部・報告会②
魚津水族館を活用した地域活性化
報告者:魚津水族館飼育研究係 学芸員 伊串祐紀氏

博物館は地域活性化の資源と考え学術・観光だけでなく,交流・産業・情報発信に活用し,魚津水族館を地域活性化の核の役割として活用させるべきと提言。日本で現存最古の歴史を持つ魚津水族館の歴史を紹介し,平成25年創立100周年リニューアルした現在の水族館の現状と課題について説明。
入館者数の推移や施設の状況を示し,施設の外観の劣化やノンバリアフリーな館内,付帯設備の不備,運営体制の問題点や課題を言及。それを踏まえて魚津水族館のあるべき姿を提案。魚津水族館の位置付けは市内の経営体の一つとして地域産業の官民連関度を高める役割とし,市内外から魚津に人を呼び込み,魚津を手にとって情報発信させる交流人口ネットワークの拠点,人・モノ・情報のプラットホームとしての役割を果たし、合わせて市外の資源と魚津をつなぐ役割を持つべきと提案。魚津水族館の存在価値や経済波及効果を考えた活用方法など7つの事業提案を説明。まとめとして,水族館の魅力向上と地域発信,地域による水族館活用による地域の魅力発信が魚津市の活性化・繁栄につながり,水族館・企業・利用者が共にWinの関係を築ける施設にしていきたいと話した。
質疑応答
塩田研究員・伊串研究員の報告においての質疑応答が行われた。魚津市3博物館の連携のエコミュージアム構想の課題や事業提案の実現性や課題について,3館連携自体の課題や学芸員の人材育成など活発な議論が交わされた。

第2部・講義・話題提供
地方創生と公共施設
~地域づくり・地域活性化の先進事例紹介~
富山大学地域連携推進機構副機構長 地域戦略連携室長 金岡省吾 教授
地方創生と公共施設をテーマに,公共施設が地域活性化の核となった事例や地方創生で求められるもの,地域づくりの考え方の変化などについて全体での意見交換に向けての話題提供となる講義が行われた。

最近,気になる公共施設の事例を紹介。神戸市で15年6月に社会実験として行われた公園内に図書館をつくるアウトドアライブラリーの事例をあげ,公共施設への考え方が大きく変化し主役は地域の人になってると話し,北海道北見市留辺蘂の「山の水族館」の事例をあげ,移転リニューアルの状況,郷土館の併設や商業施設との連携などにより地域観光の核となる施設になっている先駆例を紹介。長野県塩尻市の市民協働で地域ニーズ優先型施設を整備した事例を紹介し,市民講演会やワークショップ通じソーシャルキャピタル形成していく経緯や図書館と子育て支援の融合で人が集まる施設となり,まちなか活性という地域課題解決や役所の組織改革にもつながったと説明。県内の事例として駅舎に図書館を併設させた舟橋村の事例を紹介し,地域特性に即した子育てに特化させ,人口減に対応。地域社会を活性化するサードプレイスが今求められているらしいと話した。
事例をあげた公共施設は地域活性化に必要な機能を持ち,新たな主役となっており,このままでは公共施設は必要とされる施設とその他の施設に2極化すると明言。魚津市の公共施設も何のためか?地域をどう変えるのか?参考にすべき点がこれらに潜在してないか問いかけた。また,地域創生と新たな国土形成計画で求められる新たな地域づくりの世界について講義。これまでの社会資本・インフラをつくる地域づくりから,新たな公の考え方が登場し従来とは異なる方法での地域活性化へと変化,地域課題解決への地域経営へと変わっていくと,広島県安芸高田市の川根振興協議会の6次産業化やエコミュージアム・包括ケアサービスの事例をあげ説明。日本版CCRC構想や国土計画の「小さな拠点」づくりについても触れ,将来の人口を考え,地域の将来像を考え,起業増加するまちづくりのため人を育て,人の絆をつくることがこれからの地域づくりであると話した。
まとめとして,現在の地域活性化,地方創生の背景の中,公共施設としての博物館の存在意義の必要条件,十分条件は何かを考え,求められる機能は何か?何を追加すべきか考えなければならないと話し,地方創生と公共施設の関係について話題提供した。
意見交換会・座談会
テーマ「これからの博物館に求められるもの」
コーディネーター:富山大学地域連携推進機構 金岡省吾 教授
富山大学芸術文化学部 奥敬一 准教授
魚津市での地域活性化・地方創生の状況や魚津の3博物館に求められるもの,必要性などについて意見交換,ディスカッションをおこなった。

モノゴト(人・事業・金)を循環させるシステムの必要性,ターゲットの絞り込みや産業との関わりが話し合われた。また,人口減少を食い止めるためには長期的なキチンとした人づくり・まちづくりが必要,魚津の豊かな自然の中での活発な文化活動が地域活性化につながる,近隣市町村との連携観光・産業振興も周辺が一緒になって取り組む必要があるなどの意見がだされた。
魚津の3博物館については,長期のまちづくりの中で考える必要性,地域と連携させることの重要性,モノを見せるだけではなく産官学金連携のサードプレイスをいれる必要性があると討論。博物館は人材が全て,人材育成は重要,博物館の評価は入館者数だけでなく他の評価も入れるべきという意見や,3館連携の可能性や各館の学芸員連携の重要性,さらに現状の課題についてもあげられ内容の濃い意見交換がおこなわれた。
閉会・総括
魚津市副市長 谷口雅広氏
 有意義な意見交換をすることができた。評価の指標化といったソフトの部分は難しい部分だが,住民からの意見を統計化し指標とする方法もあるだろう。自分たちの評価を自分たちでつくってみるのも面白い試みであろう。社会教育の仕事は大変面白く,住民との繋がりも非常に強く,他からの意見もたくさん聴ける。自分たちが面白く感じられること多くあるだろう。そこを切り口に考えても良い。学芸員の「人の力」に期待していきたい。
有意義な意見交換をすることができた。評価の指標化といったソフトの部分は難しい部分だが,住民からの意見を統計化し指標とする方法もあるだろう。自分たちの評価を自分たちでつくってみるのも面白い試みであろう。社会教育の仕事は大変面白く,住民との繋がりも非常に強く,他からの意見もたくさん聴ける。自分たちが面白く感じられること多くあるだろう。そこを切り口に考えても良い。学芸員の「人の力」に期待していきたい。