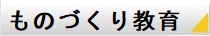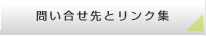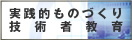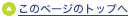3大学協働ものづくりプロジェクト
概要
特色GPでは3大学工学部が連携しながら事業を進めてきましたが、ものづくりカリキュラムやものづくりの実習は各大学で閉じられており、作品を3大学共催の「ものづくりアイディア展」で発表するという活動にとどまっていました。
平成18年度から新しい事業として、3大学工学部から4年生が集まって混成チームをつくり、卒研レベルのものづくりを行う「三大学協働ものづくりプロジェクト」を開始しました。
現在、「風力発電」と「微細加工」という2つのプロジェクトが実施されています。
本プロジェクトは、所属、専門分野の異なる学生・教職員が協働し、その知識、経験、技能を結集することにより、レベルの高い研究開発を目指しています。
本事業の主な特徴は、以下の通りです。
- 3大学工学部の4年生が、協働して一つのテーマに卒業研究として取り組む。
- インターネットの活用により、遠隔地のメンバー間の綿密な連携を図りながら研究を進める。
- それにより、高い教育効果を得ると共に、高レベルの研究成果が期待できる。
目的と意義
1.新しい教育モデルの提案
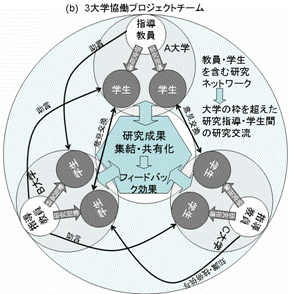
水準の高い研究成果を得るために対象学生を卒業研究生とし、指導教員間の共同研究(大学間共同研究)として実施するものです。 下記の特徴を持っています。
- 学生は講義などの制約なしに、フルタイムでプロジェクトに集中することができます。
- 研究テーマは指導教員の専門分野に関連するので、協働し、また補完し合うことにより研究の質を高めることができます。
- 参加学生は研究計画の立案段階から議論に参加します。 学生が研究計画全体を把握しながら自らの分担テーマに取り組むので、高い教育効果が期待できます。
2.新しい共同研究モデルの提案

本プロジェクトは、新しい共同研究形態の試行としての意義を有し、下記の特徴を持ってます。
- 遠隔地間で、学生が全開発プロセスに主体的に参加します。
- インターネットを利用して綿密な議論を行う共同研究形態であり、これまで殆んど実施されてきませんでした。
- インターネットを最大限活用して空間の壁を克服しようとする本モデルは、製品開発など綿密な打ち合わせを要する共同研究を遠隔地間、あるいは国際間で実施する場合、非常に有用となります。
- 地方大学が遠隔地であることのハンディーを克服して民間企業と共同研究を実施する場合のモデルとなります。
従って、本プロジェクトは、三大学の連携を研究面で進展させていく契機になると期待できます。