
| 日時 | :平成29年2月18日(土)14:30〜17:30 |
|---|---|
| 会場 | :田辺市文化交流センター たなべる 2階大会議室 |
たなべ未来創造塾修了式は、真砂田辺市長、鈴木富山大学理事・副学長、講師陣、田辺市関係者、富山大学関係者、協力金融機関、後援機関、神島高校、魚津市関係者、高岡市関係者など約75名が参加し、塾生11名による最終プレゼンテーションとポスターセッション、修了証の授与、座談会が行われ、約8か月にわたり開催された「たなべ未来創造塾」の全カリキュラムが終了した。

開会にあたり、主催者を代表して、たなべ未来創造塾長の真砂充敏田辺市長からは、7月の開講後、様々な講義を踏まえ、ようやく本日の修了式を迎え、塾生の皆さんがどのようなビジネスブランを発表されるのか大変楽しみにしていること、これまで塾の運営について、富山大学をはじめ、金融機関や関係団体の皆さんに多大なご支援を頂いたことへの感謝の言葉を込めたメッセージが伝えられた。
富山大学鈴木理事・副学長からは、ビジネスプラン発表はあくまでもスタートであり、講義を通じて学んだことを、どのように生かして、ビジネスを実践していくかが重要であると伝えられた。
また、神島高校の生徒が出席していることにも触れ、高校生の手本となるようなビジネスプランの発表を期待しているとのエールが送られた。
| 田辺市たなべ営業室 企画員 鍋屋 安則 |

「たなべ未来創造塾」の取組のきっかけとなった「価値創造プロジェクト」における戦略ビジョン・戦略プランの取組から開講までの経緯を紹介し、地域課題の解決や地域資源の活用をビジネスの視点で考える人材の育成とビジネスモデルの創出を目指すという塾の目的を説明したうえで、これまでの講義を通じて、どのようなことを学んできたかということについて写真を交えながらポイントを解説した。
また、発表するビジネスプランはあくまでもコンセプト・ストーリーであり、収支計画等の詳細については、今後ブラッシュアップしていく必要があること、そのために、金融機関や商工会議所・商工会の支援が必要であることを伝え、プレゼンテーションを聞いて頂くうえで、「地域課題と企業課題を同時に解決しているか」「自社や地域の強みを生かしているか」について、特に注目して聞いて頂きたいと述べた。
| 一言アピール |
塾生が作り上げたビジネスプランについて、1人3分の時間内で事業内容の要点、概要などを発表、ポスターセッションへと続く一言アピールを行った。

11名の塾生がビジネスプランを1枚にまとめたポスターの前に立ち、来場者の方々に向けて個別にプレゼンテーションするポスターセッションが行われた。
塾生は、来場者からの質問に個別に答えるとともに、アドバイスにも耳を傾け、ビジネスプランに対しての反応や手ごたえを感じていた。


日本政策金融公庫主催の「高校生ビジネスプラン・グランプリ」において、全国2,662件もの応募の中、神島高校が提案したビジネスプランがベスト100に入賞されたことから、入賞作品のほか、合計3つのビジネスプランについて発表を行った。
「副産物としての梅酢の可能性 -梅やきとりを日本全国へ-」
「津波対策アプリの開発」
「世界遺産体験学習ツアー&体験型オーナーシェアリング -
Iターン者とともにおこなう地域づくりのために-」
高校生は直ちに起業できるというものではないが、自分で考えて、課題を解決して、発信するということに取り組んで頂きたいという思いで、「高校生ビジネスプラン・グランプリ」を始めた。
神島高校の皆さんのビジネスプランは、地域のことを一生懸命考えた素晴らしいプランで、これを自分たちだけでなく、大人に聞いてもらいたいという思いから、この場を提供して頂いた。とコメントした。
たなべ未来創造塾長の真砂市長から塾生一人ひとりに修了証が授与された。
| テーマ | 田辺の未来を創る力とは |
|---|---|
| パネリスト | 真砂 充敏(たなべ未来創造塾長・田辺市長) 鈴木 基史(富山大学理事・副学長) 塾生11名 来場者の皆さま |
| 話題提供 | :鍋屋 安則(たなべ未来創造塾事務局・たなべ営業室企画員) |
| コーディネーター | :金岡省吾(富山大学地域連携戦略室長・教授) |
座談会では、「田辺の未来を創る力とは」をテーマに、塾生が発表したビジネスプランの内容や、たなべ未来創造塾の役割・可能性などを話し合った。
11名の塾生から、たなべ未来創造塾に参加した感想や今後の抱負が述べられ、鍋屋企画員からたなべ未来創造塾の役割と来年度に向けた新たな取組についての話題提供があった。 その後、真砂市長が市の立場から、鈴木理事・副学長が大学の立場からたなべ未来創造塾の講評を行うとともに、協力機関や後援機関、ご来場の皆さまからコメントを頂き、修了式を終えた。

2週間に一度、3時間の都合をつけるのが大変だった。経験則だけではこれからの時代は乗り切っていけないという思いがあり、よい機会となった。

いろんな人と知り合え、いろんなことを学び、それを地域に持って帰り、共有しながら地域活性化を図っていきたい。

これまで薄々感じていたことを講義を通して学ぶことで、課題を見つめ直すことができ、それにより次への対策が見えてきた。早くビジネスプランを完成させて、地域に還元していきたい。

これまで、デザイナーに何ができるのか迷いもあったが、熊野古道など地域のすばらしさを伝えるためには、デザイナーが必要で、可能性があると実感できた。

地域の中に、これだけ地域をよくしたいという人がいることに田辺市の可能性を感じた。今後、塾生同士のつながりが生きてくると思う。

東京から移住して間もないときに声をかけてもらい、塾に参加したが、いろんな人とのつながりができた。また、自分の経営を見つめ直す機会となった。

これまで「あかん、暇や」というようなネガティブな話しを聞く機会が多かったが、これからは、こうやったらビジネスプランができるよ、というようなポジティブな発信をしていきたい。

塾を通じていろんな人とつながることができた。素晴らしい人と出会うことで人は成長していく。これからもいろんなことを学び、この地域を良くしていきたい。

新しいことを取り入れながら、古い良いところを残しつつ、というのがこれから生き残るためには一番大切だと感じた。やるかやらないかで悩んだときはやることにしようと思っている。

普段、考えないことをたくさん考える機会となった。塾生同士でいろんな話をすることで、絆が深くなった。これからがスタート。プランを実現させたい。

普段、企業課題や地域課題を考えることがない中、よい機会となった。同じ志をもった塾のメンバーとのつながりを今後も大事にしていきたい。田辺をますます盛り上げていきたい。

今の皆さんのコメントを聞いて、自分の課題や地域の課題を見つめ直すというプランを発表するまでのプロセスが大事だと感じた。
地方にとって課題のベースになっているのは、人口減少問題。ある意味、人口減少を一定受け入れながら、少ない人口でどう生きるか、もしくは定住人口が増えないということになれば、交流人口を増やす。これしかないとこれまで言ってきた。
こうした中で、観光、福祉、林業、様々な分野にわたる課題をビジネスで解決しようとする具体策を示して頂いたことは大変心強い。
今回の皆さんのプランを成功させないといけない。そのためには、お互いが応援し合うことが大切。地域も行政も、皆さんの挑戦を支援していかなければならない。

開講式の時の顔と今の顔は全然違う。自信に満ち溢れている。数年前から魚津市や高岡市でこうした取組を進めてきたが、今回、それ以上のものが出たのではないか。
今すぐにでも実践できるものもあるし、コラボすることで、よりいいものができる可能性もある。
そのため、市、金融機関、商工会議所、商工会は是非支援をお願いしたい。
また、修了生は次の塾生を育てて頂き、2期、3期と息の長い取組となることを期待している。

魚津市では、平成23年から魚津三太郎塾の取組をはじめ、5期、48名もの修了生を輩出し、そのうち、25名が何らかの動きをスタートさせている。また、修了生がお互いにブラッシュアップさせる組織として「魚津三太郎倶楽部」が立ち上がり、ギフトカタログの取組などがスタートしている。

高岡市では、3期、25名の修了生を輩出。知らない間に塾生同士、また講師などとつながりができ、助け合いが生まれている。
次期からは、近隣市町村と連携して、運営していく予定。
田辺市では、高校生が参加したり、講師が出席していたりと高岡市にはない取組をしており、参考になった。

魚津三太郎塾の3期生で、魚の競り人をやっている。私も塾に参加して、楽しかったし、仲間ができ、非常に良い機会を与えて頂いたと思っている。
金岡先生からは、「自分で考えろ」ということと、「漁協の競り人は地域のために何ができるか」ということをいつも言われていた。
そのため、漁協が事業主体となり、地域課題を解決していこうという取組をスタートさせることとした。

地域と国の政策をつなぐ金融機関として、融資課長の高橋を中心に、塾生へのヒアリングやアドバイスなど「たなべ未来創造塾」の取組を支援してきた。
こうした中で、今日、皆さんのプレゼンを聞いて、演習のときよりも数段良くなっていることにびっくりした。
高校生の皆さんも、新鮮な発想で考えられ、素晴らしいプランだった。
これが、スタート。商工会議所、金融機関などと相談しながら実現に向けて取り組んで頂きたい。

非常に若い力を感じた。これからは、実際に事業をすること、そして安定させることが大切になってくる。紀陽銀行は地域密着型金融として、仕入れや販路、事業計画の作成など、様々な支援に取組んでいるため、是非、相談して頂きたい。

素晴らしいプレゼンだった。それぞれの立場で課題をビジネスプランに反映させている。商工会議所としても、是非支援をしていきたい。

塾生の皆さんは、この塾で学んだことを、是非、今後に生かして頂きたい。
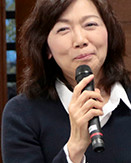
皆さん、試しにお金を借りてみましょう。金融機関はビジネスとして成立しないものにはお金を貸さない。そこで、理論構築するために、商工会議所の経営指導員がいる。
今日のコンセプトプランをビジネスプランにブラッシュアップして頂きたい。
また、この事業を是非続けて頂きたい。地域活性化への一番の近道ではないかと思う。

多くのことを悩み、素晴らしいプランができたと思うので、これを形に変えて成功することで、みんなが田辺に帰ってきたいと思えるまちに近づくのではないか。
行政は、この取組を続けてほしい。同志がこれだけできるというのは素晴らしいし、心強いと思う。お互い応援し合いながら、是非やって頂きたい。

神島高校では、5年前からビジネスの視点での取組を進めてきた。専門的な知識はないが、これまで生徒と相談しながら手さぐりで取り組んできた。
生徒たちは、進学や就職で地域を離れる子もいるが、先々でいろんなスキルを積んで、この地域に戻ってきてくれればと思っている。
| 池田副市長 |
|---|

田辺市は、合併して12年目を迎えた。今から4年前に、市長から次の10年を見据えた取組が必要だということで、「首都圏プロモーション」と「戦略ビジョン・戦略プランの策定」という2本柱で取組を始めた。
その際に、巡り合ったのが金岡先生。富山と田辺という距離的な問題はあったが、これまで多大なご協力を頂き、今日を迎えることができた。今期は12名の修了生だが、これが20名、30名と広がり、田辺のリーダーとなって頂きたいという思いで始めた取組で、今後も、引き続き、お付き合いをお願いしたい。と総括し、修了式を締めくくった。