
| 日時 | :平成28年7月16日(土)14:30~17:00 |
|---|---|
| 会場 | :田辺市文化交流センター たなべる 2階大会議室 |
富山大学地域連携推進機構と田辺市の共同主催により、地域課題の解決や地域資源の活用をビジネスの手法で考える人材の育成とビジネスモデルの創出を目指した「たなべ未来創造塾」の開講式が行われ、平成29年2月までの約7ヵ月間にわたる取組がスタートした。
開講式には塾生のほか、主催の田辺市、富山大学地域連携推進機構、協力機関である金融機関や後援機関、マスコミ関係者ら約50名が参加した。

開会にあたり主催者を代表して「たなべ未来創造塾」塾長、真砂充敏田辺市長が「世界文化遺産や世界農業遺産をはじめとした多くの地域資源を有する一方、地域の担い手不足や空き家の増加、外国人観光客の増加に伴う宿泊先の不足などの地域課題を抱えている。こうしたことを塾生の皆さんがチャンスと捉えて、新たなビジネスモデルを生み出して頂くとともに、地域のリーダーとなって地域を牽引して頂けることに期待している。」と挨拶した。
続いて、共同主催である富山大学地域連携推進機構、鈴木基史機構長が「富山大学では、大学が一体となって取り組んでいこうと、地域連携戦略室を設置し、県内の市町と連携し、地域課題解決に向けた取組を進めているが、県外の田辺市との取組は大学としても新たな挑戦となる。」と話し、塾生に対しては、「どこかにビジネスへのヒントがある。講義を通じて自らが考えることが重要だ。」と挨拶した。
| 富山大学地域連携戦略室長 金岡省吾 |
| 田辺市たなべ営業室 鍋屋安則 |

「たなべ未来創造塾」の開講にあたり、金岡教授から富山大学では「魚津三太郎塾」や「たかおか共創ビジネス研究所」などを通じて、ビジネスリーダーの育成、新たなビジネスの創出に取り組む中で、地域活性化の中核拠点としての役割を果たしてきた経緯を説明した。また、地域づくりでは、従来のボランティア的な要素が強いCSRから、持続可能な地域づくりには企業の営利活動との共通項、ビジネスの視点で考えるCSVへの転換が必要であるとして、全国の先進事例や国土形成計画など国の動向を紹介しながら、取り巻く環境が変化しているとした。
田辺市たなべ営業室鍋屋企画員からは、全国平均より早いスピード人口減少が進み、内需に依存した経済構造を持つ田辺市にとって、「交流人口の増加」「地域経済の活性化」に向けた取組が必要で、そのため、「たなべ未来創造塾」を重点事業と位置づけ、富山大学地域連携推進機構と「人材育成の連携に関する覚書」を締結し、具体化してきた経緯を説明。「たなべ未来創造塾」の概要では、カリキュラムの構成や演習の手順を説明した後、修了式では塾生自らがビジネスプランを発表することを共通認識した。

| テーマ | 「田辺の地域資源の活用と地域課題の解決を目指したビジネス創出の可能性」 ~世界遺産・世界農業遺産をビジネスに~ |
|---|---|
| パネリスト |
真砂充敏 (たなべ未来創造塾長 田辺市長) 鈴木基史 (富山大学地域連携推進機構長) 多田稔子氏(田辺市熊野ツーリズムビューロー会長) 玉井常貴氏(秋津野ガルテン代表取締役社長) 田上雅人氏((株)たがみ専務取締役) |
| コーディネーター | :金岡省吾(富山大学地域連携戦略室長) |

「世界遺産では外国人観光客が増加し、間もなく闘鶏神社などが追加登録されるなど、大きなチャンスを迎えている。また、昨年には梅産業が世界農業遺産に登録され、他にも多くの地域資源に恵まれている。
2年間、こうした魅力をまずは知ってもらおうと首都圏を中心としたプロモーションを実施してきたが、次の段階として、これを経済に結び付けていくことが大切。
塾生の皆さんには、こうしたことをニーズもしくはビジネスチャンスと捉えて、新しいビジネスモデルを生み出してくれること、またビジネスリーダーとして地域を牽引してくれることを大いに期待している。」

「大企業の中でもこれまでのCSRではなく、CSV、ビジネスにつなげることで社会貢献をしていくという考え方が広がりを見せている。塾生の皆さんには地域にとって何が足りないか、ニーズがどこにあるのかを考える中で、新たなビジネスを模索してもらいたい。講義を通じて塾生同士でディスカッションしていくことで新たな発想が生まれる。」

「地域活動をしていると地域課題が次々に出てくる。そのため、地域資源の活かし方として4つの視点を考えた。まず1点目は人材育成、2点目は組織(コミュニティ)の活用、3点目は産業をどう生かすか、4点目は歴史や文化をこれら三点にどう絡ませるか。こうした視点で取り組むことで、秋津野ガルテン等のソーシャルビジネスにつながっていった。
塾生の皆さんは、自分の引き出しをしっかりと持つこと。今、何が大事なのかをしっかり考えること、そうしたことの積み重ねが無理のない新しいビジネスへと繋がる。」
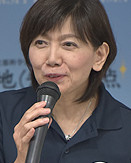
「田辺市熊野ツーリズムビューローはインバウンドに向けてプロモーションを実施してきたが、その一方で受け入れ態勢が整っていないことに気づき、来て頂ける仕組みを作るため、ビジネスとして旅行業をはじめることとなった。
これからのビジネスは世の中に何か足りないもの、不都合なもの、こうしたものを解決することで生まれてくるのではないかと思う。世の中の変わり目にこそチャンスがある。」

「熊野米の取組については、農商工連携、6次産業化の事例として様々紹介して頂いているが、まだまだ課題も多い。そのため、毎日進化していくこと、やり続けること、使命感を持って取り組むことを常に意識して取組んでいる。これまで成功も失敗も繰り返してきたが、塾生にはそのすべてを話したい。」と熱いエールを送った。
| 富山大学理事・副学長 鈴木基史氏 |
|---|

富山大学地域連携推進機構鈴木機構長が「田辺は非常に魅力的な資源が多い。こうした資源を活用し、新たなビジネスが生まれることを大いに期待している。修了式では一回り成長した皆さんの姿が見れることを楽しみにしている。」と締めくくった。