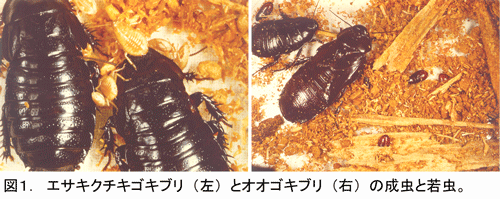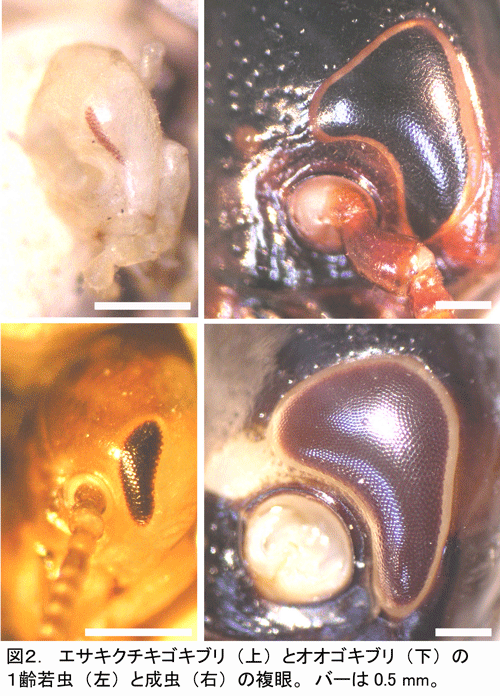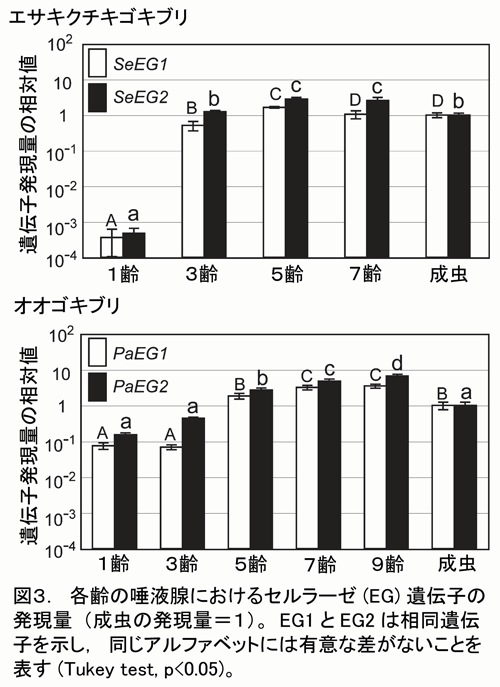|
|
Research Topics [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
2. 食材性ゴキブリが示す社会性と若虫の発達
日本で最も忌み嫌われている昆虫は,恐らくゴキブリでしょう。しかし日本には50種ぐらいのゴキブリがいて,そのほとんどが森の中でひっそり暮らしているということは,実はあまり知られていないのではないでしょうか。ここで紹介するクチキゴキブリとオオゴキブリも,そのような人目に付かない生活をしている種類で,一生を朽ちた木の中で生活する食材性のゴキブリです (図1)。両者は系統的には近縁で (同じ「オオゴキブリ亜科」に属します:Maekawa et al., 2003),どちらも生活史の全てを腐朽木に依存していますが,各々の社会構造は大きく異なっています。クチキゴキブリは,一夫一妻と子虫からなる家族で営巣することが知られていますが,オオゴキブリは,明確な家族構造を持たず,多数の個体が集まって営巣する集合性を持っています。したがってオオゴキブリ亜科は,近縁群でありながら異なった社会性を持つようになった進化的な背景を探る上で,非常に有効なグループであると考えられます。
ところで,ゴキブリなどの脱皮を重ねて成長する不完全変態昆虫では,卵から孵化した時の個体の発育程度が,種によって大きく異なることが知られています。そのような発育程度の違いは,親の保護の有無に関係すると考えられます。つまり,親の保護が発達した種では,子虫は極めて未熟な状態で孵化しますが (晩成性),親の保護がない種では,孵化直後に独立して活動できる (早成性) ということですが,昆虫類でそれが確かめられた例はありません。クチキゴキブリとオオゴキブリは,分布場所が重なる場合 (例えば屋久島) では,同じ腐朽木から見つかる場合もあるので,両者が利用する餌の質や捕食圧などは類似していると考えられます。したがって,両者の大きな違いは社会性にあるので (クチキゴキブリ:一夫一妻の家族性,オオゴキブリ:集合性),子虫の発達状態と社会性との関係を考察できることが期待されます。そこで,屋久島から九州にかけて分布するエサキクチキゴキブリSalganea esakiiと,屋久島以北の本州全域に分布するオオゴキブリPanesthia angustipennisを材料に,1齢若虫の発達状態を比較しました。
その結果,オオゴキブリの方がエサキクチキゴキブリよりも,クチクラ外皮は堅く硬化して色素もより沈着しており,各々の成虫と比較した複眼の個眼数も,有意に多くなっていました (図2; Nalepa et al., 2008)。また,木材の分解に必須な酵素であるセルラーゼの遺伝子発現量を比較したところ,エサキクチキゴキブリの1齢若虫は,成虫の1/1000以下の発現量しか検出されなかったのに対して,オオゴキブリの1齢若虫では,成虫の1/10程度の高い発現が確認されました (図3; Shimada & Maekawa, 2008)。したがってオオゴキブリは,成虫とほとんど変わらない高いセルロース分解能力を持ち,より発達した状態で孵化する早成性な種であることが強く示唆されます。
クチキゴキブリでは,吐き戻し物質を親が子虫に渡す行動が観察されており (Maekawa et al., 2008),栄養源として利用しにくい木材を,子虫が摂取しやすい形に加工処理していると考えられます。これらの結果は,分解や利用が難しい材を餌とする食材性ゴキブリにおいて,1齢若虫を取り巻く社会的・物理的な環境は親の世話によって大きく変わり,その結果として個体の発生の仕方も変わりうる (早成性←→晩成性) ことを示唆する結果であると考えています。[前川清人,2008年9月29日]
<参考文献>
Maekawa K, Lo N, Rose H & Matsumoto T. (2003) Proceedings of the Royal Society of London B, 270: 1301-1307.
Maekawa K, Matsumoto T & Nalepa CA. (2008) Insectes Sociaux, 55: 107-114.
Nalepa CA, Maekawa K, Shimada K, Saito Y, Arellano C & Matsumoto T. (2008) Zoological Science, 25: 1190-1198.
Shimada K & Maekawa K. (2008) Sociobiology, 52: 417-427.
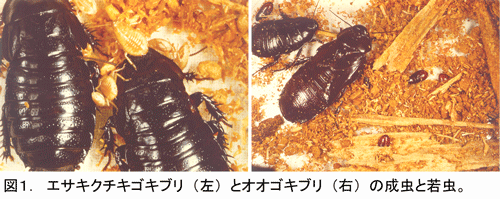
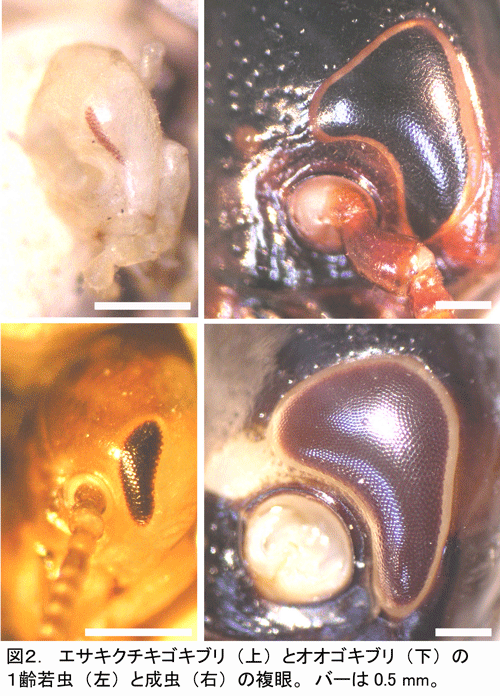
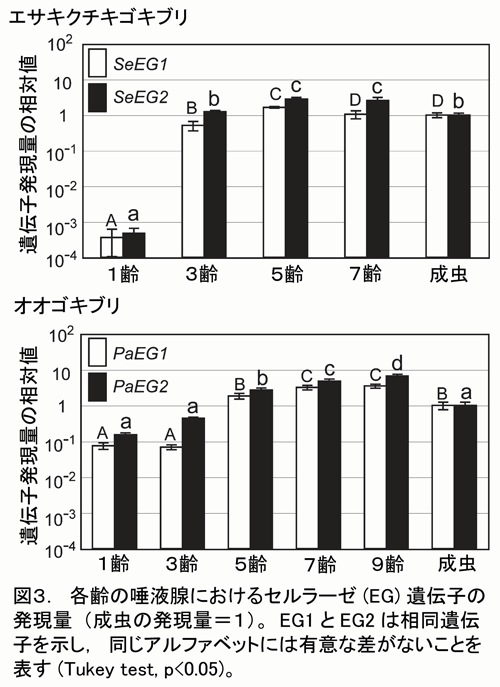
|